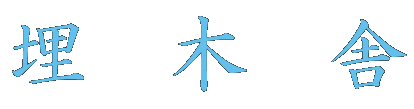やがて三月になりました。源氏の君は、
「それにしても、ずいぶんひどいことをするものだ。まさかあの大将がこうまできっぱりとけじめをつけるとは思いもよらず、油断につけこまれたのが口惜しくてならない」
と、人の手前も体裁悪く、玉鬘の君にことがどうしてもお心から離れなく、恋しく思い出されるのでした。
「前世からの縁などというものは、粗末には出来ないものだけれど、自分があまりにもうかつすぎたために、こんなにもひどい苦しみを味わわねばならないのだ」
と、寝ても覚めても恋しい人の面影を思い浮かべていらっしゃいます。
髭黒の大将のような風情も愛想もない夫に連れ添っているのでは、軽い色めいた冗談を言うのさえ遠慮されて、また面白くないともお思いになって、源氏の君は怺
えておいでになります。
雨がひどく降って、所在のない折、こうした退屈を紛らわすのにいい所としてお出かけになり、親しくお話しなさった玉鬘の君のお姿などが、たまらなく恋しくなられたので、お手紙をさし上げました。右近うこん
の所にこっそりおことづけになりながらも、一方では右近がどう思うだろうかと気がかりなので、何もくわしくはお書きになれず、ただ読む人の推量にまかせてぼんやっりお書きになりました。 |
かきたれて
のどけき頃の 春雨はるさめ に ふるさと人を
いかに偲しの ぶや
(しとしとと降る
こののどやかな春雨に 旧ふる
い馴染みのわたしのことを いったいあなたはどんなふうに 思い出してくれるのでしょう) |
|
「雨の所在なさにつけても、恨めしく思い出されることばかり多いのを、今となってはそれをどうして申し上げることが出来るでしょう」
などと書かれています。髭黒の大将のいないすきに、右近がこっそりこのお手紙をお見せしますと、玉鬘の君は、しみじみと泣かれて、自分の心にも、時が経つにつれて思い出される源氏の君のお姿を、実父ではないのであからさまには
「恋しい、何としてでもお逢いしたい」
などとは、とても申し上げられない親なのですから、ほんとうにどうしてお目にかかることも出来ようかと、思えば悲しくてなりません。時折、こちらを困らせるような色めいたお振舞いをお見せになったのを、疎ましいとお思いしたことなどは、この右近にも打ち明けてはおりませんので、お心じとつに収めてひそかに悩んでいらっしゃったのでした。右近も実は薄々お二人の仲はお察ししていたのでしたが、ほんとうのところは、どの程度の関係があったのか、今もって腑ふ
に落ちないでいるのでした。お返事は、
「さしあげるのもお恥ずかしいけれど、このままでは失礼だから」
と、お書きになります。 |
ながめする
軒のしづくに 袖ぬれて うたかた人を 偲ばざらめや
(長雨の降る軒の雫のような 涙に袖を濡らしながら ほんのしばらくの間も
なつかしいあなたを お偲び申さずにおりましょうか) |
|
「久しくお目にかかれず月日が過ぎますと、仰せのように、ひとしお所在ないわびしさもつもるように思われます。あなかしこ」
と、ことさらに礼儀正しく堅苦しくお書きになりました。源氏の君は、お返事をお開きになって、軒の玉水のこぼれるように自然に涙があふれ落ちるのを、人に見とがめられたら具合が悪いだろうと、さり気ないふりをなさるのですが、胸が一杯になるお気持です。
あの昔、朧月夜おぼろづきよ
の尚侍ないしのかみ を、朱雀院の母后が無理に逢わせないように、強いて隠して二人を引き裂かれた時のことなどをお思い出しになりますけれど、今はさしあたって、目の前のことだから、玉鬘の君のことは、世にたとえようもなく悲しくお心がひきつけられてやまないのでした。
「色好みな人は、自分から恋の苦労を求めてやまないものだ。髭黒の大将の妻になっているのに、今更何のために気苦労を抱え込むことがあるものか。あの人はもう自分にはふさわしくない恋の相手ではないか」
と、あきらめようとなさっても、やはりあきらめられないので、お琴を掻き鳴らされますと、あの玉鬘の君がやさしくお弾きになった爪音つまおと
が自然に思い出されるのでした。
和琴をすが掻きに軽くお弾きになって、玉鬘の君のことをせつなく思い、 「玉藻はな刈りそ」 と興にまかせてお歌いになっていらっしゃいます。その御様子も、恋しいあの方にお見せしたら、きっとおなつかしさにお心を動かされるにちがいないと思われます。
帝におかせられても、ほのかに御覧になられた玉鬘の君のお顔やお姿をお忘れになれず、
<くれなゐの赤裳あかも
垂れ引き去い にし姿を>
と、あまり品のいい歌ではありませんけれど、それがお口癖になっていらっしゃるのか口ずさまれて、物思いに沈んでいらっしゃるのでした。お手紙は、人目を忍んでその後も時々お遣わしになられました。
玉鬘の君は、自分の身の上をつくづく情けないと心にしみてお思いになり、こうした軽い気持のお歌のやりとりなども気が乗らず、打ち解けたお返事もさしあげません。やはりあの源氏の君の、世にも稀なお心の深さを、何かにつけしみじみ有り難くお思いになったことがお忘れになれないのでした。 |