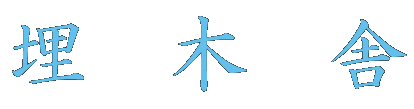| 藤 袴
(四) | すでに尚侍
に任官された玉鬘の姫君は、だんだん奥へ逃げ込みながら、厄介なことになったと思っていらっしゃるので、夕霧の中将が、
「冷たい御態度ですね。無体な間違いなど起すようなわたしでないことは、これまでで充分分かっていらっしゃる筈でしょうに」
と言いながら、こんなついでに、もう少し自分の気持を訴えたいとお思いになりますけれど、玉鬘の姫君は、
「どうも気分が悪くなりまして」
と、とうとう奥へ入っておしまいになりました。夕霧の中将は、深い嘆息を洩らしてその場をお立ちになりました。かえって、言わでものことを打ち明けてしまったと、夕霧の中将は後悔なさいます。それにしても、この姫君より、もっと深く切なく心に沁みているあの紫の上のお姿を、これくらいの物越しにでもいいから見たい、せめてほのかなお声なりと、何とかしてよい機会をとらえて聞きたいものと、悩ましい気持に心を乱しながら、南の御殿に戻っていらっしゃいました。源氏の君がお出ましになりましたので、玉鬘の姫君のお返事などをお伝えになります。
「それでは今度の宮仕えに、あまり乗り気ではないのだね。螢ほたる
兵部卿ひょうぶきょう の宮みや
など、女の扱いはいたってお上手な方が、深い思いのたけを見せてお口説くど
きになるので、そちらに心を奪われてしまわれたのだろうか、それならお気の毒なことだ。けれども大原野おおはらの
の行幸ぎょうこう の時、帝をお拝みなさってからは、本当に御立派でいらっしゃると思っていられたのだ。若い娘なら、ちらとでも帝のお顔を拝したら、とても宮仕えの話をいやとは思えないだろう。わたしはそう思ったからこそ、宮仕えの話もこのように進めたのだが」
とおっしゃいます。夕霧の中将は、
「それにしても、あの姫君のお人柄は、一体どこに落ち着かれるのがふさわしいのでしょう。秋好あきこの
む中宮ちゅうぐう が、こんなふうに、お一人抜きん出ていらっしゃる上に、また弘徽殿こきでん
の女御にょうご が貴い御身分で、格別の御君寵をお受けですから、玉鬘の姫君をどんなに帝がいとしくお思いになられても、中宮や弘徽殿の女御と肩を並べるというのは、無理な話でしょう。また螢兵部卿の宮はやいそう御執心のようですから女御としての御入内じゅだい
ではないとしても、尚侍などで宮仕えにお出しになったら、宮は御自分のお気持を無視されたと、御気分を損じられはしないでしょうか。父君とは仲のよい御兄弟の間だけに、そんなことになれば大変お気の毒に思われます」
と、大人びたことをおっしゃいます。
「まったくむずかしいものだね。わたしの一存で自由にできる人のことでもないのに、あの髭黒ひげくろ
の大将までが、わたしを恨んでいるそうだ。何につけ、ああした気の毒な有り様を見るに見かねて面倒を見てしまい、そのため人からとんでもなお恨みをかうのは、かえって軽率な行為だった。あの人の母君の可哀そうな遺言を忘れられなかったところへ、あの姫君が淋しい山里に住んでいるなどと聞き、また、
『内大臣が相談に乗って下さりそうもない』 と泣きついて来たので、不憫ふびん
に思って、こうしてこちらに引き取ることにしたわけなのだ。わたしがこうまで大切にしていると聞いて、内大臣も人並みの扱いをなさるようだよ」
と、さも本当らしくお話しになります。
「姫君の人柄は、螢兵部卿の宮の北の方としていかにもふさわしいと思う。現代的でたいそうあでやかな上、いかにも聡明で、間違いなど起しそうもないから、夫婦仲も安心だろう。また一方、宮仕えに上っても、きっと立派に任務をやりとげると思う。器量もよく、可愛らしいけれど、公おおやけ
の職務についてもよくわきまえ、判断がしっかりしていて、帝がいつもお望みになっていられた人物に適かな
うに違いない」
などとおっしゃいますけれど、夕霧の中将は、源氏の君の真実の気持が知りたくて、
「今までこうして御養育なさったお気持を、世間では変なふうに噂しているようです。あの内大臣まで、そんなことを匂わせて、髭黒の大将が、つてを求めて、あちらへ姫君との結婚を申し込まれた時にも、そんなふうにお返事なさいましたとか」
と申し上げますと、源氏の君はお笑いになって、
「世間の噂も内大臣の推量も、どちらも全くお門かど
違いというものだ。宮仕えにしても何にしても、結局は内大臣が得心なさって、こうしようとお決めになったことに従わねばなるまし。女には三従の道があるというのに、父親に従うという順序を違たが
えて、わたしの勝手にするなどということは、あり得ないことだ」
と、おっしゃいます。
「内大臣が内輪話におっしゃるには、 『六条の院には御身分の高い女君たちが前々からたくさんいらっしゃるので、この姫君をその方々のお一人として同じ扱いには出来かねるため、半分は捨てるつもるでわたしにこうして姫君を押し付け、普通の宮仕えをさせておいて、実は思い通り自分のものにしようというお考えなのだ。いやはや頭の切れる、才覚のあるやり方だ』
と、お喜びになっておいでとか。ある人から確かに聞いた話なのです」
と、夕霧の中将は実に生真面目な調子でお話しになりますので、なるほど内大臣はそんなふうに推察しておられるかも知れないと、、お気の毒になって、
「ひどく邪推なさったものだね。何にでもよく気を廻される御性分のせいだろうよ。そのうち自然に分かってくることがあるだろう。全く勝手な想像というものだ」
と、お笑いになります。その御様子はきっぱりとしていらしゃいますが、夕霧の中将はまだ疑いを捨てていません。源氏の君も、
「やはりそうだったのか。皆がそう推量しているのに、その通りになったりしたら、それこそ残念至極で、みっともない話だ。あの内大臣に、なんとかして、自分の心の潔白な次第を知らせたいものだ」
と、お考えになります。
「いかにも、表向きは宮仕えという形にして、自分の恋心をまわりに気づかれぬようにごまかしていたのを、恐ろしくも見抜かれてしまったものよ」
と、気味悪くお感じになります。
|
|
|