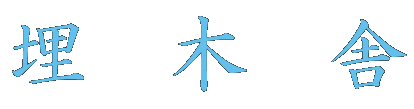夕霧の中将は、前々から何とかして玉鬘の姫君のお顔を見たいと、憧れつづけていました。
今、源氏の君が、さも楽しそうに姫君と話しこんでいらっしゃるのを見て、隅の間の御簾のそばに、乱雑に置かれた几帳の端を、そっと引き上げて内部
を覗きました。見通しの邪魔をする調度類は、すっかり取り除いてあるので、奥まで実によく見通せます。源氏の君が姫君にこうして戯たわむ
れていらっしゃる御様子もありありと見えます。
「変なこともあるものだ。親子とはいえ、こんなふうに懐に抱かんばかりに親しくしてよい、年頃でもあるまいに」
と目が吸いつけられてしまうのでした。そんな覗き見の姿を、源氏の君に見とがめられはしないかと怖ろしいのですけれど、この思いがけない異様な光景に気も動転して、なおよく目を凝らしていますと、玉鬘の姫君が柱に隠れて少し横を向いていられたのを、源氏の君が御自分の方に抱き寄せられます。姫君のお髪ぐし
がその時一方になびき寄って、はらはらとお顔にこぼれかかるのでした。その時、女君もとても厭いや
がり困った様な表情を見せながら、それでも一向に抵抗せず、実に素直に源氏の君に寄りかかっていらっしゃるのです。それを見ると、おふたりはもうよほど馴れ馴れしい間柄におなりなのでしょう。
「いやはや、何と疎うと
ましいことだ。一体これはどうしたことなのだろう。父君は色事にかけてはまったく抜け目のない御性分だから、生まれた時からずっとお側近くでお育てにならなかったから、実の娘でもこんな色めいたお心もお持ちになられるのだろうか。そういうことも普通のこととしてあり得るのか。それにしても、ああ何といやなことだ」
と、思う自分の心まで、夕霧の中将は恥ずかしくなります。
玉鬘の姫君のお姿は、ほんとうに同じ姉弟きょうだい
とはいっても、少し距離を置いた腹違いの姉弟ななおだと思ったら、心得違いの邪恋もきっと起さずにはすまないだろうと、思われるほどの魅力があります。昨日、垣間見た紫の上の御様子には、どことなく劣っていますけれど、見ただけでこzひらがほほ笑ましくなる愛らしさは、充分肩を並べられそうに見えます。
八重山吹やえやまぶき
の咲き乱れる花盛りに、霞がかかって、それが夕暮の残照に映えている美しさが、とっさに思い出されます。季節にふさわしくない喩たと
えですけれど、夕霧の中将にはやはりそういう印象なのでした。花の美しさには限度があります。中にはほつれ乱れた蘂しべ
なども交じっていますが、姫君の容貌の美しさは、たとえようもないのでした。
玉鬘の姫君のお前には、女房も誰も出て来ませんので、たいそう親しそうにしっとりと源氏の君は小声で話しかけていらっしゃいました。ところがどうしたにか、急に真面目なお顔つきでお立ちになります。女君が、 |
吹き乱る
風のけしきに 女郎花をみなえし
しをれしぬべき ここちこそすれ
(吹き乱れる風の勢いに女郎花は 今にもしおれてしまいそう わたしはあなたの ひどいなさり方に
今にも死んでしまいそう) |
|
と口ずさむそのお声は、夕霧の中将にはよく聞き取れないのせすけれど、源氏の君がそれをそのままお口ずさみになるのを、かすかに聞きますと、いまいましいと思いながらも興がそそられ、やはりこの成り行きを、終わりまで見とどけたいと思います。けれども源氏の君に、近くに居たのだと悟られまいと思って、そこを立ち去りました。
その歌への源氏の君のお返事には |
した露に
なびかましかば 女郎花 荒き風には しをれざらまし
(人目につかぬ下露に 靡なび
いていたなら女郎花 荒い風にも折れまいに あなたもわたしにこっそり 靡いていたらよいものを) |
|
「なよ竹を見てごらんなさい」
などと、おっしゃったとか。聞き違えだったのでしょうか、何にしても外聞のよいお言葉ではなかったようです。
源氏の君は、東の花散里の君の所へ、ここからお訪ねになります。野分の後の、今朝方の急な肌寒さに思い立った家事仕事なのか、裁縫などしている老女たちが、女君のお前に大勢集まっています。
細櫃ほそびつ
のようなものに、真綿を引っかけて、手で扱っている若い女房たちもいます。とてもきれいな朽葉くちば
色の薄絹や、濃い紅梅色の、またとないほど美しい艶つや
を、砧きぬた で打った絹など、そこらにひき散らかしていらっしゃいます。源氏の君は、
「夕霧の中将の下襲したがさね
ですか。せかっく用意なさっても宮中の壺前栽つぼせんざい
の宴もおそらく中止になるでしょう。こんな吹き荒れた後では、何も出来ないでしょう。おもしろくない秋になりそうですね」
などとおっしゃいます。さまざまな布地の色が、たいそうきれいなのを御覧になって、
「どういうものに仕立てあげられるのだろう。こうした染色や裁縫といった面では、花散里の君は、紫の上にも引けをとらないだろう」
とお思いになります。
源氏の君のお召料としての御直衣は、花模様を織り出した綾を、この頃摘つ
み取って来た花で、薄く染め出していらっしゃいます。それがほんとうに申し分のない色合いなのです。
「わたしよりも、中将にこんなふうに染めてお着せになるのがいいでしょう。この二藍ふたあい
は若い人の色にふさわしいようです」
などとおっしゃって、引きあげていかれました。 |