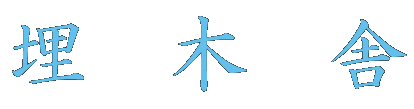夕霧の中将は、源氏の君のお供をして、気のはる方々を次々お訪ねして廻って、何だか気分がふさいでしまいました。それで、書きたい手紙なども書かないでいるうちに、日が高くなってしまったので、遅くなったのを気にしながら、明石の姫君のお部屋へいらっしゃいました。
「姫君はまだあちらの紫の上のお側にいらっしゃいます。風をこわがっておびえられて、今朝はまだ起き上がることもお出来になりません」
と、乳母
が夕霧の中将に申し上げます。
「ひどい荒れ模様の風だったので、昨夜はこちらで宿直とのい
をしようと思っていましたが、大宮がとてもおいたわしそうにしていらっしゃったので、参れませんでした。御人形の御殿は御無事でしたか」
とお訊きになりますので、女房たちは笑いながら、
「扇の風が吹いて来てさえ大変だとご心配なさいますのに、昨夜は今にも吹きこわれそうなほどの大風が荒れました。この御殿のお守もり
には、全く手を焼いております」
などと話します。中将は、
「何か、大げさでないちょっちした紙はありませんか、それにお部屋の硯すずり
とを」
とお頼みのなりますと、女房は、姫君の御厨子みずし
の中から、紙一巻を取り出し、硯箱の蓋ふた
に入れてさし上げました。
「いや、これでは畏おそ
れ多くて」
と、中将はおっしゃいましたが、北の御殿の明石の君の格を考えると、そう遠慮するにも及ばないという気がして、そてに手紙をお書きになります。紙は紫の薄様うすよう
でした。墨を心をこめて磨す り、筆の先を注意して見い見いしながら、丁寧に書き、時々筆をとめて書き案じていらっしゃるお姿は、ほんとうにすばらしく見えます。けれどそのお歌は妙に紋切り型で、感心しないお詠みびりでした。 |