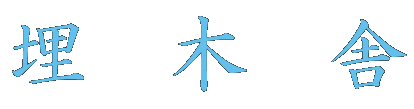| 常 夏
(五) | 西の対
にお出かけになることも、あまり度重なり、女房たちに見とがめられそうにもなると、源氏の君も、さすがに御自分のお心のやましさに自制なさり、行くのを控えられます。そんな折は、何かの用事をこしらえて、お手紙を絶え間なくお届けになります。ただもう玉鬘の姫君のことばかりが、明けても暮れてもお心にかかっていらっしゃるのでした。
「どうして、こんなしてはならない理不尽な恋をして、心の安らぐ閑もない辛つら
い悩みをするのだろう。もうこんな苦しい思いはしたくないと、思い通りに姫君を自分のもにしてしまったら、どんなに世間から軽薄だと非難されることか。自分の不面目はまあいいとしても、ただこの姫君のためにはお気の毒なことになるだろう。またこの人を限りなく愛するといったところで、紫の上への愛情と並ぶような扱いは、とても出来ないことは自分でも分かっている。もし妻にしたところで、そういう紫の上以下に立場では、どれほどの幸せがあろyか。自分だけは格別の身分とはいえ、大勢の妻妾たちのなかで、末席に仲間入りするのでは、あまりほめられもしないだろう。それならいっそ平凡な納言なごん
あたりの身分の者から、ひとりだけ愛されて大切にされる方が、はるかに幸せだろう」
と、御自分でもよくお分かりになりますので、姫君がひどく不憫ふびん
になられて、
「いっそあの螢火ほたるび
に想いをつのらせた兵部卿ひょうぶきょう
の宮みや か、熱心に言い寄る右大将などと結婚させてしまおうか。そうして自分から離れ、夫の邸やしき
に引き取られて行ってしまったら、この切ない恋心も断ち切れるだろうか。あの人たちと結婚させるのは、いかにもつまらないが、いっそ思い切って、そうさせてしまおうか」
と、お考えになる時もあるのでした。けれども、西の対にお越しになって、玉鬘の姫君の美しいお顔を御覧になり、今ではお琴をお教えになることまでも口実にして、馴れ馴れしく姫君に、いつまでも近々と寄り添っていらっしゃいます。
玉鬘の姫君も、はじめの頃こそ、気味悪く、疎うと
ましくお思いになられたものの、こうしてお側近くにいらっしゃっても何事もないので、心配するような変なお気持はなかったのだと、次第に源氏の君にお馴れになって、そうひどくはお嫌いにもなりません。そうした折のお返事も、打ち解けすぎない程度にやさしくなさいます。
お逢いになる度に、玉鬘の姫君は、ますます愛らしい魅力を増していらっしゃり、御器量もmすます匂うばかりに美しくなっていらっしゃいますので、源氏の君は、やはりこのままではすまされないと、お気持が逆もどりしてしまわれるのでした。
「それならいっそ、このまま、六条の院でお世話しつづけて婿を取り、ここに通わせて、適当な機会には人目をしのんでこっそり忍び逢い、せつない気持を訴えて、心を慰めることにしようか。今のようにまだ男を知らない娘のうちこそ、靡なび
かせるのはなかなかで、可哀そうでもあった。しかし、いったん結婚してしまえば、たとえ夫という関守が厳しく見張っていても、女も自然男女の情が分かりはじめてくれば、こちらでも痛々しがらずにすみ、自分の恋心を思う存分訴えて、相手にそれが通じたなら、どんなに人目が多くても忍び逢うのに支障はないだろう」
などと、お思いつきになるのも、ほんとうに怪け
しからぬお心です。
「しかし結婚させてしまってから、ますます悩みが深くなり、ひたすら思いつづけているのも、さぞ苦しいことだろう。そうかといって、ほどほどに恋心をなだめていくというのは、何かにつけて、どう考えても難しい」
と、お考えになるのは、世にも珍しい面倒なお二人の間柄なのでした。 |
|
|