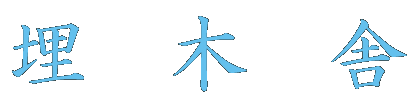巐寧堦擔偺堖峏偊偱丄恖乆偺壞偺堖徶偵栚怴偟偔夵傔偨崰偼丄嬻偺嬻婥偝偊丄柇偵壗偐偟傜忣弿偑昚偭偰偄傑偡丅尮巵偺孨偼偨偄偟偰屼梡傕側偔偍壣側帪側偺偱丄偄傠偄傠娗尲偺偍梀傃傪嵜偝傟偰丄帪傪偍夁偛偟偱偄傜偭偟傖偄傑偡丅
惣偺懳偺嬍椤偺昉孨偺強偵丄恖乆偐傜偺楒暥偑偩傫偩傫懡偔側偭偰偄偔偺傪丄傗偼傝婜懸捠傝偵側偭偨偲尮巵偺孨偼柺敀偑傜傟偰丄壗偐偵偮偗偰昉孨偺偍晹壆偵偍墇偟偵側偭偰偼丄偦傟傜偺楒暥傪屼棗偵側傝丄偍憡庤偵傆偝傢偟偄偲巚傢傟傞偍曽偵偼丄憗偔偍曉帠傪彂偐傟傞傛偆偵偲偦偦偺偐偝傟偨傝側偝傞偺偱偟偨丅昉孨偼偄偮擖偭偰棃傜傟傞偐傢偐傜側偄尮巵偺孨偵婥傪嫋偝偢丄崲偭偨偙偲偩偲偍擸傒偵側偭偰偄傜偭偟傖偄傑偡丅
暫晹嫧偺媨偑丄偍婥帩傪懪偪柧偗偰傑偩娫傕側偄偺偵丄徟
傟偰壵乆偄傜偄傜 偲崷傒偭傐偄嬸抯傪偁傟偙傟彂偄偰偙傜傟偨偍庤巻傪屼棗偵側偭偰丄尮巵偺孨偼夛怱偺徫傒傪偍楻傜偟偵側傝傑偡丅
乽戝惃偄偨傢偨偟偺孼掜偺拞偱傕丄偙偺暫晹嫧偺媨偩偗偼彫偝偄崰偐傜暘偗妘偰側偔丄偍偨偑偄偵偲傝傢偗拠傛偔偟偰偒偨偺偵丄偨偩偙偆偄偆亸楒偺摴偵娭偟偰偩偗偼媨偼偙傟傑偱傢偨偟偵傕偢偄傇傫塀偟棫偰傪偟捠偟偰偙傜傟偨傕偺偱偡傛丅偦傟側偺偵丄偙偺擭偵側偭偰偙傫側偵怓傔偄偰偄傞偍怱傪尒傞偲丄柺敀偔傕偁傞偟丄偍婥偺撆偵傕巚傢傟傞丅傗偼傝媨偵偼偍曉帠傪偝偟忋偘側偝偄丅懡彮偱傕嫵梴偑偁傝庯枴傪夝偡傞彈側傜丄偍偮偒偁偄偟偰偍榖憡庤偵側傞恖偲偟偰偼丄偁偺媨偺傎偐偵偼偁傞偲偼巚偊傑偣傫傛丅偲偰傕枺椡偺偁傞偍恖暱偱偡偐傜乿
偲丄庒偄彈側傜偒偭偲媨偵怱庝偐傟傞偵堘偄側偄傛偆側偍榖偟傪側偝偄傑偡偑丄嬍椤偺昉孨偼丄偨偩傕偆抪偢偐偟偑偭偰偽偐傝偄傜偭偟傖偄傑偡丅
旹崟傂偘偔傠
偺塃戝彨偼丄幚捈偦偺傕偺偱丄偟偐偮傔傜偟偄曽偱偡偑丄偙偺恖傑偱 乽楒偺嶳偵偼岴巕傎偳偺恖傕搢傟傞乿 偲偄偆尶偙偲傢偞
偦偺傑傑偵丄楒偺擸傒傪慽偊偰偙傜傟傞偍庤巻傕丄偙傟偼傑偨偙傟偱柺敀偄偲丄尮巵偺孨偼奆撉傒斾傋傜傟傞偺偱偡丅偦偺拞偵丄搨搉傝偺敄棔怓偺巻偵丄崄偵擋偄傪傗偝偟偔備偐偟偔偨偒偟傔偰丄偲偰傕彫偝偔寢傫偩庤巻偑偁傝傑偟偨丅
乽偙傟偼丄偳偆偟偰傑偨偙傫側偵寢傫偩傑傑側偺偐側乿
偲偍偭偟傖偭偰丄偍偁偗偵側傝傑偟偨丅
昅愓偼偠偮偵尒帠偱 |
巚傆偲傕
孨偼抦傜偠側 傢偒偐傊傝丂娾楻傞悈偵 怓偟尒偊偹偽
(傢偨偟偑偙傫側偵偍曠偄偟偰偄偰傕 偁側偨偼屼懚偠側偄偱偟傚偆 桸偒曉傞巚偄偱偄偰傕
娾娫偵偁傆傟傞悈偵偼 怓傕側偔擬偝偑傢偐傜偸傛偆偵) |
|
偲偁傞彂偒傇傝傕尰戙晽偱丄挷巕偵忔偭偰婥庢偭偰偄傑偡丅
乽偙傟偼偳側偨偐傜偺庤巻側偺乿
偲尮巵偺孨偼偍恥偒偵側傝傑偡偑丄昉孨偼丄偼偒偼偒偲偍曉帠傕側偝偄傑偣傫丅尮巵偺孨偼彈朳偺塃嬤傪偍屇傃偵側偭偰丄
乽偙傫側傆偆偵偍庤巻傪婑墇偝傟傞曽乆偺拞偐傜偄偄恖傪慖傃弌偟偰丄偍曉帠傪偝傟傞傛偆偵偟側偝偄丅怓偭傐偔晜婥側崱帪偺庒偄恖偑丄晄搒崌側偙偲傪偟偱偐偟偨傝偡傞偺偼丄偁側偑偪抝偺嵾偲偽偐傝偼尵偊側偄丅傢偨偟偺宱尡偵傛偭偰峫偊偰傒偰傕丄彈偐傜偺曉帠偑側偄偲壗偲椻偨偄忣偗側偄恖偩丄崷傔偟偄巇懪偪傪偡傞偲丄偦偺帪偼暘偐傜偢傗偺彈偩偲岥惿偟偑偭偨傝丄憡庤偑偝傎偳偱傕側偄恎暘偺彈側傜丄恎偺掱抦傜偢偺柍楃側偙偲傪偡傞側偳巚偭偨傕偺偩丅偦傟傎偳幏怱偟偰偄傞偲偄偆偺偱偼側偔丄壴傗挶側偳偵偐偙偮偗偰偝傝偘側偔憲偭偰偒偨庤巻偵偼曉帠傕偣偢丄憡庤傪岥惿偟偑傜偣傞傛偆偵偡傞偲丄偐偊偭偰抝偺擬偼偐偒偨偰傜傟傞偙偲偑偁傞丅傑偨丄彈偑曉帠傪偟側偄偐傜偲偄偭偰丄抝偑偦傟偭偒傝朰傟偰偟傑偆傛偆側偺偼丄彈偵偲偭偰壗偺嵾偑偁傞傕偺偐丅
側偵偐偺偮偄偱偖傜偄偵傆偲巚偄偮偄偨丄偄偄壛尭側楒暥偵傕丄怱摼婄偵憗乆偲曉帠傪偡傞偺傕丄傑偭偨偔柍梡偺偙偲偱偱丄偦傫側偙偲傪偡傞偲偐偊偭偰丄屻偱偳傫側嵭擄傪彽偔庬偵傕側傝偐偹側偄丅
壗帠偵傛傜偢丄彈偑怲傒傪朰傟帺暘偺巚偄捠傝偵偟偰丄傕偺偺忣庯傪傢偒傑偊婄偵傛偦偍偄丄晽棳傕傛偔夝偡傞傛偆偵抦偭偨偐傇傝傪巒廔偟偰偄傞偲丄寢嬊偦偺寢壥偼傠偔側偙偲偵側傜側偄丅暫晹嫧偺媨傗旹崟偺塃戝彨偼丄恀寱側傆傝傪偟偰丄偄偄壛尭側偙偲傪偍偭偟傖傞傛偆側偍曽偱偼側偄偺偱丄偙偺曽乆偵偼偁傑傝丄憡庤偺婥帩偑暘偐傜側偄傛偆側柍垽憐側懺搙傪偲傞偺傕丄昉孨偲偟偰偼帡崌偄傑偣傫丅偙偺偍擇恖傛傝恎暘偺掅偄恖乆偼丄憡庤偺楒怱偺傎偳偵墳偠偰丄偦偺恏偝愗側偝傕棟夝偟偰偁偘側偝偄丅傑偨丄怱恠偔偟偺搘椡偺悢乆傕擣傔偰偍偨傝側偝偄乿
側偳偲偍榖偟偵側傝傑偡偺偱丄嬍椤偺昉孨偼抪偢偐偟偑偭偰婄傪偦傓偗偰偄傜偭偟傖偄傑偡丅偦偺墶婄偑偙偺忋側偔旤偟偔尒偊傑偡丅晱巕側偱偟偙
偺嵶挿偵丄偙偺婫愡偺塊偆 偺壴廝偼側偑偝偹
偺憉傗偐側彫遢偙偆偪偒 傪彚偟偰丄偦偺怓崌偄偑尰戙晽偱恊偟傒傗偡偔丄暔崢側偳偼丄慜偵偼傑偩壗偲偄偭偰傕丄揷幧堢偪偺缈傂側
傃偨柤巆偑偁偭偰丄偦傟偑偁傝偺傑傑偺偍偭偲傝偟偨姶偠偵偍尒偊偩偭偨傕偺偱偡丅偲偙傠偑崱偱偼榋忦偺堾偺彈孨偨偪偺屼條巕傪尒廗偆偵偮傟偰丄恎偩偟側傒傕岰敳偗偰偒偰丄側傛傗偐偵側傝丄偍壔徬傕擮擖傝偵側偝傞偺偱丄偳偙偵傕晄懌側偲偙傠偑側偔丄偼側傗偐偱壜垽傜偟偔側傜傟傑偟偨丅偙傫側枺椡偺偁傞恖傪傒偡傒偡愒偺懠恖偵偟偰偟傑偆偺偼丄偳傫側偵巆擮偩傠偆偲尮巵偺孨偼偍巚偄偵側傝傑偡丅 |