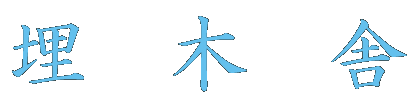夜が明けたので、皆で右近の知り合いの僧の宿坊に下りました。積もる話しを気がねなくゆっくりしようというつもりなのでしょう。姫君が旅疲れで御器量がやつれていらっしゃると思い。右近にきまり悪そうにしていらっしゃるお顔が、右近にこの上なくすばらしく見えます。
「わたしは思いもかけない高貴のお方にお仕えして、多くの方々とお会いしましたけれど、源氏の君の紫の上の御器量に並ぶお方は、あるまいと、長年お見受けしてまいりました。また、ほかにはそのお手許でお育ちになった明石の姫君の御様子が、当然のことながら、ほんとにこの上もなくお可愛らしいのです。源氏の君がその姫君を大切になさる御有り様も、並一通りではございません。こちらの姫君は、こうした旅疲れでおやつれなのに、そのお二方にひけをおとりにはなるまいとお見受けされますのは、めったにないお美しい御器量でいらっしゃいます。
源氏の君は、父帝の御代から、大勢の女御
やお后をはじめ、それより以下の身分の女君は残りなく御覧になっていらっしゃいますが、そのお目にも、今の帝の御母后おんははきさき
であられた藤壺の宮とこの明石の姫君の御器量とを、 『美人とはこうした人をいうのだろうと思う』 と、紫の上に話していらっしゃいます。わたしがその方々とこの姫君を比べて拝しましても、あの藤壺の御母后は拝したこともありませんし、明石の姫君はいくらお美しくても、なにしろまだお小さくて、御成人の後こそお楽しみなお方です。紫の上の御器量が、やはりどなたも肩をお並べになることは出来ないだろうとお見受けします。源氏の君も、紫の上を一番優れていらっしゃるとお思いなのでしょうが、さすがにお口に出されては美人の数の中にお入れになりません。
『このわたしと夫婦めおと になるなんて、あなたは分に過ぎていますよ」
など御冗談をおっしゃいます。そんなお二方の御様子をわたしが拝見いたしましても、命も延びるようで、ほかにこんなすばらしい御夫婦がまたといらっしゃるだろうかと思われるのです。
けれどもこちらの姫君は、その紫の上に比べても少しも劣っていらっしゃいません。ものには限度というものがありますから、いくらお美しいといっても、仏様のように頭上から光を放つようなお方はある筈もありません。ただ、この姫君のようなお方をこそ、すぐれた御器量と申し上げねばならないのでしょう」
と、にこにこして姫君に見惚れますので、乳母も嬉しくなります。
「こんなお美しい御器量なのに、すんでのことに辺境の片田舎に、御生涯を埋もれさせそうになったのです。それがもったいなくて、悲しくて、家や竃かまど
もうち捨てて、頼りになる息子や娘たちとも生き別れて、かえって見知らぬ他国のような気がする京に帰って来たのです。どうかあなた、はやく姫君をよい御運にお導き下さいな。高貴のお邸にお勤めなさるあなたは、自然、おつきあいの間には、何かとつてがおありでしょう。姫君のことが父君の内大臣のお耳に入り、お子さまのお一人として認められるような手はずをお考え下さいまし」
と言います。姫君は恥ずかしく思われて、背を見せていらっしゃいます。右近は、
「いえもう、つまらないわたしですが、源氏の君も、お側近くに召し使って下さいますので、何かの折々に、あのお小さい姫君はどうなさってことだろうと、お話し申し上げますのを、君はお心におかけ下さって、
『自分も何とかして探し出したいと思っているから、もし噂でも聞きだしたら、ぜひ知らせるように』 と仰せになります」
と言います。乳母は、
「源氏の太政大臣は、いくら御立派なお方でも、そういうれきっとした女君たちもおいでになります。まずは何よりも、実の父君でいらっしゃる内大臣にぜひお知らせ下さいな」
などと言います。右近は昔のいきさつなどを話しだして、
「源氏の君は、お方さまのことを、ほんとうに忘れられない悲しい思い出となさり、
『あの人の代わりに、忘れ形見の姫君のお世話をしたい。わたしは子どもが少なくて淋しいから、もしその姫君が見つかれば、自分の実の子を探し出したと、人には話しておくことにして』
など、前々からおっしゃっておいでなおです。あの頃は、まだわたしも一向に分別もなくて、何かにつけて気おくればかりする年頃でしたので、ようお探しもしないでいるうちに、あなたのご主人が大宰府の少弐になられたことは、人々がそうお呼びしているので知りました。御赴任の時、お暇乞いとまご
いに二条の院へおいでになった日に、ちらとお姿をお見かけしましたが、お声もかけずじまいになってしまいました。それにしても、姫君は、あの頃の五条の夕顔の咲く宿にお残しになって行かれたものとばかり思っていました。それがまあ、大変な。すっかり田舎人になっておしまいになるところだったとは」
などと、話し合いながら、その日は終日、昔話をしたり、念仏を唱えたり、読経したりして暮しました。そこは参詣に集まる人々の姿を眼下に見下ろせる場所で、宿坊の前を流れる川を初瀬川はつせがわ
というのでした。右近が、 |