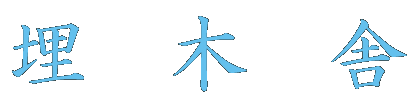あれから長い年月がはるかに過ぎ去ってしまったけれど、愛着のいつまでも尽きないあの夕顔のことを、源氏の君は露ほどもお忘れになりません。それじれに心ばえのちがうさまざまな女君たちと、次々恋を重ねてこられるにつけても、あのあの夕顔が生きていたならと、悲しくて残念でたまらなく思い出していらっしゃいます。
女房の右近
は、これといって取り立てて言うほどの女ではありませんけれど、やはり夕顔の形見とお思いになるので、いたわっておやりになります。今では古参の女房の一人として、あれ以来長く御奉公しているのでした。
源氏の君は須磨へ御流浪なさいました際、紫の上に御自分の女房たちをすっかりお預けになりました。それ以来、右近は紫の上にずっとお仕えしています。性質のよい控え目な女房だと、紫の上もお思いになりますけれど、右近は心の内で、
「亡き夕顔の君が御存命なら、明石の御方に負けないくらいの御寵愛は受けていられただろうに。源氏の君はそれほど深く愛していらっしゃらなかった方々でさえ捨てて磊落させず、こちんと末々までお世話なさるという気長なお方だから、夕顔の君ならなおさらのこと、高貴の御身分の方々と同列とはいかないまでも、この六条の院にお移りになられた女君たちの中には、お入りになったにちがいない」
と思うと、いつまでもあきらめきれず、悲しくなってくるのでした。
あの西の京に残された幼い姫君さえ、行方も知れません。あの夕顔の頓死の一件は、ひたすら自分からは洩らさずに秘密にしています。また源氏の君が今更言っても仕方のないことのために、自分の名を世間に洩らしてくれるなと、口どめなさったのに御遠慮していましたので、幼い姫君を探し出してお便りを差し上げるということもしなかったのでした。その間に、その乳母めのと
の夫が、大宰だざい の少弐しょうに
になって赴任したので、乳母も一緒に筑紫つくし
へ行きました。あの姫君の四つになる年のことでした。
乳母たちは、姫君の母君のお行方を知ろうと、あらゆる神仏にお願いして、昼夜恋い泣きしては、心当たりの方々ほうぼう
を尋ね捜しましたけれど、とうとうわかりませんでした。
「もうこうなっては仕方がない、せめて姫君だけでもあの方のお形見としてお世話申し上げよう。筑紫へ下るわびしい田舎の旅路にお連れして、はるばる遠くまで行っておしまいになるのは、ほんとにおいたわしい。やはり父君にそれとなく申し上げてみようか」
とは思いましたけれど、お知らせするよいつてもないうちに、
「母君のお行方も分からないのに、父君の頭の中将さまに、それを尋ねられたら何とお答えいたしましょう」
「まだ父君のお顔もよく覚えていらっしゃらないこんな小さい姫君を、やとえ引き取って下さっても、父君の許にお残しいていくのも、わたしたちは心配でたまらないことでしょう」
「頭の中将さまが御自分のお子とお分かりになってからは、姫君を連れて筑紫へ行ってもよいとは、とてもおっしゃる筈がありません」
などと、お互いにそれぞれ相談しあったあげく、たいそうお可愛らしく、もう今から気高くお美しく見える姫君を、ろくな設備もない粗末な船にお乗せして漕ぎ出した時には、ほんとうにお可哀そうに思われたのでした。
姫君は幼心にも母君のことを忘れないで、時々、
「お母さまの所へ行くの」
とお尋ねになります。乳母はそのため涙の絶えることもありません。乳母の娘たちも、夕顔の君を慕いこがれて泣きますので、船旅には涙は縁起でもないと、少弐は乳母たちを叱しか
ったりもするのでした。
道中、景色のよい所々を見ながら、
「姫君の母君はお気持が若々しくいらっしゃったから、こんんな道中のいい景色もお見せしたかったのに」
「さぞお喜びになったことでしょうね」
「でもあの方がいらっしゃれば、わたしたちは筑紫なんかに下らなかったことでしょうよ」
などと言って、何かにつけ、京のことばかりが思いやられて、返る波を見ても羨ましく、心細くなるのでした。船頭たちが荒々しい声で、
「うら悲しくも遠くに来にけるかな」
と歌うのを聞きますと、娘二人はさし向かって泣くのでした。
|
船人も たれをふとか
大島の うらがなしげに 声の聞こゆる
(荒くれた船頭たちも 誰を恋しがっているのか 大島の浦を漕いで行く今 うらがなしそうな
船歌の声が聞こえる)
来こ
し方も 行方ゆくへ も知らぬ
沖に出い でて あはれいづくに
君を恋ふらむ
(いずこからいずこへ 行方も知らぬ沖の海に 漂い流れるわたしの船旅よ あわれどこを目指して あなたを恋いもとめるのか)
|
|
都を遠く離れ、田舎へ旅する悲しさに、<鄙ひな
の別れにおとろへて> の歌を思い出し、二人はそれぞれ気晴らしに、こんな歌を詠よ
んでいます。
筑前の金かね
の岬みさき を過ぎてからは、
<金の御崎みさき を過ぎぬとも>
の古歌の、<われは忘れず> という言葉が、明けても暮れても口癖になってしまいました。
大宰府に到着しましてからは、ますます都との隔たりのはるかさを思いやって、乳母たちはひたすら京恋しさに泣きながら、姫君を御主人として大切にお仕えして明け暮れております。
乳母の夢に、ほんのまれに夕顔の君がお見えになる時などがありました。その度に前に見た時と同じ姿をした女が、お側に付き添っているのも見えます。夢が覚めると後まで気分が悪く、病みついたりしましたので、やはり女君はもうこの世にはいらっしゃらないのだろうと、だんだんあきらめてくるのも、とても悲しいことでした。
|