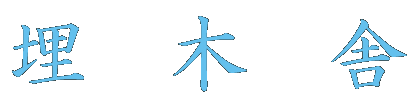二人でそれを見ていた時に、父の惟光がいきなりそこに来ました。恐ろしさに二人はあわてふためいて手紙を隠すことも出来ません。
「どういう手紙か」
と言って取り上げるので、娘は顔を真っ赤にしています。
「怪
しからんことをしたな」
と怒るので、兄が逃げて行くのを呼び戻して、
「誰の手紙か」
と問い詰めます。
殿の若君が、こうおっしゃってお渡しになったのです」
と答えますと、惟光はさっきの怒りはどこへやら、打って変わった笑顔になって、
「何とかわいらしい若君のお戯れ心ではないか。お前たちは若君と同い年なのに、話にもならないほどのぼんやり者だ」
などと若君をほめて、妻にもその手紙を見せます。
「この若君が、娘を多少とも人並みに思って下さるなら、あたりまえの宮仕えをさせるよりは、いっそこの若君にさし上げようではないか。源氏の君の女君へのお心がまえを拝見していると、いった愛情をおかけになったら、御自分からはお忘れになるまいとなさり、実に頼もしいのだ。わたしも明石の入道のようになれるかも知れないな」
などと言いますが、誰も相手にしないで、家人は宮仕えの支度に大わらわなのでした。 |