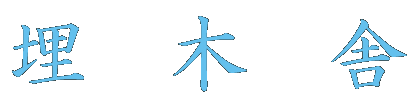大学にいる夕霧の若君は、あの時以来、ただもう悲しみに胸がふさがれて、食事もろくに召し上がらず、すっかり鬱
ぎこんで、書物も読まないで物思いに沈み込み、臥ふ
せっていらっしゃいましたが、少しは気分も紛れようかと、部屋を出てあちこちこっそりお歩きになります。若右は、御様子や御容貌が御立派で美しく、態度も落ち着いて優雅でいらっしゃるので、若い女房などはほんとうにすばらしいお方だと思って眺めています。
源氏の君は紫の上のお住まいのあたりへは、若君を御簾の前にさえまぢかにはお近づけになるようなお扱いはなさいません。御自分の色好みなお心臓に照らして、どうお考えになられてか、よそよそしいお扱いなのです。
主だった女房たちなぢにも親しい者はうないのですが、今日は五節の騒ぎに紛れて若君は西の対に入っていらっしゃったのでしょう。
舞姫を牛車ぎつしや
から大切に下して、廂ひさし の隅の間に屏風などを立てて、臨時の控え所を設けてあります。そこへ若君がそっと立ち寄ってお覗のぞ
きになりますと、舞姫はくたびれたように物に寄りかかっています。
ちょうど、雲居の雁の姫君と同じくらいの年と見えて、姫君よりもう少し背が高くすらりとして、姿かたちなどに風情があり、魅力は姫君よりまさっているようです。暗いからはっきりとは見えないのですが、その感じが姫君を思い出さずにはいられないように似ているので、心が移るというのではないのですが、胸が動揺して、自分の衣裳の裾すそ
をひいて、衣ずれの音をさせ、舞姫の注意をおひきになりました。舞姫は何も気づかず不思議そうにしていますので、 |
あめにます
豊岡姫とよをかひめ の 宮人も わが心ざす
しめを忘るな
(天にいます豊岡姫に お仕えする天女のあなたよ わたしが見初そ
め注連しめ を張り わがものと思い定めた心を
忘れないで下さい) |
|
「はるかな昔からあなたに思いをかけていたのです」
とおっしゃるのは、あまりにも唐突すぎます。若々しく美しい若君の声でしたけれど、舞姫は誰とも思い当たらないので、薄気味悪く思っているところへ、舞姫の化粧直しをしようと騒いでいた、介添えの女房たちが、忙しそうに近寄って来てざわめいてきましたので、若君はたいそう心残りのまま立ち去っていかれました。
六位の浅葱あさぎ
の袍ほう に引け目を覚えてこれまで参内もでず、鬱ふさ
いでばかりいらっしゃいましたが、五節にことよせて、直衣のうし
なども、浅葱とはちがう色も着ることも聴ゆる
されて宮中にいらっしゃいました。まだいかにも子供っぽく綺麗なお方ですが、そのわりにはませていらっしゃって、はしゃいであちこち歩いていらっしゃいます。帝よりはじめぢなたも、この若君を大切にされることは一通りではなく、またとはない御信望でございます。
五節の舞姫が参内する儀式は、どのお邸でもいずれ劣らず、それぞれにこの上なく立派になさいます。今年の舞姫も器量は、源氏の太政大臣と、按察使の大納言の舞姫が特に優れていると人々がほめそやします。なるほど二人ともたいそうな美人なのですが、おっとりして可憐そうな感じでは、やはり源氏の君の舞姫にはとてもかなう人はおりません。
この舞姫はいかにもきれいではなやかで、惟光の娘とも思えないくらいに美々しく装いたてている姿かたちが、稀に見る美しさなので、こうも誉めそやされるのでしょう。例年の舞姫よりは、皆少し大人びていて、今年はほんとうに格別な年なのです。
源氏の君も参内なさって御覧になりますと、その昔お心を惹かれた五節の乙女の姿を思い出されます。
節会の当日の辰の日暮れ方に、源氏の君は昔のあの舞姫の許にお手紙をおやりになります。御文面は御想像におまかせしましょう。 |
乙女子をとめご
も 神かみ さびぬらし 天津袖あまつそで
ふるき世の友 よはひ経へ ぬれば
(その昔天津乙女の
すら若い舞姫だったあなたよ 今は年をとられたことだろうか 天つ袖をひるがえした舞姫の 旧友だったわたしも老いたものだもの) |
|
| あれから後の長い歳月を数えて、ふとお思い出しになられた昔の恋のなつかしさを、とてもひとりでお忍びになれず、お届けになっただけのお手紙にすぎないものを、相手はそれに切なく胸をときまかせるのも、思えばはかないことなのでした。 |
かけて言へば
今日のこととぞ 思ほゆる 日蔭の霜の 袖にとけしも
(五節の舞にかけて お言葉いただけば 昔、日蔭のかずらをかけたわたしが 日ざしにとける霜のように
なびいたのも今日のことのようで) |
|
五節の君からのお返事は青摺あおずり
の紙に書かれていて、舞姫が当日着る青摺の唐衣からぎぬ
に趣向を合わせてあるのも気がきいています。誰か分からないように筆跡を変えた字は、墨の濃淡をつくり、平仮名に、それほど崩さない草仮名そうがな
を多くまぜて、散らし書きにしてあるのも、その人の身分のわりには趣があると御覧になります。
夕霧の若君も、惟光の娘が目にとまってからは、人知れず恋心を覚えて、会えないものかと、うろうろ歩き廻られるのですが、娘のまわり者は近くにも寄せ付けず、ずいぶん無愛想にしますので、何かにつけて気恥ずかしい年頃の若君は情けなくて、ただため息をついているだけで終わりました。
娘の顔だちが、しっかりと心に焼きついて、あの恋しくてならない雲居の雁の姫君に逢えない慰めにも、なんとかして五節の君と思いを遂げたいと思うのでした。 |