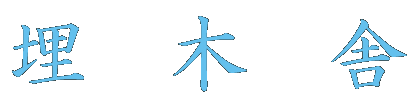内大臣はあれ以来、大宮のお邸にはお出かけにならず、大宮をたいそうお恨みしています。それでも北の方には、こんなことがあったなどとは、そぶりにもお見せになりません。ただ何かにつけひどく不機嫌なお顔つきでした。
「梅壺の中宮が格別華々しいお支度で、立后後に威儀を整え入内なさったので、弘徽殿の女御が、すっかり悲観して滅入っていらっしゃるのが、お可哀そうで見ていられない。いっそこの際、宮中から里に下がらせていただいて、ゆっくりこちらでお休みいただこう。后には立てなかったけれど、さすがに帝が夜昼お側にお引きつけになっていらっしゃるので、お付きの女房たちもくつろぐ閑がなく難儀だとこぼしているようだし」
とおっしゃって、急にお里へ下がらせておしまいになります。
帝から容易にそのお許しが出ませんのを、内大臣が不機嫌な態度で苦情を申し上げます。帝はまだしぶっていらっしゃるのに、内大臣は強引に女御をお里にお迎えになりました。
「こちらではさぞ御退屈でしょうから、大宮のところから姫君をお呼びになって、御一緒に音楽のお遊びでもなさいませ。姫君を大宮にお預けしておくのは安心なようですが、あちらにはもうそういうことが差し障りのある年頃になりましたので」
とおっしゃって、姫君を急にこちらへお引取りになります。
大宮はたいそう気落ちなさいまして、
「たった一人の娘だった葵の上が亡くなった後は、とても淋しく心細かったのに、嬉しいことにこの姫君をお預かりしたので、わたしの生涯の大切な宝物と思って、明け暮れにつけて、老いの身の辛さも慰めようと思っていたのです。それを心外なことにあなたが思いやりのないお心で、分け隔てなさるのが辛くてなりません」
と申し上げます。内大臣は恐縮して、
「わたくしが心にずっと不満に思っておりますことを、率直にそのまま申し上げただけです。どうして母上にひどい別け隔てなどいたしましょう。入内しております女御が、帝とのおん仲も思わしくなくて、先頃、里に下がってまいりましたが、まことに所在なさそうにふさいでおられますので、おいたわしく思っています。音楽の遊びごとでもなさって、気散じされるのがよかろうと思いまして。それで姫君にお相手させようと、ほんの一時、引き取るのです、ここまで御養育下さいまして、立派に成人させていただいた御恩は、決してあだ疎
かには思いません」
と申し上げます。こう思い立たれたからには、お止めしたところで考え直されるような内大臣の御気性ではありませんから、大宮はほんとうに飽き足らずに残念に思われて、
「人の心ほど情けないものはありません。あの幼い二人でさえ何かにつけてわたしに隠しごとをしていたのが憎らしいこと。それでもまあ、あの二人は子供のことで仕方がないとしても、大臣は思慮分別も深くわきまえていらっしゃるのに、わたしを恨んで、姫君をこうして引き取って連れ去ってしまわれるとは。あちらへ行ったところで、ここより安心ということもないでしょうに」
と、泣きながら仰せになります。
折も折、ちょうどそこへ夕霧の若君がお見えになりました。もしかしてほんのわずかな隙でもないものかと、この頃は足しげくお顔をお出しになるのです。
あいにく内大臣のお車があるので、気がとがめ、ばつが悪くて、そっと人目につかぬよう御自分のお部屋へお入りになりました。
内大臣の若君たちの左近の少将、少納言、兵衛ひょうえ
の佐すけ 、侍従、大夫たいふ
などという方々が、皆こちらにお集まりになりましたが、この方々が御簾の中に入ることは、大宮がお許しになりません。左衛門さえもん
の督かみ 、権ごん
中納言なども、異腹の御兄弟ですが、故太政大臣のお躾しつけ
どおり、今も大宮の所に参上して丁重にお仕えしていますので、そのお子たちもそれぞれお越しになりますけれど、この夕顔の若君の御器量の美しさには誰も敵かな
いません。
大宮は、この若君だけを誰よりも愛いと
しく思っていらっしゃいましたが、その他には、ただ姫君だけを、身近に慈いつく
しんで、大事になさり、いつもお側から離さず可愛がっていらっしゃいました。それなのにこうして姫君が行っておしまいになるのを、この上なく淋しくお思いになります。
内大臣は、
「今のうちに参内さんだい
して、夕方、迎えに参りましょう」
とおっしゃってお出かけになりました。今さらとやかく言っても仕方のないことだから、穏やかに話しをつけて、いっそ若君と結婚させてやろうかともお思いになりますけれど、やはろどうしても納得ができません。若君の官位が今より少しは高くなったら、一応一人前になった者と認めた上で、姫君への愛情の深さも見定めてから、許すとしても、改めて結婚の話しを持ち出し、きちんと婿として形をつけよう。今、いくらおさえ止めたところで、同じ邸に住んでいては、若い分別のない心のままに、見苦しいことも起こりかねないだろう。大宮もどうせきびしくお叱りになることもないだろうし、とお思いになりますので、弘徽殿の女御の御退屈にかこつけて、あちらにもこちらにも波立たないように上手に言いつくろって、姫君をお引取りになるのでした。 |