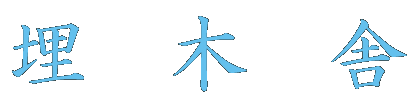乽偙偺揟帢偑媨拞偱摥偒惙傝偺崰偵丄屻媨偱孨挒傪憟偭偰偄傜傟偨彈屼丄峏堖偺曽乆偺塃偆偪丄偁傞曽偼朣偔側傜傟偰偟傑偄丄傑偨惗偒峛斻傕側偄傎偳忣偗側偄嫬嬾偵棊楫
偟偰偄傜偭偟傖傞曽傕偁傞傛偆偩丅偦傟偵偟偰傕丄偁偺摗氣偺擈媨側偳偼壗偲偍庒偔偍朣偔側傝偵側傜傟偨偙偲偐丅偼偐側偄柍忢偺悽偺拞偵丄擭偐傜偄偊偽梋柦偄偔偽偔傕側偝偦偆偱丄惈幙側偳傕愺偼偐偵尒偊偨偙偺揟帢偑惗偒巆傝丄怱惷偐偵暓摴偺偍嬑峴偮偲傔
側偳偟偰偙傟傑偱夁偛偟偰棃偨偲偄偆偺偼丄傗偼傝丄壗帠傕掕傔偺側偄悽偺拞側偺偩乿
偲偍巚偄偵側傜傟偰丄偟傒偠傒姶奡偵傆偗偭偰偄傜偭偟傖偄傑偡偲丄尮偺揟帢偼姩堘偄偟偰丄帺暘偺偙偲傪巚偭偰壓偝偭偰偄傞偺偐偲丄嫻偺偲偒傔偔巚偄偱丄婥傕偦偧傠偵庒傗偄偱偄傑偡丅 |
擭宱傆
傟偳 偙偺宊傝偙偦 朰傜傟偹丂恊偺恊偲偐 尵傂偟堦尵傂偲偙偲
(擭宱偰傕 孨偲偺宊傝 朰傜偟傚偐 偍慶曣忋偽偽偆偊
條偲偺 孨偺堦尵) |
|
| 偲揟帢偑怽偟忋偘傑偡偲丄尮巵偺孨偼寵偱偧偭偲側偝偭偰丄 |
恎傪偐傊偰
偺偪傕懸偪尒傛 偙偺悽偵偰丂恊傪朰傞傞 偨傔偊偟偁傝傗偲
(惗傑傟曄傢偭偰 偁偺悽偵偄偭偰傕 懸偭偰尒偰偄偰偛傜傫傛 偙偺悽偱恊傪朰傟傞
巕側偳偄傞偐偄側偄偐) |
|
乽枛棅傕偟偄宊傝偱偡傛丅偦偺偆偪備偭偔傝偍榖偟偟傑偟傚偆乿
偲嬄偣偵側偭偰丄偍棫偪偵側傝傑偟偨丅
惣柺偵偟偍傕偰
偺挬婄偺昉孨偺偍晹壆偱偼屼奿巕傒偙偆偟
傪壓傠偟傑偟偨偗傟偳丄尮巵偺孨偺偍墇偟偵側傞偺傪柪榝偑偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞偺傕偄偐偑偐偲巚偭偰丄堦丄擇枃傎偳偼奿巕傪偁偘偨傑傑偵偟偰偁傝傑偡丅
寧偑偝偄忋偑傝丄偆偭偡傜偲愊傕偭偰偄傞愥偑寧岝偵塮偊偰丄弔廐傛傝偐偊偭偰晽忣偺偁傞栭偺宨怓偱偡丅偝偭偒偺榁彈偺擭峛斻傕側偄撈傝寽憐偗偦偆
傕丄悽偵傕嫽偞傔側傕偺偺歡偨偲
偊偲偟偰傂偐傟偰偄偨偺偵丄偲巚偄弌偝傟偰丄崱栭偼偨偄偦偆恀柺栚側挷巕偱丄
乽偣傔偰堦尵偱傕丄婥偵擖傜側偄偲屼帺恎偱偍偭偟傖偭偰壓偝偄傑偟偨側傜丄偦傟傪偁偒傜傔傞傛偡偑偵偆偨偟傑偡偺偵乿
偲丄擬怱偵偍偣偑傒偵側傝傑偡丅
乽愄丄偍屳偄偵傑偩庒偔偰丄彮偟偖傜偄偺夁偪偼悽娫偐傜戝栚偵傕尒偰傕傜偊偨崰偵傕丄傑偨偦偺忋丄朣偒晝媨偑尮巵偺孨偲偺寢崶傪婜懸偟偰偄傜傟偨偺偵傕偐偐傢傜偢丄傢偨偟偼偟傫側偙偲偼傕偭偰偺傎偐偺偙偲偲抪偢偐偟偔巚偭偰丄偦偺榖偟傕棫偪徚偊偵側偭偨偺偵丄彈惙傝傕夁偓丄寢崶側偳偍傛偦晄帡崌偄側擭崰偵側偭偨崱峏丄堦惡側傝偲傕帺暘偺惡傪偍暦偐偣偡傞偺偼婥抪偢偐偟偔偰偨側傜側偄偩傠偆乿
偲巚傢傟偰丄堦岦偵昉媨偺偍婥帩偼備傜偓傕側偝偄傑偣傫丅尮巵偺孨偼丄側傫偲偄偆傂偳偄偍曽偐偲偍崷傒偵側傞偺偱偟偨丅
偦傟偱傕丄棫偮悾偺側偄傎偳抪傪偐偐偣偰丄撍偒曻偡偲偄偆懺搙偱傕側偔丄彈朳偵庢傝師偑偣偰堦墳偺偍曉帠偼側偝傞偺偱丄偐偊偭偰尮巵偺孨偼壵乆偄傜偄傜
側偝傞偺偱偟偨丅
栭傕偨偄偦偆峏傆
偗偰備偒丄晽偑楏偼偘 偟偔悂偒偮偺傝丄傎傫偲偆偵怱嵶偔姶偠傜傟傞偺偱丄尮巵偺孨偼桪夒側姶偠偱椳傪偙偭偦傝怈傢傟偰丄 |
忣偮傟
側偝傪 愄偵偙傝偸 怱偙偦丂恖偺偮傜偒偵 揧傊偰偮傜傟偗傟
(愄偵曄傢傜偸忣側偝偵 偁偒傜傔偒傟偢楒偄偙偑傟 崱側偍挦傝偸偙偺怱
崷傓愗側偝偄傗憹偣偽 傢偑怱偙偦側偍恏偔) |
|
乽偙傟傕帺暘偺怱偺偣偄側偺偱偡偗傟偳乿
偲丄尵偄偮偺傜傟傞偺傪丄
乽傎傫偲偆偵偛傕偭偲傕偱偡丅偁傫傑傝偍婥偺撆偱丄婥偑傕傔傑偡傢乿
偲丄彈朳偨偪偑椺偵傛偭偰怽偟忋偘傑偡丅 |
偁傜偨傔偰
壗偐尒偊傓 恖偺偆傊偵丂偐偐傝偲暦偒偟 怱偑偼傝傪
(崱峏偵偳偆偟偰 怱傪曄偊傜傟傛偆 偼偠傔偼嫅傫偱傕 怱曄傢傝偟偰側傃偔傛偆側
彈偺傑偹偼懴偊傜傟偸) |
|
乽愄偺怱傪曄偊傞側偳丄傢偨偟偼撻傟偰偍傝傑偣傫偺偱乿
偲丄偍摎偊偵側傞偽偐傝偱偟偨丅
尮巵偺孨偼丄偳偆偟傛偆傕側偔偰丄偝傫偞傫崷傒尵傪偍偭偟傖偭偰偍棫偪偵側傞偺傕丄偄偐偵傕戝恖婥側偄婥偑側偝偄傑偡偺偱丄
乽慡偔丄悽娫偺暔徫偄偵側傝偦偆側偙偺傢偨偟偺廥懺傪丄備傔備傔恖偵偼楻傜偝側偄偱壓偝偄丅
<偄偝傜愳偄偝偲摎傊偰傢偑柤楻傜偡側> 偲偄偆壧偺椺傪傂偄偰偍婅偄偡傞偺傕岤偐傑偟偄榖偱偡偑丄偁偺応崌偼擇恖偑宊偭偨屻偺壧偱偡偐傜偹乿
偲偍偭偟傖偭偰丄傑偩偟偒傝偵愰巪偵傂偦傂偦偲殤偝偝傗
偒偐偗偰偄傜偭偟傖傞偺偼丄壗偺偍榖偟側偺偱偟傚偆丅彈朳偨偪傕丄
乽傑偁丄傎傫偲偆偵栜懱傕偭偨偄
側偄丅偳偆偟偰昉媨偼偙偆傕傓偒偵側偭偰忣偠傚偆
偺側偄偍巇懪偪傪側偝傞偺偱偟傚偆丅尮巵偺孨偼寛偟偰寉乆偟偔柍懱側偙偲傪側偝傞屼條巕偼偍尒偊偵側傜側偄偺偵丄偁傫傑傝婥偺撆偱乿
偲尵偭偰偄傑偡丅偨偟偐偵彈朳偨偪偺尵偆捠傝丄偍恖暱偺偡偽傜偟偄偙偲傕丄偟傒偠傒曠傢偟偄偍曽偱偄傜偭偟傖傞偙偲傕丄昉媨偵偼偍傢偐傝偵側傜側偄傢偗偱偼側偄偺偱偡偗傟偳丄
乽偦偺偍怱偺撪傪傢偐偭偰偄傞傛偆側條巕傪偍栚偵偐偗偨偲偙傠偱丄偦傟傪悽娫偺懡偔偺彈偨偪偑丄尮巵偺孨傪傓傗傒偵傎傔徧偊偰偄傞偺偲摨楍偵丄尮巵偺孨偵巚傢傟傞偺偼偄傗偩偟丄傑偨偙偪傜偺愺偼偐側怱偺掙傕偡偭偐傝偍尒捠偟偵側偭偰偟傑傢傟傞偩傠偆丅壗偵偮偗偰傕偙偪傜偑抪偢偐偟偔側傞傛偆側屼棫攈側偍曽側偺偩偐傜乿
偲偍峫偊偵側傝丄
乽偙偺忋偍曠偄偟偰偄傞傛偆側傗偝偟偄懺搙傪偍尒偣偟偨偲偙傠偱偳偆偟傛偆傕側偄丅偙傟偐傜傕摉偨傝忈傝偺側偄偍曉帠側偳偼丄揔摉偵偝偟偁偘偰丄彈朳側偳傪捠偟偰偺偍曉帠側偳傕幐楃偵側傜偸傛偆婥傪偮偗偰丄偝傝偘側偔偍晅偒崌偄偟偰備偙偆丅偙傟偐傜偼丄挿擭嵵堾偲偟偰恄偵巇偊丄暓摴偐傜墦偞偐偭偰偄偨嵾柵傏偟偵丄偍嬑峴偮偲傔
偵傕惛傪弌偝側偔偰偼乿
偲巚偄棫偨傟傑偡丅偦傟偱傕媫偵尮巵偺孨偲偺偙偆偟偨偍晅偒崌偄傪丄懪偪愗傞傛偆偵怳晳偆偺傕丄偐偭偰巚傢偣怳傝偲尒傜傟傕偟偰丄恖偺塡偵忋傞偵堘偄側偄偲丄悽娫偺恖偺岥偝偑側偝傪抦傝恠偔偟偰偄傜偭偟傖偄傑偡丅偍懁偵偍巇偊偡傞彈朳偵傕婥傪偍嫋偟偵側傜偢丄偢偄傇傫婥傪偍尛偄偵側傝側偑傜丄師戞偵偍嬑峴偮偲傔
堦搑偵偍椼傒偵側傞偺偱偟偨丅 |