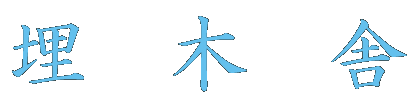お気持のおさまらないままお帰りになった源氏の君は、まして夜中にも目覚めがちに、思いつづけられます。
翌朝は早く御格子
を上げさせて、朝霧をぼんやりと眺めていらっしゃいます。枯れた秋の花々の中に、朝顔がそこここの何かに這は
いまつわって、あるかなきかのはかなげな風情でほのぼのと咲いています。その中で色艶もすっかりあせてしまったのを折りとらせて、朝顔の姫宮にお贈りになりました。
「昨夜のそっけなく冷たい待遇に、きまりの悪い思いがして、すごすご帰りました。その後ろ姿をどのように御覧になったことかと、恨めしくて、とはいえ、 |
見しをりの
つゆ忘らねぬ 朝顔の 花の盛りは 過ぎやしぬらむ
(昔お目にかかった時の 朝顔の花の美しさ 今も瞼まぶた
に残り忘れられない あの花の盛りは もはや過ぎ去ったであろうか) |
|
長い年月、積もり積もったわたしの恋の苦しさを、いくら何でも可哀そうだとくらいは、お思いになって下さるだろうかと、どこかで頼りにしております」
などと申し上げました。おだやかな落ち着いたお手紙の文面なので、お返事をさし上げないで気をもませるのも情味を解さないように見られるかと思われて、女房たちもお硯すずり
の御用意をしておすすめしますので、 |
秋果てて
霧の籬まがき に むすぼほれ あるかなきかに
うつる朝顔
(秋も過ぎ行き 霧の濃い垣根に しめやかにまつわりながら あるかなきかに色あせた 朝顔よわたしのような) |
|
「いかにもわたしの身にふさわしい花にたとえて下さいました。それにつけても涙の露に濡れております」
とだけ書いてあります。とりたてて気の利いたところがあるわけでもないのに、なぜか手放し難くて、源氏の君はそのお手紙を、いつまでも眺めていらっしゃいます。青鈍色の紙に、おだやかな筆跡の墨の色の濃淡は、なかなか美しく見えるようです。
大体こういう歌の贈答は、その人の身分や筆跡などに、欠点がとりつくろわれて、その時は欠点がないように見えても、それをもっともらしく書き伝えようとしますと、おかしいなと思うような点もあるようなので、さしでがましくとりゆくろって書き直したりしますうちに、どうでもいい加減なところも多くなっていることでしょう。
昔に返って、今更若い者のように恋文などをお書きになりますのは、御自分には不似合いなこととお思いになりますけれど、朝顔の姫宮がこんなふうに昔から、全く相手にもしないという冷淡さでもないのに、なぜか、思いを遂げることが出来なかったのが残念で、どうしても諦められないので、また今更のように熱心にお便りをさし上げています。
源氏の君は東の対にひとり人目を避けていらっしゃって、あの女房の宣旨をお呼びになっては相談相手になさいます。朝顔の姫宮にお仕えしている女房たちの中で、たいした身分でもない男にでもすぐ靡きそうな浮気女は、間違いでも起しかねないほどに、源氏の君をお讃めしています。ところが朝顔の姫宮はお若かった昔でさえ、全くその気がおありでなかったのに、今では尚更お互い色恋などには関われないお年でも、御立場もありますので、何気ない木や草につけての御返事などを、その折々の興趣をこわさない程度にしていらっしゃいます。それさえ軽率な振舞いと、世間に取り沙汰されはしないかと、人の噂を気になさって、姫宮は源氏の君にお親しくなさりそうな御様子は全くありません。相変らず昔のままに自尊心の高い姫宮のお気持を、世間の女たちとはずいぶん変わっていらっしゃると、源氏の君は珍しくも、いまいましくもお思いになります。
おふたりのこうした仲が、世間に漏れて、
「源氏の君が前斎院さいいん
の朝顔の姫宮に、熱心に言い寄っていらっしゃるので、叔母君の女五の宮なども喜んでいらっしゃるそうな。たしかにお似合いの御縁組みというものだろう」
などと噂しているのを、紫の上は人伝ひとづて
にお耳にされました。初めのうちは、
「まさかいくら何でもそんなことがあるなら、わたくしにお隠しになりはしないだろう」
とお思いになりましたけれど、さっそく気をつけて御覧になると、源氏の君のそぶりなどが、いつもに似ずそわそわして、心も上の空なのがわかります。
「さてはこんなに思い詰めていたのを、自分には何気なく冗談のようにごまかしていらっしゃったのかしら」
と思うと情けなくなります。
「あの姫宮は自分と同じ皇族のお血筋だけれど、昔から世間の声望もお高くて、格別重んじられた方だから、源氏の君のお心がそちらへお移りになったら、このわたしはどんなにみじめな目にあうだろう。これまで長い年月、肩を並べる人もないほど愛されて来たのに、今更、人に圧お
し除の けられるようになるとは」
と、人知れず悩みあぐねてお嘆きになります。
「すっかり見捨ててしまわないまでも、幼い頃から連れそって下さった心安さから、わたしを軽々しくお扱いになるかもしれない」
などと、あれやこれやと思い乱れていらっしゃいます。源氏の君の浮気がたいしたことでもない場合は、わざと恨み言を言ったりすねたり、憎らしくない程度に可愛らしく嫉や
いて責めたりなさるのに、今度は真実ひどいと恨んでいらっしゃるので、かえって顔色にもお出しになりません。
この頃、源氏の君は、ぼんやり外を眺めては物思いに沈んでいることが多く、宮中でのお泊りが重なり、朝顔の姫宮へお手紙を書くことだけが日課のようで、
「やっぱり噂は嘘ではなさそうだ。それならせめて一言でも、そのことをほのめかして下さればよいのに」
と、紫の上はただもう憎らしくて話しも聞きたくないとお思いになります。 |