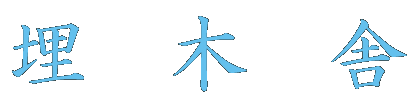源氏の君は、公の立場からしても、こうした高貴の方々ばかりが、たて続けにお亡くなりになろうとするのをお嘆きになります。藤壺の尼宮への人知れぬ恋愛の思いは、これもまた限りもないことで、延命にための御祈祷などは思いつく限りのことをなさいます。もうこの長年おあきらめになっていらっしゃった切ない慕情までも、もう一度お伝え申し上げないでしまうことが、たまらなく悲しくてなりませんので、御病床の傍らの御几帳
のもとに近寄られて、御容態などをしっかりした女房たちにおたずねになりますと、そうした側近の女房たちだけが控えていて、くわしくお話し申し上げます。
「ここ数ヶ月来御病気でいらっしゃいましたのに、み仏へのお勤行つとめ
を少しの間も怠らずおつづけになりました疲れが、おつもりになられて、一段とひどくお弱りになっていらっしゃいます。最近ではもう、柑子こうじ
みかんのようなものをさえお手になさらなくなりましたので、御快復の頼みを、何にかけていいかわからなくなってしまいました」
と、泣き嘆く女房たちが多いのです。藤壺の尼宮は、
「故院の御遺言どおりに、帝の御輔佐をなさり、御後見をして下さいます御厚意は、長年の青だ度々身にしみて感謝申し上げております。どうした折に、並々でない感謝の気持をお伝えしたらいいのかと、そのことばかりを、のんきに考えていたのですが、もう今となってはそれもかなわず、かえすがす残念で」
と、かすかな声でお取り次ぎの女房に仰おお
せになるのが、ほのかに漏れ聞こえて来ます。源氏の君はお返事申し上げることも出来かねて、お泣きになる御様子がなんともおいたわしい限りです。どうしてこんなに尼宮の御病気に気弱くなってお泣きになるのかと、まわりの人が疑うかも知れないと、こらえようとなさいますけれど、昔からの藤壺の宮のお姿やお人柄が思い出されますと、ああした特別の間柄を抜きにしましても、もったいなく惜しくてならないお方なのです。
人の定命じょうみょう
は自分の心の自由にならないものですから、この世にお引止めする方法もないのが、限りなく情けなく辛くてなりません。
「不甲斐ないわたくしではございますが、昔から帝の御後見を務めさせていただきますことは、精一杯心がけて一生懸命励んでまいりましたが、この度、太政大臣のおかくれになったことだけでも、世の中の無常迅速が感じられてなりません。その上にまた尼宮さままでがこのような御容態でいらっしゃいますので、何につけても心が惑乱してしまい、わたくしもこの世に生きているのはもう長くないような気持になります」
と申し上げているうちに、燈火ともしび
のかき消えるようにして、はかなくおかくれになってしまわれました。
源氏の君は何を言っても甲斐ないことながら、悲しさに堪えかねて激しくお嘆きになります。
高貴な御身分のお方の中でも、藤壺の尼宮は、世の中のすべての人に対して広く深いご慈愛をおかけになられる御性質でした。世間では権勢を笠に着て、下々の人を苦しめるようなことなども、自然ありがちなことですが、藤壺の宮にはそうしたことで間違いをなさるようなことは全くなく、人々が奉仕いたしますことも、世間に難儀をかけるようなことは、お止めになります。また仏事供養なども、人の勧めるままに、またとはないごど華々しく盛大になさる人々などが、昔の聖帝の御代みよ
にもよくあったものですが、藤壺の宮はそんなことはなさらず、ただ宮家の伝来の宝物や、毎年当然お受けになる年官ねんかん
や年爵ねんしゃく 、また御封みふ
などの御収入の中からさしつかえのない額だけをおあてになって、実に御信心の深い御供養を、最高に尽くされました。それだけに、何の分別もわきまえない山伏などまでが、尼宮の御崩御を惜しみ、心からお悔やみを申し上げるのでした。
御葬送の折にも、世をあげての騒ぎになり、御崩御を悲しまない者はありません。殿上人でんじょうびと
なども皆一様に黒っぽい喪服を身につけ、宮中も陰気にしめり、何をしても一向に映えない暗い晩春なのでした。
二条の院の前庭の桜を御覧になっても、源氏の君は昔の花の宴の時のことをお思い出しになります。
<今年ばかりは墨染すみぞ
めに咲け> という古歌をひとり口じさまれて、当然人が怪しみ、咎めますので、御念誦堂ねんずどう
にお籠もりになって、日がな一日泣き暮していらっしゃいます。
夕日がはなやかにさして、山際の木々の梢がくっきりと見えるところに、雲が薄く棚引たなび
いているのが、喪服と同じ濃い鈍色にびいろ
なのを御覧になりますと、この日頃は悲しみのあまり何一つお目にも入らないのに、たいそうしんみるともの悲しく思われます。 |