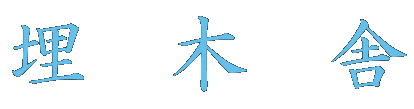藤壺の出家は、この物語の中での、最初の女の出家で、重大な意味を持つ。藤壺は、表面源氏を拒みながら、心の底では、源氏を愛していることを、これまでに作者は読者の充分さとらせてきている。
慈父のような優しい夫を裏切り、しかもその相手が、夫の実の息子だという宿命は、藤壺にとって罪の意識をいっそう深める。その上、不貞の証として子供まで妊もってしまう。その間の藤壺の苦悩については、作者はくだくだしい説明はしていない。しかし源氏に三条の宮邸で、執拗に迫られた時、絶命しかねないほど肉体が苦しむのを書き、藤壺の懊悩の深さを充分にわからせている。
藤壺が女を捨てて母となって生き、罪の子を帝位につけようと決意するまでの心の軌跡も、作者は一切はぶいている。夫をあざむき通そうと決意した藤壺は、それを源氏には一言の相談もしなければ匂わせてもいない。子供が源氏の子だということさえ、源氏には全く告げてはいない。
桐壺帝が、罪の子を抱き、源氏と瓜二つだと喜ぶところなどは、すべての事情を知っている読者にとっては滑稽である。コキュよいう立場はいずれにしろ、第三者の目には滑稽に映るものだ。しかし、将来、あざむいた父帝と同じ立場に源氏自身が立たされるなど、この時点で誰が予想出来よう。
藤壺はなぜ、ひとりで出家を決意したのか。源氏に洩らせば、必ず止められることを知っていたからだ。しかし東宮の身の安全を守るためには、源氏との情事は、どんなことがあっても天下に秘密にしなければならない。
これ以上、二人の関係がつづけば、ことが露見しない筈はない。その危険を防ぐには自分が出家するしかないと考えたのであった。源氏の情熱を防ぎきる自信がないことを、誰よりも藤壺自身が知っていたからだ。
この当時、仏教はまだ強い力を持っていた。仏教の戒律に対して、人々は畏怖を抱いていた。邪淫戒の恐ろしさは活きていた。物語が進むにつれ、源氏は恋の相手を見境なく手当たり次第に獲得する。しかし、源氏は生涯の中で、二つの恋の禁忌を守っている。
一つは出家した女、つまり尼は犯していない。
二つには、血の繋がった母娘の場合、母親と通じたら、その娘には決して手をつけていない。
また源氏自身も、出家したら色欲は断つべきものと考えていた。
藤壺が出家してしまえば、源氏はいくら藤壺に憧れていても、もはや藤壺と情交は結べないのである。
出家した藤壺とは、これまでとちがって、割合自由に逢え、遠慮がとれた話をするようになるということを、さらりと書いてあるのも、こうした約束ごとを踏まえてのことである。
藤壺は出家して以来、次第に、したたかな女に変貌する。ひとえにわが子を無事帝位につけることだけが生きる目的となり、そのためには源氏の後見を必要とするため、源氏の心情を惹きつけておくテクニックまで自然に具わるようになる。
円地文子さんは、源氏には常に自分よりすぐれた仰ぎ見る女が恋人として必要だったとして、その例に、藤壺、六条の御息所、朝顔の姫君を挙げている。六条の御息所も、朝顔の姫君も、満たされない藤壺への愛の身代りのようなものだという見解で、この説は説得力がある。
朧月夜との危険な情事は、平常の安全な恋には魅力を感じず、困難の伴う恋に限って情熱が燃えるという源氏の困った性格を代表している。あえて危険極まりない密会を右大臣邸で重ねるというのは、すっかり右大臣一派に圧迫され、不遇と退屈をかこつ不如意な身の上になった鬱屈が、はけ口を求めた結果とも考えられよう。自分への加害者に対して、その鼻を明かしているという快感が、この情事にスパイスの役目を果たしていたことは否めないだろう。
|