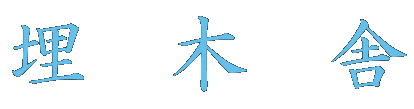源氏二十五歳の夏。橘の花が咲き、郭公
の鳴く五月二十日の話である。
桐壺帝の女御の一人に麗景殿れいけいでん
の女御という方があった。子供が出来なかったので、桐壺帝の亡き後は淋しい暮らしをしていた。源氏はそうした不遇の元女御を何かにつけて庇護してきた。この女御の妹の三の君を、宮中で、源氏はほんの軽い恋の相手として逢瀬を重ねたことがある。一度関係のあった女はわすれられないという性情のある源氏は、全くかえりみないという態度はみせず、とはいっても熱心な通い所にしているというのでもない。
五月雨さみだれ
の晴れ間に、源氏は女御のお邸を見舞おうとして出かけた。中川あたりまで来た時、気を惹かれるたたずまいに家の前にさしかかる。折から、邸の中から琴の音が洩れ聞こえて来る。興をそそられ源氏は邸の中を覗き込むと、そこは以前一度通ったことのある女の家だったと思い出す。
ずいぶん捨てておいたけれど覚えているだろうかと思っていると、たまたま郭公が鳴いたので、行きかけていた車を返し、歌を詠んで惟光これみつ
に届けさせる。女は今更という感じで、源氏を迎え入れようとはしない。
目的のお邸に行き、女御を慰めて話をしてから、本当の目的の、三の君の部屋を訪れる。
人格も容貌も何も書かれていないが、三の君はしっとりした落ち着いた雰囲気の女だということが伝わって来る。
この三の君は、次の
「須磨すま
」 の帳では 「花散里」 と呼ばれている。その夜女御と交わした 「橘の香か
をなつかしみほととぎす花散里をたづねてぞ訪と
ふ」 という歌の中の言葉をとったものだ。
この帖は、淡白なごく短い小編だが、
「葵」 「賢木」 と続いて来た重いねっとりした小説の後では、神経をほぐす間奏曲のような役目を果たしている。
花橘の匂う季節感が出ていて、読者は大して意味もない短編に、心を慰められるだろう。
まさか、この何の特徴もない花散里の君が、物語の終わりまで、源氏の最も心の安らぐ女として、愛されつづけるとは、読者は想像もしないことだろう。そうした布石をあらゆる所にちりばめるのも、紫式部の才能の一つである。 |