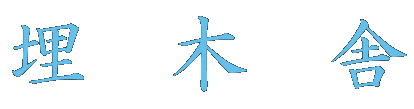末
摘つむ 花はな
(一) | 十七歳の源氏の君は奔放な恋愛遍歴の数々を経験した。
十八歳を迎えた源氏の君は、あのはかなく死んでいった夕顔ゆうがお
のことがなつかしく恋しく思い出され、またあの薄情な空蝉のことも時折思い出す。あまり気の張らない可愛い女はいないものかと思いつづけてりところへ、乳母めのと
の娘で好色なspan>大輔だいふ の命婦みょうぶ
が一つの情報を伝える。故常陸ひたち
の宮みや に姫君が一人残されていて、顔や性質はどの程度か知らないけれどひっそりと暮しているというのだ。姫君は誰とも会わず、琴きん
だけを友としているという。
源氏はたちまちこの姫君に興味を覚えて、大輔の命婦を口説き落とし、手引きさせる。
故常陸の宮が琴の名手として聞こえていたので、姫君も琴が上手だろうと、源氏は想像するのだ。梅の香のゆかしい十六夜いざよい
の月の美しい夜、荒れはてた葎むぐら
の生い茂った常陸の宮邸の庭に忍び込み、ほんの少し掻き鳴らす姫君の琴の音を忍び聞く。その後を宮中から尾つ
けてきた頭とう の中将ちゅうじょう
も、源氏と同じように荒庭に忍び込み、二人は顔を合わせてしまう。それ以来、頭の中将も源氏の鼻を明かそうと常陸の宮の姫君に恋文を送るようになった。二人への手紙は梨のつぶてで、姫君からは何の反応もない。
源氏は大輔の命婦の手引きでついに八月二十日過ぎに姫君と結ばれるが、姫君のあまりに初心うぶ
でぎこちない態度は魅力がなく、失望する。翌朝の後朝の手紙も気がのらず夕方やっと書く始末で、それっきり訪ねる気にもまらない。
責任を感じた大輔の命婦に責められて、公用の忙しさのおさまった頃、源氏は申しわけの様に幾度か姫君を訪ねた。いつでも後味の悪い失望感だけが残る。
やがて冬を迎え、源氏が久々に常陸の宮邸で一夜を明かした翌朝、外は一面の雪景色になっていた。雪の美しい景色を見るようにと誘った源氏の声に、素直ににじり出て来た姫君の顔を、雪明りにはじめて見た源氏は仰天する。胴長で座高が高い姫君の顔は馬面で、鼻が異様に長く垂れ下がっていて先が赤い。末摘花
(紅花) のような赤さである。
姫君のあまりの不器量さと、宮家の零落の様子に同情して、源氏はかえって見捨てられなく世話をつづける。 |
|
|