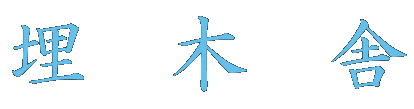その頃。朧月夜の尚侍
の君は、宮中からお里に退出なさいました。瘧病わらわやみ
を長くお悩みでしたので、呪まじな
いなどをお里で気楽になさりたいおつもりなのでした。加持祈祷をはじめて、快方に向かわれましたので、右大臣家では誰も誰もほっとなさり喜んでいる折から、例によって。これはめったにない機会だからと、源氏の君とお二人で、しめし合わされて、無理な算段をつけ、毎夜毎夜忍び逢いをなさっています。
尚侍の君は今まさに盛りのお年頃で、もともと豊満で華やかな感じのお方なのに、少し病におやつれになり、ほっそりとなさった御様子が何ともいえず男心をそそる風情がおありでした。
姉君の弘徽殿の大后おおきさき
も、同じ右大臣邸にお里帰りしていらっしゃる時でしたので、密会が見つかればとても恐ろしい筈ですけれど、源氏の君はこのような無理な逢瀬ほど、かえって情熱がつのる困ったお心癖なのです。こっそりと忍んで度々逢瀬を重ねていましたので、それとさとった女房たちもあるようですが、面倒にかかわりたくないので、誰も大后にこのことを内緒にして、申し上げません。右大臣はなおさら、夢にもご存じないことなのでした。
そんなある夜、雨がにわかに恐ろしい勢いで降りつづけ、雷もはげしく鳴り騒いだ夜明け方、右大臣家の御子息たちや、宮司みやづかさ
たちなどが立ち騒いで右往左往しますので、人目も多く、女房たちは怖じ恐れてあわてふためき、尚侍かん
の君のお側近くに集まって来ました。
源氏の君は尚侍の君の御帳台の中に閉じこもったまま、お帰りになる方法もないまま、たいそう困り果てているうち、すっかり夜が明けはなれてしまいました。御帳台のまわりも、女房たちが大勢つめかけていますので、源氏の君はほんとうに胸もつぶれそうな思いがしています。
事情を知っている女房が二人いて、これもただおろおろするばかりです。
そのうち、ようやく雷がやみ、雨もおさまってきた頃、右大臣がこちらへお越しになりました。まず、大后のお部屋へお見舞いにいらっしゃったのを、俄にわ
か雨の音にまぎれて尚侍の君はお気付きになれませんでした。右大臣は無造作にすっと尚侍の君のお部屋へお入りになって、御簾をお引き上げになるなり、
「いかがでしたか、なにしろすさまじい昨夜の天気に、どうしていらっしゃるかとお案じはしていたのですが、お見舞いにも伺えなかった。中将の君や宮の亮などは、お側にいましたか」
などとおっしゃる様子が、早口で落ち着きがないのを、源氏の君は、こんな密会のあわただしいさ中にも、左大臣の態度とふと比較なさって、ひどいちがいだと、思わず苦笑いなさいます。ほんとうに、お部屋にすっかりお入りになってから、おっしゃればおよろしいのに。
尚侍の君はほとほとお困りなさって、御帳台からそっとにじり出ていらっしゃいました。
そのお顔がたいそう赫あか
くなっていらっしゃるのを、まだ御気分がお悪いのかと、右大臣は御覧になって、
「どうしてお顔色がいつものようでなく、そんなに赫いのでしょう。物もの
の怪け などが憑つ
いていると厄介だから、修法ずほう
を続けさせるべきでしたね」
とおっしゃりながら、ふと、目をやると薄二藍うすふたあいの男帯が、尚侍の君のお召物の裾にまつわって、御帳台から引き出されているではありませんか。これはあやしいとお思いになった上に、畳紙たとうがみ
に何か手習いを書きつけたものが、御几帳みきちょう
の下に落ちているのを見つけました。これは一体どうしたわけかと、お心も動顛どうてん
なさって、
「それは誰のものです。見慣れないあやしい物ですね。こちらへお渡しなさい。それを見て、誰の物か調べてやろう」
とおっしゃるので、尚侍の君も、はっと振り返って、御自分も畳紙を見つけられました。もう、どうとりつくろいようもないことなので、何とお答えが出来ましょう。度を失って茫然としていらっしゃるのを、わが子ながら、さぞ恥ずかしくて身の置き所もないようにお思いだろうと、お察しして御遠慮なさるのが、右大臣ほどのお立場の人なら、当然のことでしょう。ところが、日頃たいそう短気で寛大なところがおありでない大臣なので、前後の分別も失われて、畳紙をわしづかみにされるなり、御帳台の中をいきなりお覗きになりました。
中には何とも言えず色っぽい様子で、臆面もなく横になっている男がいます。今になって、男はそっと顔をおし隠して、何とか身を隠そうととりつくろっています。右大臣はあまりのことに呆れ果てて、腹も立つし、いまいましくてやりきれないものの、面と向かっては、どうしてそれが源氏の君だとあばきたてられましょう。目の前も真っ暗になる気持がして、この畳紙を手に掴つか
んだまま、寝殿にお引き上げになりました。
尚侍かん
の君は、正気も失くされたような気持で、死ぬほどの思いでいらっしゃいます。源氏の君も、そんな尚侍の君が可哀そうでならず、とうとう軽率な振舞いが重なって、世間の非難を浴びることになったかとお思いになりながら、女君のいたしたしそうな御様子を、しきりに何かと慰めておあげになります。 |