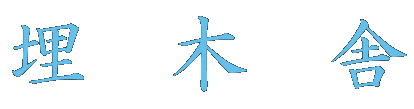右大臣は直情径行で、何事も胸に収めておけない御性分の上に、老いのひがみさえこの頃はとみに加わっておいでになるので、何をためらわれることがありましょう。何もかもずけずけと、大后にすっかりお訴えになってしまいました。
「これこれしかじかの事がありました。この畳紙の手跡
は源氏の君のものです。昔もあの二人は親の許しもなく、勝手に出来てしまったことですけど、あの方の人物に免じて、すべての罪を許して、それでは婿としてお世話しようと、こちらが申しました折には意にも介さず、全く無視しきった心外な態度をとられたのです、けしからぬことだと思いましたが、これも前世の宿縁なのだとあきらめて、まさか帝は操みさお
の穢けが れた女だなどとお見捨て遊ばすこともあるまいと、その御愛情にすがって、このようにして、はじめの望み通り、帝に奉ったのでした。何と言ってもやはりあの落ち度の遠慮がありまして、れきっとした女御などとも名乗らせるわけにも参らず、それだけでもいつも口惜しく残念に思っておりましたのに、またもや、このようなことさえ起こってきたのです。改めて、つくづく情けない気持になってしまいました。男たちにはありがちなこととは言え、源氏の大将は、まったく何という怪け
しからぬ御料簡なのでしょう。朝顔の斎院にもまだ相変らず大それたことを言い寄っては、こっそり御文通などつづけて、怪しげな御様子だなどと、世間では噂しています。こういうことは御治世の爲ばかりでなく、源氏の君御自身にとってもよくないことですから、よもや、そんな無分別なことはなさらないだろうと思い、また当代の識者として、天下を従えなびかしていらっしゃる御様子は格別のようですから、わたしは源氏の君の心を、これまで疑ったこともなかったのです」
などとおっしゃいますと、大后は、右大臣よりもずっと激しい気性で、源氏の君をひどくお憎しみなので、大そう御不興の面持ちで、
「帝と申し上げても、昔から誰も皆帝を軽んじ申し上げて、あの到仕ちじ
の左大臣も、この上なく大切に育てていた一人娘を、兄耳の東宮にはさしあげないで、弟の源氏の君がまだ幼くて元服した時、添臥そいぶ
しとしてとっておいたり、またこの姫も、後宮こうきゅう
にさしあげようと心づもりいていましたのに、源氏の君のため、みっともない恥さらしな有り様にされたのです。それなのにあの当時は、唯一人として、それを不都合なことと思ったでしょうか。誰もがみな源氏の君ばかりをひいきになさるようだったので、こちらも源氏の君を婿にとというあても外れたものだから、こうして尚侍ないしのかみ
として宮仕えもしていらっしゃるわけです。それが可哀そうなので、なんとかして尚侍かん
の君としてでも、人にひけ目を感じないようにお世話してあげよう、あんないまいましい源氏の君の手前もあるし、などと思っていましたが、その御当人の尚侍の君ときたら、こっそり自分の好きな人に靡なび
いているというわけなのですからね。斎院とのことだって、おそらく噂通りなのでしょうよ。何事につけても、源氏の君が帝の御ために安心できないように見えるのは、あの方は東宮の御代に、それはそれは期待をかけている人ですから、当然のことでしょう」
と、ずけずけ容赦なく仰せ続けられるのを、右大臣はさすがに聞き苦しく思い、どうして大后に、あの密会の一件をすっかり申し上げてしまったのかと後悔なさりながら、
「まあしかし、しばらくこのことは他に洩らさないようにしましょう。帝にも奏上なさらないで下さい。尚侍の君はこのような罪がありましても、帝がお見捨て遊ばすことがあるまいと頼みにして、甘えていい気になっているのでしょう。大后から内々に御意見をなされましても、聞き入れないようでございましたなら、その罪はただわたしが一身に負いましょう」
などと、おとりなし申し上げますけれど、大后の御機嫌はさっぱりよくなられません。こんなふうに御自分が一つ邸に居て隙もない筈なのに、源氏の君は遠慮もしないで、大胆に忍び込んで来られるというのは、わざと、こちらを軽んじ愚弄なさっているのだと、お考えになりますと、ますます御立腹がひどくなり、この機会こそ、源氏の君を失脚させるような計りごとを企てるには、ちょうど都合がいいと、大后はあれこれ御思案をめぐらされるようでした。 |