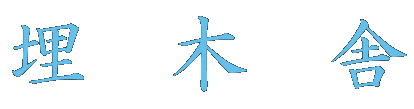源氏の君はまず帝の御前に参上なさいますと、帝はちょうど御政務もなく、ゆっくりしていたっしゃる折でしたので、昔の思い出や最近の出来事など、いろいろお話し申し上げます。帝はお顔も故院にたいそうよく似ていらっしゃって、もう少し優美なところがおありで、おやさしく柔和でいらっしゃいます。お二人はお互いになつかしく思われて、しみじみお顔を御覧になります。
帝は朧月夜の尚侍
の君と源氏の君の忍ぶ恋も、まだつづいているとお耳にされ、尚侍の君の様子にそれらしいそぶりを御覧になる時もあるのですけれど、どうせ、今始まったことならばともかく、前々から続いていることなのだから、そういうふうに愛しあっても、不似合いでみない間柄だと強い
いて大目にお考えになって、お咎とが
めもなさらないのでした。
さまざまなお話をなさり、学問の上での疑問に思っていらっしゃることなどを、帝は源氏の君に御質問遊ばしたり、また艶つや
っぽい恋の歌にからんだ体験談など、お互いに打ち明け話をなさるついでに、あの斎宮は伊勢へお下りになられた日のことや、斎宮の御器量がたいそう美しくいらっしゃったことなどを、帝がお話しなさいますので、源氏の君も打ち解けて、野の宮での、情趣深かった六条の御息所との別れの曙のことまで。すっかり告白なさっておしまいになりました。
二十日の月がようやく上って来て、風情の美しい時刻なので、帝は、
「管絃の遊びなどを催したいような景色ですね」
と仰せになりますと、源氏の君は、
「藤壺の中宮が今夜御退出なさるようですから、そちらにお伺いしようと存じます。故院が御遺言なさいましたことがございますし、また、私の外には御後見申し上げる方もございませんようですので、東宮の御縁からも、中宮がおいたわしく存ぜられまして」
と、奏上なさいます。帝は、
「東宮をわたしの猶子ゆうし
にするようにと、故院が御遺言なさいましたので、とりわけ気をつけて大切にしてはいるのですが、殊さら特別なお扱いをするのもどうかと思われて。東宮はお年の割にはお筆跡なども殊の外するれていらっしゃるようですね。何をしてもふつつかなわたしの面目を立ててくださいます」
と仰せになりますので、源氏の君は、
「およそ、東宮は何事につけても、たいそう御聡明で大人びたところもおありですが、やはりまだ何と申しても、ほんとうに幼くていらっしゃいますから」
などと、日頃の東宮の御有り様などを奏上なさって御退出になりました。
弘徽殿の大后の兄君の藤とう
の大納言だいなごん の子息に頭とう
の弁べん という、時勢の乗って得意気に威張っている若者が居ました。何の屈託もないのでしょう。
妹君の麗景殿れいけいでん
の御方おんかた へ行こうとして、源氏の君の前駆の者がひそやかに先払いを遭いましたので、しばらく立ち止まりながら、
<白虹はくこう
貫つらぬ けり。太子畏お
ぢたり>
と、たいそうゆっくりと謀反の意味の文句を口ずさみました。源氏の君は、全く目をそむけたい思い出それをお聞きなりましたが、と言って真っ向から咎めだてすることも出来ません。大后の御機嫌はこのところ全く険悪至極で、物騒な雲行きばかりが耳に入ってくる上に、こうした大后の近親の人々までが、露骨な態度で当てこすりをわざと言うようなことも何かとあるのを、源氏の君は実にわずらわしくお思いになります。けれどもつとめてそ知らぬふうを装っていらっしゃるのでした。
藤壺の中宮のところにいらっしゃった源氏の君は
「帝の御前にまいりまして、今まで夜を更かしてしまいました」
と、御挨拶を申し上げました。
月光が鮮やかに照り輝いているのを御覧になって、中宮は昔はこんな美しい月夜には故院が管絃の御遊びを催されて、はなやかにお過ごしになられたことなどを、お思い出しになられます。あの頃と同じ宮中なのに、今は昔に変わることばかりが多くて、悲しさをそそられるのでした。
|
九重ここのへ
に 霧や隔つる 雲の上の 月をはるかに 思ひやるかな
(九重の宮中には 幾重にも霧がかかり わたしを隔てているのか 雲の上の月をはるかに
おしのびしているのに) |
|
| と、王命婦からお伝えになります。御座所が近くで、中宮の御様子もほのかながらもなつかしく伝わって来ますので、源氏の君は辛さも忘れて、思わず、感激の涙を流します。 |
月影は
見し世の秋に 変はらぬを へだつ霧の 辛くもあるかな
(月の光は昔の秋と 全く変わらないのに 月を隔てて見せない 今夜の霧こそ
何と辛いことか) |
|
「<霞も人の心なりけり> という古歌もありましたが、昔もこういうことがございましたのでしょうか」
などと、申し上げます。
東宮は普段はとても早くお寝やす
みになられますのに、今夜は中宮がお帰るになるまでは、起きていようとお思いになるのでしょう。中宮のお帰りの時は恨めしくお思いになりながらも、さすがに、お後を追うようなことはなさいませんのを、中宮はほんようにいじらしくお思いになるのでした。 |