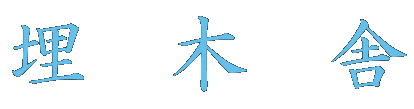あたりを見回して御覧になりますと、几帳の後ろ、襖の向こうなどの開け放され見通しになったあたりに、女房たちが三十人ばかり身を寄せ合うようにしています。濃いのや薄いのやさまざまな鈍色
の衣裳を着て、皆たいそう心細そうに、涙に沈みながらしおれきって集まっています。それを御覧になると、源氏の君は、ほんとうに可哀そうにと同情なさいます。左大臣は、
「お見捨てなさるはずのない若君も、ここに残っていらっしゃるのですから、いくら何でも、おついでの時はお立ち寄り下さらないなずはばいなぢ、自分で慰めているのですが、ただもう分別もない女房などはこの邸を、今日限りお見捨てになってしまう古里ののように、悲観してしまっております。故人との永なが
の別れの悲しみよりも、ただ折にふれて親しくお仕えいたして「まいりました歳月が、これですっかり跡かたもなく消え去るであろうと、女房たちが嘆き悲しんでいるのも、もっともなことでございます。ついにこれまでも、ごゆっくりとうち解けて、この邸においで下さることはございませんでしたが、それでのいつかはと、あてにならないことを頼みにしておりましたのに、ごんとうに、心細い夕べになりました」
と、おっしゃるにつけても、またお泣きになるのでした。源氏の君は、
「それはどなたもあまりにも浅はかな御心配です。まず、さしあたって葵の上がどんなに冷たくても、そのうちおつかはわかっていただけるだろうと、のんきのかまえておりました間は、自然、御無沙汰がちのこともございました。しかし、今となっては、かえって何を理由にして御無沙汰することが出来ましょう。そのうち、きっとわたしの気持もおわかりいただけましょう」
と、おっしゃって、お出かけになりますのを、左大臣はお見送りなさってから、源氏の君のお部屋にお戻りになりました。お部屋の御調度や装飾をはじめとして、何一つ昔に変わることはないのですけれど、住む人のいなくなった部屋は空蝉うつせみ
のようにうつろな、淋しい感じがいたします。
御帳台みちょうだい
の前に、お硯すずり などが散らかったまま置かれいます。源氏の君のお手習いの捨て反古ほご
を左大臣は拾い上げて、涙をおししぼりながら御覧になりますのを、若い女房たちは、悲しみながらもほほ笑んで見ているのでした。そこには心を打つ古人の詩歌などを、唐のものやら大和のものなど書き散らしては、草仮名そうがな
も漢字も、いろいろめずらしい書体で書きまぜてあるのでした。
「何というみごとな御筆跡だ」
と、左大臣は空を仰いで嘆息なさりながら、御覧になるのでした。これほどのお方と、これからは他人づきあいをしてゆかねばならないのが惜しまれてならないのでしょう。
「旧ふる
き枕、故ふる き衾ふすま
、誰と共にか」 とある漢詩の傍そば
に、 |