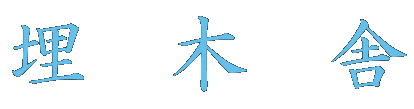亡き葵の上の七日毎の御法要などはすみましたけれど、四十九日の忌明きあ
けまではまだ引きつづき、源氏の君は左大臣家にお籠りになっていらっしゃいます。馴れないお独り暮らしをお気の毒に思って、三位になられた頭とう
の中将ちゅうじょう は、いつもお訪ねになります。世間話などに、真面目な話や、また例のような色好みな話などもお耳に入れながらお慰め申し上げます。中でもあの源げん
の典侍ないしのすけ のことが、何かといえば今も笑い話の種になるようでした。源氏の君は、
「やれお可哀そうに、お祖母上おばうえ
様のことを、あんまり軽蔑なさるな」
と、おたしなめになるものの、いつも面白がっておいでになるのでした。あの常陸ひたち
の宮みや での、十六夜のおぼろな月影にぼんやりとしか見えなかった秋の夜のことや、そのほかにもさまざまな色恋沙汰を、お互いに残らずすっぱ抜いてしまわれる。あげくの果ては、無常な浮き世のあわれにはかないことなどを語りついで、お泣きになったりもするのでした。
時雨しぐれ
が降り、もの淋しい夕暮れに、頭の中将は、鈍色にびいろ
の喪服の直衣のうし や指貫さしぬき
を、少し色薄めのに衣がえして、見るからに男らしくすっきりと、御立派なお姿で源氏の君のお部屋にお越しになりました。
源氏の君は、西の妻戸の前の高欄に寄りかかって、霜枯れの前庭を眺めていらっしゃる時でした。
風は荒らしく吹き、時雨がさっと降りそそいだ時、涙も時雨と競ってこぼれ落ちるかと思われて、
<雨となり雲とやなりにけむ、今は知らず>
と、葵の上のことを漢詩に託して、ひとりごとをつぶやきまがら、頬杖をついていらっしゃいます。その御様子に、
「もしも自分が女だったら、この方に先立って死ぬと、魂がきっとお側に留まってしまうだろう」
と、頭の中将は色めかしいお気持になり、つい、じっとお顔を見つめながら、お側近くにすわられました。源氏の君は、しどけなくおくつろぎになったお姿のまま。直衣の紐ひも
だけをお直しになります。
中将よりは少し色の濃い鈍色の夏の御直衣に、紅/rb>くれない
のつややかな下襲したがさね を重ねて、地味な喪服姿にしていらっしゃるのが、かえって見飽かない気がします。
頭の中将も、いかにもしみじみとした目つきで、空のけしきを眺めていらっしゃいます。
|
雨となり
時雨しぐ るる空の 浮き雲を いづれの方と
わきてながめむ
(雨となり雲となる 時雨の空に漂う浮き雲は どれが亡き人を 焼いた煙と 見分けられようか) |
|
「行方も知れずに」
と、頭の中将がひとりごとのようにつぶやかれますと、 |
見し人の
雨となりにし 雲居くもゐ さへ いとど時雨に
かきくらすころ
(亡きわが妻が雲となり 雨となった空までも 時雨が降りこめいよいよ暗く わたしの心のように 悲しみにかきくれて) |
|
と、おっしゃる源氏の君の御様子にも、亡きお方を偲ばれるお心の深さがよくわかりますので、頭の中将は、
「はて妙なこともあるものだ。長年の間、源氏の君は葵の上をさほど愛していらっしゃるようには見えなかった。桐壺院はそれを見かねて御忠告遊ばされ、父大臣のねんごろなお扱いも源氏の君はお気の毒に重い、また大宮のお血筋からいっても、切っても切れない深い血縁でいらっしゃるなど、あれこれ抜き差しならぬ関係が絡んでいるので、葵の上を捨てることもお出来にならず、お気の重そうな御様子ながら、いやいや添いつづけていらっしゃるのだろうかと、お気の毒に感じた折節もあった。ところがほんとうのところ、大切な正妻としては、葵の上を格別に重んじていらっしゃったのか」
と、今になってうなずけます。それにつけても、頭の中将は、ますます葵の上の死が残念に思われるのでした。何事につけても、光が消え失せた気持がして、すっかり気がめいっていらっしゃるのでした。 |