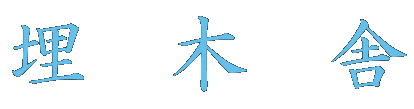左大臣のお邸にお戻りになってからも、源氏の君は少しもお眠りになりません。これまでの葵の上の在りし日の御様子を、しみじみ思い出されながら、
「いつか最後には自然におわかりになって、自分を見直して下さるだろうなど、のんびち構えて、どうしてつまらない浮気沙汰にかかわり、ひどく恨まれるようなことをしたのだろう。生涯、あの方は自分のことを薄情で冷淡な者と思い通して亡くなってしまわれたのだ」
などと、取り返すすべもない後悔を、次々思い出しつづけられます。今更何の甲斐もありません。
御自分が鈍色
の喪服をお召しになっていらっしゃるのも、夢のようなお気持がなさり、自分がもし先立っていたら、亡きお方は、もっと濃い鈍色にお染めになることだろうと、お思いになるにつけ、 |
限りあれば
薄墨衣うすずみころも 浅さけれど 涙ぞ袖を
ふちとなしける
(妻の死に決まりの喪服の 薄墨色を着ているが 悲しみの涙で袖が染まり 深い淵の藤衣に 変えてしまったことよ) |
|
と、詠じて、念誦ねんず
をなさるお姿は、ひとしおあでやかさがまさり、お経をしめやかにお誦よ
みになりながら、 「法界三昧普賢大士ほうかいざんまいふげんたいし」
とお唱えになる御様子は、勤行ごんぎょう
に馴れた法師よりも、すぐれていらっしゃいます。
若君を御覧になりましても、<何にしのぶの草を摘ままし> の古歌のように、この子がなかったら、何によって亡き人を偲ぶよすがにしようかとお思いになり、ほとしお涙にくれられ、それにつけてもこの形見かたみ
が残されたことをせめてもの慰めに思われるのでした。
母宮は悲しみのあまり、そのまま寝込んでおしまいになり、お命さえ危ないようにお見受けしますので、左大臣家ではまたご心配なさって騒動になり、御祈祷などをおさせになります。
|
| |
| 月日がはかなく過ぎて行くうちに、七日ごとの御法要のお支度などおさせになるにつけても、思いもかけなかったことですから、その都度、いつまでも悲しみが新たに湧き上がって来るのでした。平凡でふつつかな子でさえ、失った親の思いはどんなにかせつないものでしょう。まして、この葵の上の場合は、すぐれたお方だっただけにお嘆きになるのはごもっともなことです。その上、ほかに姫君がいらっしゃらないのさえ、淋しく物足りないのに、今は袖の上に大切にしていた珠たま
が砕けたよりも、もっと心の底から、落胆なさったようにお見受け申します。 |
| |
源氏の君は、二条の院にさえ、ほんのしばらくもお帰りにならず、しみじみと心から葵の上を偲ばれお嘆きになって、仏前のお勤めをまめまめしくなさりながら、明かし暮していらっしゃいます。
お通い所の方々には、お手紙だけをさしあげています。
あの六条の御息所は、斎宮が初斎院となった宮中の左衛門さえもん
の司つかさ にお入りになったので、ひとしお厳しい御潔斎ごけっさい
にかこつけて、ふっつり御文通もなさいません。
源氏の君はつくづく疎ましいと思い知っていたはずの男女の仲も、今はすべて厭わしくおなりで、こういう絆ほだし
になる幼い若君が生まれていなかったら、かねて願っていたように、世を捨てて出家でもしていただろうにと、お思いになります。それにつけても、まず二条の院の西の対たい
の姫君が、淋しそうに暮していらっしゃるだろうお姿が、ふっと浮かんで来て思いやられるのでした。
夜は御帳台みちょうだい
の中にお一人でお寝やす みになられますので、宿直とのい
の女房たちは御帳台の近くを取り囲んで控えておりますものの、何となく御身廻りが淋しくて、ただでさえもの淋しい秋に亡くなるとはと、亡き人が恋しく、寝ざめがちになられます。声の美しい僧ばかりを選り抜いてお側に置かれ、念仏をあげさせる暁方などは、とりわけ悲しみが堪え難く、断腸の思いがなさるのでした。
|