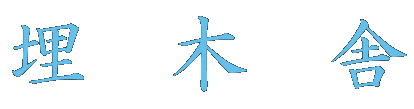晩秋の淋しさのいよいよ深まっていく風の音が、身にしみて、馴れないお独り寝に、源氏の君が夜長を明かしあぐねていらっしゃるその朝ぼらけのことです。霧が一面にたちこめているところへ、開きそめた菊の枝に、濃い青鈍色の紙にしたためた手紙をつけて、誰からとも言わず置いて行った者がありました。折にふさわしい気の利いたことをする者よとお思いになって、御覧になると、それは六条の御息所の御筆跡なのでした。
「お悲しみの折と御遠慮して、お便りをさしあげなかったこの日頃の、わたくしの気持はお察し下さいますでしょうか」 |
人の世を
あはれときくも 露けきに 後おく
るる袖を 思ひこそやれ
(人の世の無常を 人の死に感じて 涙がちにつけ 残されたあなたの お袖の涙がしのばれて) |
|
「ただ今の空の色を見ましても、思いあまりまして」」
とあります。いつもよりも更に優雅にお書きになっているものよと、源氏の君はさすがにそのお手紙を捨てがたくて、しみじみ御覧になるのですが、一方では、よくもしらじらしく弔問なさるものだと、お心が暗くなります。とはいっても、ふっつりとお便りをさしあげなくなってしまうのもおいたわしくて、御息所の御名を汚すことにもなるだろうかと思い迷われるのでした。
亡くなった方は、どうしたところでどっちみちああなる運命でいらっしゃったのだろうに、どうして自分はあんな生霊のありさまを、ああまでまざまざと見てしまったのかと、口惜しくてならないのは、やはり御自分のお心のせいとはうえ、御息所へのお気持を、もとに戻せないからなのでしょうか。
斎宮の御潔斎の間は、いろいろ面倒だろうかなどと、源氏の君は長い間、ためらっていらっしゃいましたが、わざわざ下さったお手紙のお返事をさしあげないのは、つれなさすぎはしないかと、鈍色にびいろ
がかった紫の紙に、
「すっかり御無音ごぶいん
にうちすぎましたが、いつもあなたのことを忘れず思いつづけておりました。しかし何分にも喪中のことで、御遠慮しておりますわたしの気持は、よくお察しくださるだろうと存じまして」 |
とまる身も
消えしもおなじ 露の世に 心置くがむ ほどぞはかなき
(生き残った者も 死んでしまった者も 同じはかない露の世に 執着しているのこそ
むなしいかぎり) |
|
「つきましては、お恨みがございましても、どうかつとめてそれをお捨てになって下さい。喪中からの手紙は、御自身で御覧下さらないかとも存じまして、書くのはこれだけにして、ほかはひかえます」
と、お書きになりました。
御息所はたまたま六条のお邸にいらっしゃった時でしたので、人目を避けてお読みになって、源氏の君が、それとなく仄ほの
めかしていらっしゃるお気持を、自分でも常にひそかに心の鬼に責められていたやましさがあるだけに、やはりそうだったのかと、はっきりと受け取られるのも、たまらない辛さなのでした。
「自分は何という罪障の深い、情けない身の上なのだろう。それにしてもこういう噂がひろまっては、桐壺院のお耳にまで入ったら、どのように思し召すだろう。亡き前さき
の東宮とは、御同腹の御兄弟というばかりでなく、とても睦まじくおつきあおなさって、この斎宮の姫君のことも、前の東宮は父親として、ねんごろにお頼み申し上げておかれたので、
『前の東宮のお身代わりになって、姫君を同じように大切にお世話してあげよう』 などと、いつも仰せになって、わたしにも、前の東宮の御在世の時のように、そのまま宮中で暮らすようにと、度々おすすめ下さった。それさえ、全くあるまじきこととして、頭から考えてもみなかった。それなのに、思いもかけず、こうした年甲斐もない恋の苦労に憂き身をやつし、果ては情けない浮き名まで流してしまうとは」
と、御息所はさまざまに思い乱れお嘆きになるので、相変らず御気分の悪さは一向にお直りになりません。
そうは言うものの、御息所はこのことのほかには一体に奥ゆかしく、風雅な御趣味だとの定評がおありで、昔から名高いお方でいらっしゃいました。宮中から野の宮へお移りになります時にも、趣深く目新しい趣向をいろいろお凝らしになりますので、殿上人の中でも風流好みの人たちなどは、朝夕に嵯峨野さがの
の露を踏み分けて、野々宮へ通うことを、その頃の日課にしている、などの噂をお聞きになるにつけても、源氏の君は、
「それもしのはずだ、優雅なおたしなみはあくまで深く身につけていらっしゃるお方だもの、もしあの方が世の中に飽き果てて、伊勢にお下りになってしまわれたら、やはりどんなに淋しいことだろう」
と、さすがに心細くお思いになるのでした。 |