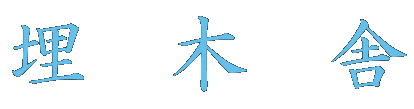頭の中将は、源氏の君がひどく真面目ぶったふりをなさり、いつも人のことばかりとがめ立てなさるのがいまいましくて、何食わぬ顔をなさりながら、実はこっそり忍び通っていらっしゃる所が少なくないらしいのを、何とかしてあばいてやりたいと、かねがね思っていたところへ、この現場を見つけましたので、何とも嬉しくてたまりません。こういう機会に少し脅してあわてさせ、懲
りましたかと言ってやろうと思い、わざとしばらくそっとして油断をさせていました。
そのうち風がひんやりと吹いてきて、夜が次第に更けゆく頃、二人とも少しとろとろまどろんでいる様子なので、頭の中将はそうっと入ってきました。
源氏の君はとても気を許してお眠りになるような御気分ではありませんでしたので、すぐに気配を聞きつけました。まさか頭の中将とは思いも寄らず、いまだに典侍を思い切れないでいる修理すり
の大夫かみ に違いないとお思いになります。修理の大夫のような年寄りに、こんな不似合いな行為を見つけられることは面目ないので、
「やれやれ厄介な。さあ、帰るよ。あの人が来ることは
<蜘蛛くも のふるまひ>
でも分かっていただろうに、騙だま
すとはあんまりだ」
と、おっしゃって、脱いであった直衣のうし
だけを取って、屏風びょうぶ のうしろへお入りになりました。頭の中将はおかしさをこらえて、源氏の君が引きめぐらされた屏風の側へ寄って行き、ばたばたと屏風を畳んでしまい、わざと大げさに騒ぎ立てました。
典侍は年は取っていても、ひどく気取った色っぽい女で、これまでもこうしたことでたびたび肝を冷やした経験がありましたので、物馴れていて、内心動転していても、男が源氏の君をどんな目にお合わせするつもりなのかと、心細さにぶるぶる震えながら、頭の中将をしっかり掴つか
まえていました。
源氏の君は、自分と知られないうちに出てしまいたいとお思いになりますが、しどけない姿で冠などを歪ゆが
めてかぶったまま走る後ろ姿を想像すると、何とも醜態だろうと思いためらってしまわらます。頭の中将も何とかして自分だと知られまいとして、無言のまま、ただ非常に激怒しているふりをよそおい、太刀たち
を引き抜きます。典侍は、
「あなた、あなた」
と言いながら、頭の中将に向かって手をすり合わせて拝むので、頭の中将はあやうく吹き出しそうになります。婀娜あだ
っぽく若づくりに装ってうわべだけは、まあ何とか見られますが、五十七、八にもなった老女が、恥も外聞も忘れておろおろあわてふためいている様子、しかも格別美しい二十の若者たちの中にはさまって、恐ろしがっているのは、何ともみっともなくおさまりがつきません。
頭の中将はわざとこんなふうに、まるで別人のように見せかけていますけれど、かえって源氏の君は目ざとく、頭の中将だとさとってしまわれました。自分だと知っていて、頭の中将がわざわざこんなことをするのだろうと馬鹿らしくなりました。
頭の中将に違いないと分かってしまうと、ひどくおかしくなって、太刀を引き抜いた頭の中将の腕を掴まえて、きゅっとおもいきりつねってやりますと、頭の中将は癪しゃく
だと思いながらも、こらえきれずに吹き出してしまいました。
「ほんとにこれは正気の沙汰ですかね。冗談にもほどがある。さあ直衣のうし
を着よう」
とおっしゃるのですけれど、頭の中将はその源氏の君の直衣をしっかり掴んで、一向に放しません。
「それなら、そちらも御同様さ」
と、源氏の君は頭の中将の帯を引き解ほど
いて直衣を脱がせてしなまおうとなさいます。頭の中将は脱ぐまいとしてさからってあちこち引っ張り合ううちに、直衣の袖下の縫い合わせてないところがびりびりちぎれてしまいました。頭の中将は、 |
つつむめる
名やもり出でむ 引きかはし かくほころぶる 中の衣に
(包みかくしている浮き名が 洩れてしまうかもしれない 引っ張り合って
こんなにほころびた ふたりの中の衣から) |
|
「この破れたのを上に着たら、さぞ目立ちあなたの浮気は知れることでしょう」
と言います。源氏の君は、 |
隠れなき
ものと知る知る 夏衣 着たるを薄き 心とぞ見る
(薄い夏衣では自分だって 隠しようもないと知りながら その夏衣を着て 嚇おど
しに来るとは何と 浅い料簡の人だろう) |
|
| と歌を詠み交わしてどちらも恨みなしの、だらしない姿にされて、連れ立ってお帰りになりました。 |