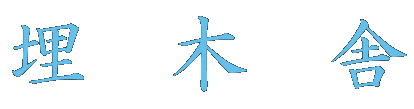「厄介なことになりそうで」
と、お立ちになるお袖をとらえて、
「まだこんなつらい物思いをしたことはございません。今更になってあなた様に捨てられてはいい恥さらしでございます」
と言って泣く様子がとても大げさなのでした。源氏の君は、
「そのうち便りをしますよ。いつもあなたを思っているのだけれど」
と、袖を振り払って出ようとなさいますのを、典侍は懸命にとりすがって、
「橋柱
」
と怨めしそうに言い浴びせますのは、<津の国の長柄ながら
の橋柱古ふ りぬる身こそ悲しかりけれ>
の、橋柱の五文字なのでしょう。
帝はお召替えをしませてお障子の隙間からすべてを覗いておしまいになりました。不釣り合いな間柄だとたいそう滑稽にお感じになられて、
「女には目も向けないと、女房たちが皆心配していてようだが、やっぱりそなたのことは見過ごさなかったのだな」
とお笑いになりますと、典侍はなんとなくきまりが悪いとは思いながらも、恋しい人とのことなら、濡ぬ
れ衣ぎぬ だって着たがるという類なのでしょうか、それほど弁解も申し上げません。
女房たちも、意外なこともあるものだと、取り沙汰するのを、頭の中将が聞きつけて、女のことにかけては抜け目なく関心を持つ性分なので、まだあの女のことは考えも及ばなかったなと思うにつけ、幾つになっても色好みの止まぬ典侍の心を試したくなりまして、とうとう情人の仲になってしまいました。
頭の中将も人よりはるかに優れていらっしゃいますので、典侍はあの情つれ
ない源氏の君の代わりの気晴らしにと思いましたが、ほんとうに逢いたいのは、やはり源氏の君お一人だったとか。何とまあ年甲斐もなく贅沢な好みですこと。 |