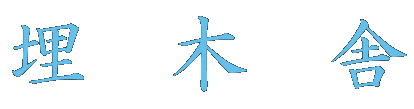源氏の君は、それにしても何という呆れた歌の詠みぶりだ。この歌こそ、姫君御自身が作られた精いっぱいのところなのだろう。いつもはきっと侍従がお直ししているのだろう。その侍従は今、斎院に行って留守なのだ。ほかに添削して教えてさしあげるお抱えの博士
などもいないのだろう。これではとやかく言っても甲斐がないとお思いになります。姫君が必死になって歌をお詠みになっていらっしゃる御様子を想像なさると、お気の毒やらおかしいやらで、
「まことに勿体もったい
ないものとは、こんな歌をいうのだろうね」
と苦笑いなさって、御覧になっていらっしゃるのを、命婦はおかしさに顔を赤らめてみています。
今はやりの薄紅色のとても見られないほど艶もなくなった古めかしい単衣と、表と裏が同じほど濃い紅色の直衣が、衣筥ころもばこ
の中にいかにもありふれた感じで、褄々つまづま
を見せておさまっています。
源氏の君は、やれやれとお思いになりながら、お手紙をひろげたまま、筆をとられて、端の方に興にまかせて何かお書きになります。命婦は横から覗きますと、 |
なつかしき
色ともなしに 何にこの 末摘花すえつむはなを
袖に触れけむ
(それほど心惹かれる 人でもなかったのに なぜ末摘花のように 鼻の赤いあの人に 触れてしまったのか) |
|
など、書きよごしていらっしゃるのでした。
命婦は、源氏の君が紅花べにばな
の別の名の末摘花のことをけなされたのを、何かわけがあるのだろうと考えるうち、これまで折々の月光に、ちらちらと、おみかけした姫君のお顔を思い合わせて、お気の毒とは思うものの、おかしくなってくるのでした。 |
紅くれなゐ
の ひと花衣ごろも うすくとも ひたすら朽くた
す 名をし立てずは
(紅色の一度染めたように あなたの愛が薄くても 姫君をひたすらけなされて 悪い噂だけは おたてにならないで) |
|
と、いかにももの馴れたふうに、命婦がひとりごとに口ずさむのを源氏の君は、それほど上手な歌というのではないが、せめて姫君にもこれくいらいに一通りの歌が詠めたらと、かえすがえす残念におおもいになるのでした。それにしても姫君の御身分が御身分だけに、お名を汚けが
すような噂が立つのは、いかないもお可哀そうにお思いになります。他の女房たちがそkへ参りますので、
「これは隠してしまおうよ。こんな贈り物は常識のある人のすることだろうか」
と、太い溜息をついていらっしゃいます。命婦はどうしてお目にかけてしまったのだろう、自分までが気が利かないようではないかと、たいそう恥ずかしくなって、こっそり退出してしまいました。 |