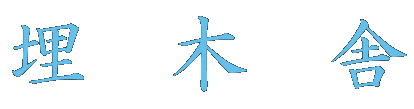ようよう夜が開けたようなので、源氏の君は御自身で格子をお上げになり、前庭の植え込みの雪を御覧になりました。人の踏んだ跡もない雪は、はるばると見渡し限り白く荒涼としていて、たそう寂しそうに見えます。こんな朝、振り捨ててお帰りになるのも姫君gお可愛そうに思われたので、
「あの美しい空の色を御覧なさい。どうしていつまでもかたくなに打ち解けて下さらないのでしょうね」
とお恨みになります。
まだ外はほの暗いのですが、雪明りに映えて、源氏の君がひときわp綺麗に若々しくお見えになるのを、老女たちは笑みこぼれて、仰ぎ見るのでした。
「はやくお出ましなさいませ。そんなふうではあまりに無愛想に見えてよくありません。女の方は素直なのが何よりでございますよ」
などと女房がお教え申し上げますと、姫君が格別に内気でいらっしゃっても、さすがに鷹揚で、人の申し上げることには逆らわない御性質なので、何かと身づくろいなさって、にじる出ていらっしゃいました。
源氏の君は、姫君を見ぬふりをしながら、外の方を眺めていらっしゃいますが、横目でしきりに御覧になります。さて、どうだろうか、こうして打ちとけた時に見て少しでもよく見えるようだったらどんなに嬉しいだろうとお考えになるのも、身勝手なお心というものです。
何よりも先ず、座高がいやに高くて、胴長なのが目に映りましたので、やはろ思った通りだと、お胸もつぶれるお気持でした。その次に、ああ、みっともないと思われたのは、お鼻でした。ふとそこに目がとまってしまいます。普賢菩薩
のお乗り物の像の鼻のようです。あきれるばかり高く長くのびている上に、先の方が少し垂れ下がって、赤く色づいているのが、ことのほかいやな感じでした。
顔色は雪も恥ずかしいほど白く青味を帯びています。額つきはむやみにおでこが広く、それでもまだ顔の下の方が長く見えるのは、たぶん恐ろしく長いお顔立ちなのでしょう。痩せていらっしゃることといったら、お気の毒なほど骨ばっていて、肩のあたりなどは、痛そうなほどごつごつしているのが、お召物の上からでもありありと見えます。
源氏の君は、どうして何もかもすっかり見てしまったのだろうと思いながら、姫君があまりにも珍しいご器量なので、やはりついお目がそちらへ寄せつけられてしまうのでした。
頭の恰好や、髪の顔に垂れかかった様子だけは、申し分なく美しいとお思いになっていらっしゃる女君たちにもおさおさ劣らないくらいに見えます。袿うちき
の裾に長い黒髪がたまって、なお床にあふれている部分は、一尺に余るだろうと思われます。
お召物のことまで言いたてるのは口さがないようですが、昔物語にも、まず人物の着ている衣裳について語っているようです。それにならって言えば、姫君は薄紅うすくれない
の、ひどく古びて表面が白っぽく色褪せた一襲ひとかさね
の上に、色目にも見えないほどすっかり黒ずんだ紫色の袿を重ねて、表着うわぎ
には黒貂くろてん の皮衣かわぎぬ
の、たいそう艶やかで香をたきしめてあるのを着ていらっしゃいます。古風な由緒ある御衣裳ですけれど、やはり若い姫君のお召物としては不似合いで、ものものしすぎるところがとりわけ目につきます。けれども、yはりこの皮衣がなくてはさぞお寒いことだろうと思われる姫君のお顔色なので、お気の毒だと同情なさって御覧になるのでした。
源氏の君は呆れて何もおっしゃらず、ご自分までも口が塞ふさ
がったような気持がなさいますけれど、例の姫君のだんまりをどうにかして破ってみようと、何かと話しかけてごらんになるのでした。
姫君は、一途に恥ずかしがられて、口もとを袖でかくしていらっしゃる仕種までが、野暮ったく古風で、勿体もったい
ぶっています。
ちょうど儀式官が式の時に、仰々しく笏しゃく
をかまえた肘を張っているのを見るようです。それでもさすがに姫君は笑っていらっしゃるのが、何とも言えずみっともなくしっくりしないのでした。そんな姫君がおいたわしくてたまらなく、源氏の君はいつにもまして、いっそう急いでお発た
ちになりました。
「ほかに頼りになるお方もいらっしゃらないのですから、ご縁を結んだわたしには、冷たなさらず、睦まじく親しんで下さってこそお世話の甲斐があると思いますのに、いつまでも打ち解けて下さらない御様子なので、ほんとに恨めしく思います」
などと、早く帰るのを姫君のせいにして、
|