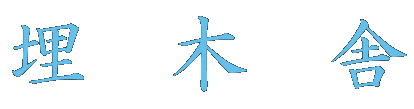御車を寄せてある中門
がたいそうひどく歪んで倒れかかっていて、昨夜夜目にはそれがわかっていても、なんとか暗さに隠されていることが多かったのに、今朝見ると、ひどくあわれに寂しく荒れはてているのに、松の雪ばかりが、あたたかそうに降り積もっています。その景色が、山里のような心地がしてしみじみともの哀れです。それを御覧になった源氏の君は、
「そういえばあの雨の夜の品定めの時、左馬さま
の頭かみ たちが話していた美女の住む葎むぐら
の宿とは、こういう所を言ったのだろう。なるほど、可哀そうな身の上のかわいらしい女を、ここに住まわせて、気がかりでたまらないような恋がしたいものだ。そうすれば、恋してはならぬあのお方への切ない物思いも、それにまぎれることだろう」
とお思いになります。
「ここは全く物語の中の荒れ果てた葎の宿のように、住んでいる姫君はおよそそれにふさわしくない御様子なのだからお話にならない。これが自分でなかったら、なおのこと、とてもこの姫君には辛抱できないだろう。自分がこうして姫君に通うようになったのは、亡き常陸の宮の御魂みたま
が、姫君の身の上を御心配のあまり、姫君の身につき添われていて、お導きになったのだろう」
とお考えになります。
橘たちばな
の木が雪に埋もれているのを、随身ずいじん
を呼ばれて、雪を払わせられます。それを羨うらや
み顔に、松の木は自分で起きかえって、その拍子にさっと落ちこぼれる雪が、<わが袖は名に立つ末の松山か> という歌の情景に見えるのを御覧になって、さほど深い嗜たしな
みなくても、こんな時、一通りの気のきいた受け答えの出来る人がいて欲しいものだとお思いになります。
お車を曳き出す門はまだ閉まっておりましたのでゑ、鍵の番人を探し出しますと、大層な年寄りが出てまいりました。老人の娘か孫か、どっちつかずの年頃の女が、雪に映えてひどく汚れて、すすけの目立つ着物を着て、いかにも寒そうな様子をしながら、妙な器に火をほんの少し入れて、袖で囲って持っています。
老人がなかなか門を開けられないのを、側に寄って力を合わせて女が手伝っているのですが、いかにも見苦しく見えます。源氏の君のお供の人たちが、寄っていって開けました。
|