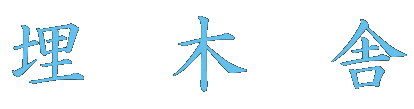「帚木」
のはじめに、源氏の性質として 「うちつけのすきずきしさなどは、このましからぬ御本性にて」 とあるのは、源氏の恋愛の嗜好をはっこり打ち出している。成立し難い恋、無理な恋、邪魔のある恋、許されぬ恋等、気苦労の多い恋に挑む時だけ、源氏は情熱がかきたてられる。いわゆる据え膳には全く興味も情熱も湧かないのである。後につづく源氏の恋のすべては、この独特の源氏の性質から出ていることを読者は承知しているべきである。
源氏が申し分ない正妻の葵
の上にどうしても愛情が湧かないのは、父帝や左大臣によって与えられた、努力も苦労も伴わない関係だったからである。
十七歳といっても数え年だから、今では十六歳のまだ高校生だ。なんという早熟な不良少年かと愕くところだが、この時すでに、父帝の妃、自分にとっては義母に当る藤壺と、思いを遂げていることがぼんやり示されている。
「帚木」
の帖に、源氏が伊予の守の家に行った夜、女房たちが自分の噂話をしているのを盗み聞く場面がある。
「胸深く秘めていらっしゃることばかりが気にかかっているので、まずどきりとなさいます。こんな折にでも、女房たちがあのお方との秘めごとを口にすべらせるのを聞きつけたら、どうしようか」
と思うと恐ろしくなるという源氏の脅えには、単なる片想いではない切迫したものが感じられる。
この時点で、すでに何等かの形で、藤壺と肉体的に不倫の関係を結んでいたと解釈出来るのである。
藤壺を得た自信が、なかなか逢えない藤壺の代用品として、同じ高貴の、得難い女性にょしょう
の六条の御息所に近づかせたのだろう。
紀伊の守の邸では誰はばからぬ強引な態度で人妻に近づき犯す源氏の太々しさには、最高の女性を二人も立て続けに掌中にした若者の自信の裏打ちがあったのである。
しかし、夕顔の死に際して、源氏が身も世もなく馬から落ちるほど自失して、嘆き悲しむ姿を見せられて、読者はほっとする。この我を忘れた悲嘆ぶりには、青年の純情さが感じられるし、万一、よみがえった時、自分がいなかったら、夕顔がどう思うだろうと、見栄も保身もかなぐり捨てて、死体を運び込んだ東山の秘密の場所に、出かけていく源氏の一途さも、若さゆえの情熱と純愛の発露で、感動的である。
藤壺への初恋は、母恋いの変形だと取る説もあり、この許せない所行も、その一点で許せると観る節もあるが、そんな通俗的な発想ではなく、源氏の恋愛事件のいざこざは、あくまで、困難な恋にしか情熱が湧かないよいう源氏の持って生まれた因果な性格によるものだろう。
コンスタンの 「アドルフ」 の中に、 「すべては性格の悲劇です」 という言葉があるが、源氏の生涯を貫くものは、この性格がもたらす悲劇に外ならないと思う。
男性の読者に、源氏物語の中で好きな女性はと訊くと、異口同音に
「夕顔」 と答える。夕顔という女は、それほど男性にとっては好ましい永遠の女性であるようだ。可憐で、謎めいて、おとなしく、性的にもすばらしい。男の言いなりに、心も体も、飴のようにとろけさせ自在に曲げ、水のようにどんな男のすき間も満たそうと、ぴったり密着してくる。まるで我というものが全くないように見える女。ところが紫式部は、この夕顔にもっと、不思議な魅力を書き加えている。
廃院へ連れ出して、はじめて源氏が覆面を取って、顔を見せ、
「どうだい、この顔は、御感想はいかが」 というような歌を自信たっぷりに詠みかけると、夕顔は流し目にvひらと見て、 「前にちらりと見てすてきと思ったのは、たそがれ時のひが目だったのかしら、間近で見ると、大したこともなかったわ」
という返歌で、やんわり返す。決して、個性のない無色な女ではないのである。こうした反応の仕方を見ても、ユーモアも解するし、とっさの機転もきく、手応えのある女だったのだ。
|