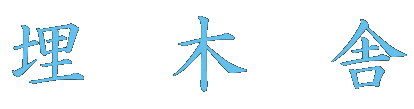外は朝霧が深く立ちこめ、空の風情もひとしおお情趣深い上に、地には霜が真っ白に降りていました。こういう朝こそ、ほんとうの恋の朝帰りにもふさわしいのにと、源氏の君は昨夜のことをもの足りなくお思いになられるのでした。
たいそう人目を忍んでお通いになっていらっしゃる家が、この途中にあったのを、ふと思い出されて、門を叩かせてごらんんいなりましたが、聞きつけて出迎える人もありません。仕方なくお供の中で声のよい者に、歌わせてごらんになります。
|
朝ぼらけ 霧立つ空の
迷ひにも 行き過ぎがたき 妹が門かな
(あさぼらけの空に 霧が立ち迷い 見分けもつかない中にも ふと素通りしかねる恋しい
あなたの家の門だった) |
|
| と繰り返し二度歌いますと、気のきいた下仕
えの女房が出て来て、 |
立ちとまり
霧のまがきの 過ぎうくは 草のとざすに さはりしもせじ
(立ち止まって 霧の立ち込めたこの垣根が 素通りしにくいにのでしたら
草の戸がしまっていることなど 何の妨げにもなりますまいに) |
|
と詠みかけて中に入ってしまいました。それきり、もう誰も出て来ないので、このまま引きあげるのも情がないものの、見る見る空も明けわたってきて不都合ですから、そのまま二条の院へお帰りになりました。
あの可愛らしかった姫君の面影がなつかしく恋しく、源氏の君は独り笑いなどもらされながらお寝みになるのでした。
日が高くなってからお起きになり、姫君にお手紙をおあげるにつけても、普通の恋人同士の後朝きぬぎぬ
のお手紙のようなわけにも書けないので、幾度も筆をお置きになり、思案しては熱心に書いていらっしゃいます。面白い絵などをお手紙に添えて、お届けになりました。
姫君のお邸では、ちょうどその日、父宮の兵部卿の宮はお越しになりました。尼君の歿後は、その前頃よりも、いっそう荒れの目立つだだっ広くて古めかしい邸内に、ますます人も少なくなってもの淋しいのを、兵部卿の宮はつくづく見渡されて、
「こんなところに、わずかの間にしろ、幼い姫君がどうして過ごすことが出来よう。やはりあちらの邸に引き取ってあげよう。あちらは何の気がねもいらない。乳母には部屋をあげるから、今まで通りお仕えするがいい。あちらには小さい姫たちもいることだから、一緒に遊べて、きっとうまく楽しくやっていけるだろう」
などと仰せになります。宮はお側近くに姫君をお呼び寄せになりますと、源氏の君の移り香が姫君のお召物に、たいそうなまめかしく染みついていらっしゃるので、
「おや、いい匂いだね、着物はすっかりくたびれているにに」
と、お可哀そうにお思いになります。
「この幾年もの間、御病気の重い老尼と一緒にお暮らしだから、時々はあcぎらの邸に行って、みんなと馴染みにおなりなさいとすすめたけれど、こちらの尼君が妙に向こうをお嫌いになるし、北の方も遠慮があったようだった。こんな時にあちらに移られるのも、何だか可哀そうな気もして」
などとおっしゃいますと、乳母は、
「いえいえ、そのご心配には及びません。心細くても、もうしばらくこのままにしておおきになられるのがようございましょう。もう少し、このごとの分別がお出来になられてから、あちらへお移し申し上げるのが、よくはございませんせしょうか」
と申し上げます。
「まだ夜昼、尼君を恋しがられて、ほんの少しのものもお召し上がりになりません」
と乳母が申します通り、たしかに姫君はたいそうひどく面やつれいらっしゃいます。それでかえっていっそう上品で可愛らしくお見えになります。
「なぜぞんなに尼君を恋しがられるのですか。亡くなってしまわれた尼君のことは、いくら恋しがっても、もうどうしようもないのです。わたしがついているのだから安心なさい」
など、よく話してお聞かせになって、夕暮れにはあちらのお邸へお帰りになろうとなさいます。姫君はそれを見てたいそう心細く思われて、お泣くになるので、宮も貰い泣きされて、
「ほんとうに、そんなに思いつめないように、今日、明日にも、あちらへお連れしますからね」
など、かえすがえすなだめすかされてから、お出ましになりました。
姫君はその後、かえって寂しくなり、泣いてばかりいらっしゃいます。姫君はこれから先、御自分の運命がどうなっていくかなどお考えにもなれず、ただ今まで長い間、いつも離れる時もなくて、お側で馴れ親しんでいられた尼君が、今はもうお亡くなりになってしまわれたと思うと、ただもう悲しいばかりなのです。幼いお心にも悲しみに胸がふさがって、いつものように遊びもなさいません。昼は何とかまぎらせていらっしゃるものの、夕方になれば、ひどくふさぎ込んでおしまいになりますので、
「この様子ではこの先、どうしてお暮らしになれよう」
と、姫君を慰めかねて、乳母も一緒に泣いてしまうのでした。
|