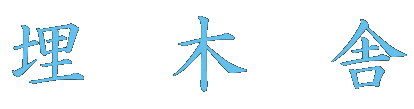源氏の君は右近に、
「さあ、一緒に二条の院へ行こう」
とおっしゃいましたが、
「長年、幼かった時から、片時もお側を離れずにお仕えいたしましたお方に、急にお別れいたしまして、今更、どこへ帰っていけましょう。お亡くなりになったいきさつを、どう人に話せばよろしいのでしょう。自分の悲しいことはともかくとして、わたしがおつきしていてどうしたのかと、五条の家の人たちに、とやかく取り沙汰されるのが辛うございます」
と申し上げて、正気も失いそうに泣きつづけ、
「火葬の煙にまじって、私もお跡を追います」
と言います。
おまえのそう「嘆くのももっともだけれど、この世は、こんなふうに無常なものなのだ。別れというものはすべて悲しいものなのだ。先に死ぬのも、後に残るのも、誰も同じ命で、いつかは限りがあるものなのだ。何とか悲しみをまぎらして、わたしを頼りにするがいい」
と、お慰めになりながらも、すぐ、
「そういうわたし自身こそ、ほんとうに生き残っていられそうもない気がする」
とおっしゃいますのも、何とも頼りないことでございます。惟光が、
「夜が明けそうになりました。早くお帰りにならなくては」
と申し上げますと、源氏の君は、ふりかえり、ふりかえりなさりながら、お胸もいっぱいに塞がったまま、お発ちになったのでした。
お帰りの道すから、道の辺の草に露がしとどきに置き、おびただしい朝霧が立ち込めて、涙とともに視界をかき消し、どことも知れぬ無明の闇をさ迷っているようなお気持がなさいます。
生前の姿のまま、横たわっていた亡き人の俤
や、昨夜お互いに交換しあったご自分の紅くれない
のお召物が、亡骸に着せ掛けてあった様子などを思い出されては、どうした前世の因縁でこうなったのだろうと、道々ずっとお考えになるのでした。
お馬にも堂々とお乗りになれないほど弱りきった御様子なので、お帰りもまた、惟光が付き添い、お助けしながらお供して行きます。
賀茂川の堤のあたりで、とうとう馬からすべり落ちて、耐え難く御気分が終るくなられました。
「こんな道端で、死んでしまうのだろうか。もう二条の院にもたどりつけないような気がする」
と、おっしゃいますので、惟光も気持が動転してしまいました。自分がしっかりしていたら、どんなにおっしゃろうが、あんなところへお連れ申すのではなかったのだと後悔すると、ひどく心がそわそわして落ち着かないので、賀茂川の水で手を洗い清めて、清水の観音さまをお祈りしましても、どうしていいか一向にわからず、途方にくれきっています。
源氏の君も、強いて気持を奮いたたせて、心中に仏を祈念なさいまsy。何とか惟光に助けられて、ようやく、二条の院にたどり着かれたのでした。 |