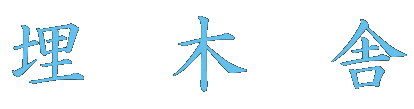その時、滝口の男が紙燭を持って来ました。右近もほとんど気を失い、動ける様子もありませんでしたのでm源氏の君は近くにある几帳
をお引き寄せになられて、
「もっと近くへ持ってまいれ」
と、お命じになります。お側近くへ参るなど例のないことなので、男はとても近寄れず御遠慮して、縁から室内へも上がることが出来ません。
「もっと近くへ持って来るのだ。遠慮も時と場合による」
とおっしゃって、紙燭を取り寄せて女君をご覧になりますと、その枕上に、あの夢に見たときと同じ顔をした女が、幻のように浮かび、ふっとかき消えてしまいました。
昔の物語などには、こういう話しは聞いているものの、こんな異様なことが現実に起こるとは只事でなく、気味が悪くてなりません。
けれどもとにかく、この人がどうなっているかと、心配で動揺なさり、御自分に害の及ぶことなどお考えになるゆとりもなく、そっと側に添い寝しておあげになり、
「ねえ、どうしたの」
と目を覚まさせようとなさいました。けれども夕顔の女は、ただもうすっかりひえびえと冷たくなってしまっていて、息はとうに絶え果てていたのでした。もはや、どうしようもありません。
こんな場合、どう処置をとればいいのか、相談できる頼もしい人もおりません。法師などがいてくれたら、こんな時に頼りになるのにとお思いになりますけれど、あれほど強がってはいらっしゃったものの、何としてもまだお若いので、目の前で女が、はかなくなられたのをご覧遊ばしては、やりきれなくなられて、冷たい女の体を、しっかり抱きしめられて、
「ねえ、お願いだから、どうか生きかえっておくれ、こんなつらい目を見させないでおくれ」
と、悲しまれるのですが、女の体はもう冷えきっていて、次第にうとましい死相まであらわれてまいります。
右近は、ひたすら恐ろしいとばかり脅えていた気持も、すっかり覚め果てて、ひた泣きに泣き惑う様子もあわれなももでした。
昔、宮中の南殿なんでん
の鬼が、何とかいう大臣を脅かした時、かえって大臣に叱られて逃げてしまったという話など思い出されて、源氏の君は気強く心を引き立てて、
「まさかこのまま、なくなってはしまわないだろう。夜の声はとかく仰々しく響く。静かにしなさい」
と、泣きじゃくる右近をお叱りになりながらも、御自分も、あまり突然の慌ただしい出来事に呆れていらっしゃいます。さっきの滝口の男をお召しになり、
「不思議な事だが、ここに、突然物の怪におそわれた人がいて苦しんでいるので、大至急、惟光の朝臣の家に行って、急いで来るようにと、随身に命じなさい。また惟光の兄の阿闍梨あじゃり
もその家に居合わせていたら、一緒にここへ来るようにと、こそり言いなさい。あの尼君などが聞くといけないから、びっくりするような大きな声で言ってはならない。尼君はこんな夜歩きをきびしく叱る人だから」
などと、口ではお命じになっているようですけれど、お胸は一杯になっていて、この人をこのまま空しく死なせてしまうことが辛くてたまらない上に、あたりの気配の不気味さはたとえようもありません。
夜風がさっきより少し荒々しく吹きはじめているのは、もう真夜中も過ぎたのでしょう。まして松風の響きが深い木立の中に陰々ろ鳴りひびき、聞き馴れない鳥が、しわがれた声で鳴いています。梟ふくろう
というのはこれなのだろうと思われます。
あれこれお考えになりますと、どこもかしこも馴染みが薄く、嫌なところなのに、その上、人声さえ全くしないのです。どうしてこんな心細い所に泊まったりしたのだろうと、いいようもなく後悔がつのりますが、今更どうしようもありません。
右近は無我夢中で、源氏の君にしっかりと、としすがったまま、わななき震えて、今にも死に入りそうなありさまです。この女も死ぬのではないかと、源氏の君は心も上の空で右近の体をつかまえておやりになります。
自分ひとりだけが正気なのだと思うと、どうしようもなく、分別もつきません。
燈火はほのかにまたたいて、母屋もや
との境に立てた屏風びょうぶ の上の方や、そこかしこ隅々に黒い闇がただよい、気味悪く思われます。背後からひしひしと足音を踏み鳴らしながら、何者かが近づいて来るような気持がします。
惟光が早く来てくれればいいのにとひたすら待ち遠しくなられます。女に通う所が多く、いつでも居場所の定まらない男なので、随身があちこち尋ね探しているらしく、待つ身にとっては夜が明けるまでの長さは、千夜を過ごすようにもお感じになるのでした。
|