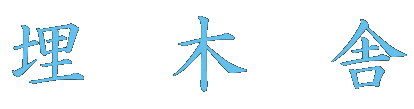「実は、同じその頃、もう一人、通っていた女がありました。そっちは人柄もずっとよく、心ばえも奥ゆかしく見え、歌も上手に詠み、文字も流麗で、琴の音色もおよそ手でする技、物のいい方など、すべてなかなかのものでした。器量もまあ見られるほうでしたから、例の嫉
きもち焼きの女を、遠慮のいらない世話女房とし、こちらへ時々かくれて通っている分には、とても気に入ったいました。
嫉きもち焼きの女が亡くなりましたので、可哀そうでしたが、今更どうなるものでもなし、自然残った女の方へ足繁く通うようになりました。ところがそうなってみると、少し派手すぎて、なんとなく色っぽく浮気らしい点が鼻についてきまして、信頼できないと思い、通うのも間遠になっていました。
その間に、他の男がこっそり通いはじめていたのでした。十月の月の美しいある夜のことでした。わたしが宮中から退出しようとすると、一人の殿上人が来合わせて、わたしの車に相乗りして来ました。わたしは父の大納言の家へ泊るつもりでしたところ、この男が、
『今夜、わたしを待っているにちがいない女のことが、妙に気にかかって』
と言います。わたしのその女の家が丁度通り路にあたっていましたので、そこまで同行するはめになりました。荒れた築土塀の崩れから、池の水に月影が宿っているのが見えます。月さえ宿る家を、素通りも出来かねて、車を降りた男の後から、わたしもこっそりついて行きました。前から情を交し合っていたと見えて、男はひどくそわそわしながら、中門に近い廊の縁側のような所に腰を下ろし、しばらく月を見ています。前庭の菊が霜にあい、色が変わりはじめたのもおもむきがあります。風に先を争って紅葉が散り乱れる様なども、なかなか情趣の深い眺めです。男は懐から横笛を取り出して吹きはじめました。<飛鳥井あすかゐ
に 宿りはすべし や おけ 蔭もよし・・・・> など、思わせぶりに笛の音の合間、合間に謡ううちに、女は音色の美しい和琴わごん
の調子を、用意周到に整えてあったと見え、歌に合わせて見事に合奏したところなどは、なかなかのものでした。 「飛鳥井」 のような律りち
の調べは、女の手でものやわらかく掻き鳴らすのが御簾みす
の奥からもれ聞こえてきますと、和琴は現代風のやわらかな音色ですから、澄んだ月影に折から実によく調和いたします。男はすっかり感激して、御簾の近くに歩み寄って、
『この庭の紅葉だけはまだ誰も踏み分けた跡はありませんね、あなたの恋人は冷淡なようですね』
などと皮肉を言っています。菊を手折って、 |
琴の音ね
も 月もえならぬ 宿ながら つれなき人を ひきやとめける
(琴の音も月の光も 美しく清らかな 宿だというのに つれない人を
あなたは ひきとめられなかった) |
|
『いや、どうも失礼しました』
などと言って、
『今一曲お願いします。こんな聞き手のある時は、手をおそまずお弾きになるものですよ』
などと、いやに馴れ馴れしく戯れかかると、女は気取った作り声をして、 |
木枯らしに
吹きあはすめる 笛の音ね を ひきとどむべき
言こと の葉ぞなき
(木枯らしに合奏する
あなたの激しい笛の音色 その音にも似たひどいことを おっしゃるあなたを引きとめる言葉なぞ 持っているものですか) |
|
と、いちゃつきあいまして、わたしがむしゃくしゃしているのも知らずに、今度は箏そう
の琴を盤渉調あんしきちょうの調子にして、当世風に掻き鳴らす爪音は、うまくないとはいえませんが、こちらは気恥ずかしくて、やりきてない気持がしなした。ただ時たま親密につきあうだけの女房などが、限りなくあだっぽくて浮気なのは。浅い仲の相手としてはおもしろいことでしょう。
しかし通い所のひとつと決めて生涯の伴侶とするには、そういう女は色っぽすぎて、危なっかしく厭気がさします。出過ぎてもいるようなので、その夜のことにかこつけて、その女とは別れてしまったのです。
この二つのことを考え合わせてみますと、若い頃のわたしの頭でも、そういう色っぽい女の振舞は、どうも怪しく、信頼できないように思いました。若くもないこれからは、ましてますます、そう感じることでしょう。
あなた方も、お心にまかせて、手折ればこぼれそうな萩の露のように、男の誘いを待ちのぞんでいる女とか、手に掬すく
おうとするとすぐ消え失せそうな風情の、玉笹の上の霰あられ
にも似た、いかにもはかなそうな、色っぽい女ばかりを面白くお思いになるでしょうが、まあ七年、八年もしましたら、そのうちおわかりになりますでしょう。
数ならぬわたしの忠告をお聞き下さって、色っぽく男に靡なび
きやすい女には、せいぜい御用心遊ばせ。そういう女はきっと不貞な過ちをしでかして、夫のためにもみっともない評判をたてられるに違いないのです」
と戒めます。
頭の中将は、例によって感心してうなずいています。源氏の君も少しほほ笑みながら、そういうことはありそうだなろお思いのようです。
「どちらにしても、みっともなく、外聞の悪い身の上話しだね」
と笑っていらっしゃいます。 |