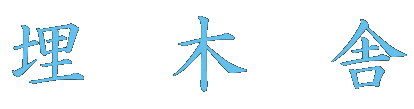悲しみのうちにいつとなく日々は過ぎてゆき、七日ごとの法要にも、帝はお心をこめて更衣のお里へ弔問の勅使を送られます。
そうした時が過ぎてゆくにつれ、帝はいっそう耐えがたいほどやるせなく悲しく、お妃たちを夜の御寝所にもふっつりお召しにならず、ただもう涙に溺れて明かし暮していらっしゃいます。そのお悲しみの御様子を拝する人々までが、涙に袖もしめりがちなうちに、いつの間にか露もしめっぽい秋になりました。
「亡くなった後まで、人の心をかき乱すあの女の憎らしいこと、それに相も変わらない帝の何というご未練」
と、弘徽殿の女御は、今でも相変らず、手きびしく悪口をいわれます。
帝は一の宮をご覧になるにつけても、更衣の若宮が無性に恋しくなられて、気心の知れた女房や
御乳母
などを、更衣のお里に遣わされて、若宮の御様子をお尋ねになります。
野分めいた荒々しい風が吹きすぎた後、急に肌寒くなった
黄昏
たそがれ
時に、帝は常にもまして亡き更衣や若宮を思い出されることが多いので、
靫負
ゆげい
の
命婦
みょうぶ
という女房を更衣のお里にお遣わしになられました。
夕月の美しく冴えかかる時刻に、命婦をお使いに出されて、帝はそのままもの思いにふけっていらっしゃるのでした。
「こんな美しい月夜には、よく管絃の合奏などして楽しんだものだが、そういう折には、あの人はとりわけ美しく琴の音をかい鳴らし、さりげなく口にする歌のことばも、他の人とはどこかちがっていて心にしみたものだ」
そんな折々の更衣の表情やしぐさなどが、ありし日のままに思い出されて、今もそのまま、幻になってひたとおん身に寄り添っているかのように思われます。それでも、やはりその幻は、闇の中での逢瀬は、はっきり見た夢のそれより劣っていたという古歌とは反対に、闇の中でこの手に触れたあの生きていた人にはといてい及ばなかったのでした。
命婦は更衣のお里に着き、車を門に引き入れると、そこにはもう、いいようもないもの淋しく悲しい気配が、あたりじゅうに漂い満ちているように感じられます。
母君は、夫に先だたれた心細い暮らしの中にも気を張り、更衣一人を大切に守り、人に引けをとらせぬよう、邸の内外も何かとよく手入れをして、体裁よく暮してこられました。ところが更衣に先だたれからは、悲しみのあまり、泣き沈んで庭の手入れも怠り、雑草も茂るにまかせ高くぼび放題です。
野分にそれが吹き倒され、見るも無残に荒れはてた感じになっています。月の光ばかりは、生い茂った雑草にもさえぎられず、あたり一面にこうこうとさしいっています。
命婦を
南面
みなみおもて
の
間
ま
に招じ入れたものの、母君は涙にむせび、すぐには口もきけません。
「今まで生き永らえているのさえ、つくづく辛うございますのに、
畏
おそ
れ多い勅使としてあなたが草深い荒れ庭の
蓬
よもぎ
の露を踏み分けて、こうしてお訪ねくださるにつけても、いっそうお恥ずかしく身の置き所もございません」
といいながら、耐え切れないようによよと泣くのでした。
「こちらにお伺いいたしますと、それはもうおいたわしくて、魂も消え入るようでしたと、せんだって
典侍
ないしのすけ
が帝に
奏上
そうじょう
なさっておられましたが、たしかにわたしのように物の情趣もわきまえない者にも、ほんにおいたわしくて、耐えきれない気持がいたします」
と言い、しばらく心を静めてから、帝のお言葉をお伝えいたしました。 |