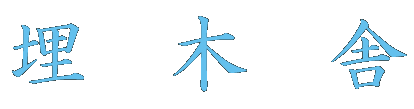日本のキリスト教会において、リバイバル
(信仰復興運動) があまり頻繁には起こらないことも、同じくこの克己の訓練から説明できる。
男女を問わず、人はその魂が揺さぶられた時、はじめは本能的にそれが外に現れるのを抑えようとする。抑えることの出来ない感情によって自然と言葉が発し、誠実かつ熱烈に雄弁をふるうことは、きわめて稀だった。軽々しく霊的な経験を口にするよう促すことは、第三戒
(あなたの神、主の名を妄りに口にしてはならない) への違反を奨励することである。
もっとも神聖な言葉、もっともひそかな心の経験が、雑多な聴衆への中で述べられるのを聞くことは、日本人には本当に耳障りなのである。
「あなたの魂の土壌が微妙な思想で動かされるのを感じるか。それは種子が芽を出す時である。それを言葉で邪魔するな。むしろ、静かに、秘
やかに、それを働くままにしておけ」 と、ある若い武士は日記に書いた。
心の奥底の思いや感情 ── 特に宗教的なもの ── を雄弁に述べ立てることは、日本人の間では、それは深遠でもなく、誠実でもないことの疑いないしるしだと受け取られた。川柳にも、
「口開けて腸はらわた 見せる柘榴ざくろ
かな (口を開けて心の中を見せる人は柘榴にすぎない) というのがある。
感情が動かされた瞬間、それを隠すために唇を閉じようとするのは、東洋的な心のひねくれでは決してない。しゃべることは、私たちにあっては、かのフランス人
(タレイラン) が定義するように、 「思いを隠す技術」 なのである。
日本の友人を、彼がもっとも深い悲しみにある時に訪問してみよ。彼は、目を真っ赤にし、頬をぬらしながらも、いつもと変わらず笑みを浮かべてあなたを迎えるだろう。
あなたは、最初、彼が狂ったかと思うかも知れない。しかし、しいて彼に説明を求めたとしたら、
「人生憂愁多し」 とか 「会者えしゃ
定離じょうり 」 とか 「生者必滅」
とか 「死児の齢よわい を数えるのは愚かだが、女心は愚痴にふける」
とか、二、三の断片的な常套句じょうとうく
を聞くであろう。そのように、ホーエンツォレルン家の高貴な人の気高い言葉 ── 「つぶやかずに耐えることを学べ」 という言葉が発せられるはるか以前から、わが国民の間にはこれに共鳴する多くの心があったのである。
じっさい日本人は、人間の本質的な弱さがもっとも厳しい試練に直面した時でさえ、いつも笑みを浮かべる癖がある。私たちのアブデラ的
(よく笑う) 傾向に対しては、デモクリトスその人よりも上等な理由がある、と私は思う ── というのも、私たちにあっては、笑いは逆境によって乱された心の平衡を回復しようとする努力を隠す幕だからである、それは、悲しみや怒りの均衡をとるためのものである。
こうした感情の抑制が常に要求されたため、詩歌がそのはけ口となった。十世紀のある歌人
(紀貫之) は、 「かやうの事、歌このむとてあるにしもあらざるべし。唐土もここも、思うふことに堪へぬ時のわざとぞ
(和歌を詠むのは、それが好きだからということでもない。中国でも日本でも、悲しみに堪えきれない時の慰めなのだという)
」 と書いている。
ある母親 (加賀千代女) は、亡くなった子がいつものように蜻蛉とんぼ
を捕りに出かけて不在なのだと想像して、その傷心を慰めようと次の句を吟じている。
蜻蛉つり 今日はどこまで 行ったやら
他の例をあげることは控えよう。なぜなら、一滴一滴血をしたたらせるように胸から搾り出され、至高の価値あるネックレスのようにつなぎ合わされた思いを外国語に翻訳しようとすれば、わが国文学の珠玉の真価をかえって傷つけることになることを恐れるからである。 |