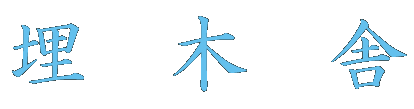アリストテレスや何人かの近代社会学者と同じように、武士道では、国家と個人に先立って存在し、個人は国家の構成要素ないしは分子としてその中に生まれてきた、と考えられた。そのため個人は、国家のため、もしくは正当な権威を掌握するする者のために生き、また死なねばならなかった。
『クリトン』
を読んだ者は、ソクラテスの逃走問題について、彼と国法との間の論争として描かれた議論を覚えているであろう。ソクラテスは、法あるいは国家にこう言わせている。──
「お前はわれらの下に生まれ、養われ、かつ教育されたのであるのに、お前もお前の先祖も。わららの子、そして召使でもないとお前は言うのか。」
この言葉は、私たち日本人に何らの違和感も感じさせない。というのは、同じ言説が、長く武士道で口にされてきたからである。ただし、法および国家が、わが国にあっては一人の人格によって体現されたという違いはある。忠義は、この政治論理から生まれた倫理である。
政治的従属
── 忠義 ── を、過渡的機能にすぎないとするスペンサー氏の見解を、私はまったく知らないわけではない。おそらく彼の言う通りだろう。しかし、その日の德はその日で十分である。私たちは日々を安心してくり返そう。
「その日」 というのが長期間であって、その期間とは日本の国歌の一節 「さざれ石の巌となりて苔のむすまで」 であることを私たちは信じるのだから。
これに関連して、イギリス人のような民主的国民の間であっても、
「一人の人間とその子孫に対して個人の心から発する忠誠の感情は、彼らの祖先であるゲルマン人がその首長に対して抱いていたものであり、これが多かれ少なかれ伝わって彼らの君主の血統に対する深い忠義となる。それは王室に対する彼らの異常な愛着に示されている」
と、ブートミー氏は最近述べたことが想起される。
政治的従属は、良心の命令への忠義にとって代わられるであろう、とスペンサー氏は予言する。彼の推論が実現するとして、忠義とそれに伴う崇敬の本能は、永久に消え失せるだろうか。私たちは、みずからの服従を一人の主君から他の主君へ、どちらにも不忠を働くことにならない形で移す。すなわち、地上の王権をふるう支配者への臣下であることから、私たちの心の奥殿に座す王の臣下となるのである。
数年前、心得違いのスペンサー学徒によって、とてもばかげた論争が引き起こされ、わが国の知識層の間に混乱を捲き起こした。彼らは、皇室への全面的な忠義を擁護するに熱心なあまり、キリスト者はその主に忠誠を誓うものであるゆえに、大逆の傾向があると攻撃したのである。
彼らは、ソフィスト
(詭弁者) の機知もないのにソフィスト的議論を組み立て、スコラ学徒の緻密さもないのにスコラ的なひねくれた議論を展開した。キリスト者が、ある意味においては、
「一方に親しみ、他方を嫌うことなしに、二人の主に仕える」 、つまり 「カエサルの物はカエサルに、神の物は神に納める」 ことを、彼らは知らなかったのである。 |