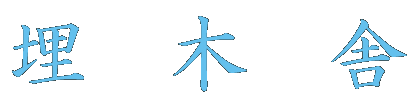ネボガトフの旗艦ニコライ一世について来ている残存軍艦は、二番艦がほんんお昨日まで世界でもっとも新鋭とされた戦艦アリョールであり、この艦には主計兵ノビコフ・ブリボイが
「自分の艦はまるで筏 のような姿になった」
とあきれつつも無事に勤務していた。
第三番艦がアブラシンクで、殿しんがり
を走っているのがセニャーウィンである。もう一艦いる。快速をもって知られた巡洋艦イズムールドで、この艦は旗艦と並航してネボガトフのために通報艦の役目を引き受けていた。
ネボガトフ少将は、五十の半ばをすぎている。彼はロジェストウェンスキーのような海軍省における官僚的な切れ者ではなかったが、練達の船乗りとして知られていた。
ずんぐりした体に白い戦闘服をまとい、黒いズボンをはいている、髪もふげも真っ白で、目が大きく、変に愛嬌があって、軍人というより商店のおやじといった感じだった。
まだ海上に残光が残っているころ、味方の駆逐艦が彼の旗艦の横を通り抜けて行った。この時、その駆逐艦が、ロジェストウェンスキーの命令というのを伝えたのである。
その内容は、指揮権をネボガトフに移譲すること、針路をウラジオストックにとれということであった。ロ提督がスワロフを脱出して駆逐艦に移ったとき、その命令を出した。その命令が逓伝ていでん
されて、いま通り過ぎた駆逐艦が伝達役になったのである。
夜に入って、日本の水雷戦がはじまった。
この夜、ネボガトフとその艦隊は運がよかった。というより、彼はかねて自分の艦隊に無燈航行の訓練をしておいたため、この夜、闇にまぎれることによって幾度かの危機をすりぬけた。
彼はたとえ日本の駆逐艦や艇隊が近づいて来ても探照燈をつけることを禁じ、射撃さえ禁じていた。
彼は旗艦の艦長が倒れてしまったため、自分で操艦していた。魚雷が近づいても、ひどく落ちついた態度で、面舵おもかじ
とか取舵とりかじ とかいってこれをかわした。
──
ネボガトフが居るかぎりは安心だ。
という気分が、旗艦乗組みのすべてに横溢おういつ
していた。この老練で冷静な彼が翌日、東郷が出現した時、戦わずして洋上で降伏するとはたれも想像出来なかったし、むろんこの艦がのちに日本の艦籍に入って 「壱岐いき
」 という名前に改められようとは夢にも思っていなかった。
ネボガトフは、一度もそのことを言動にあらわしたことがないが、こういう寄せ集めの老朽艦を自分に率いさせてロジェストウェンスキーの艦隊に合流せしめたロシアの海軍省というものをひどく憎んでいた。勝てるはずがなかった。水兵までが
「自沈艦隊」 と、みずからの艦隊を嘲笑していたし、航海中面倒をみてくれたフランス海軍でも 「犠牲の艦隊」 と密かに呼んでいた。極東を征服するための戦争を起こした以上は、ロシア帝国は勝つための態度をとるべきであった。ネボガトフはもしウラジオストックへたどり着けなかったならば兵員の命を救うため、みずから死刑を覚悟して降伏しようと考えていた。 |