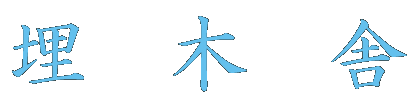午後五時過ぎ、旗艦スワロフは、かつてそのマストに聖アンドレーエフの軍艦旗と、皇帝の指揮権を代行する司令長官旗が翻っていた栄光の新鋭戦艦とはとうてい思えないような姿で海面にうずくまっていた。
甲板の上は鉄屑の山であった。砲塔は裂け、艦橋は炎の中にあり、マストは吹っ飛ばされていた。艦体は左へ傾いていたがそれでのなお沈没しないというあたりに、戦艦の不沈性を目標としたこの時代の造船技術の水準のサンプルを見るような景況であった。
この時期、ロジェストウェンスキーは右舷中部砲塔の中で、拳闘に敗れた闘士のように横たわっていた。全身に無数の擦過傷があり、両脚も動かなかった。頭部に仮繃帯
が巻かれていたが頭蓋骨の一部が陥没し、そのおびただしい出血が繃帯を赤く染めていた。意識はあった。しかしときどき薄れた。
スワロフは、孤艦になっていた。もっとも工作艦カムチャッカだけがそばにいた。カムチャッカはこの辺りを通りかかったのだが、どうしていいのか分からず、手をつかねて眺めているといったかっこうだった。しのカムチャッカ自身も、煙突を吹っ飛ばされて黒煙をあげていた。
この海域には無数の忠誠と勇気と臆病と裏切りが発生したが、ロジェストウェンスキーは、彼にとって自分に忠実な男として可愛がっていた一人の五十男に裏切られていた。駆逐艦ベドーウィの艦長N・W・バラノーフ中佐だった。
ロ提督がなぜ数ある駆逐艦の艦長の中でこの男だけを愛したのか、彼がロシア皇帝の代理者として演じたこの大海戦という叙事詩の中での疑問の数行とされている。
ロ提督はベドーウィを通報艦に選んでいた。伝令者としてあるいは秘書として、通報艦の艦長というのは無能な艦長ではつとまらなかったし、また海戦中、旗艦に敵の砲弾が集中するため、その旗艦のそばにいることを義務づけられている通報艦の艦長というのはよほど勇気のある男でなければつとまらなかった。上村における通報艦千早の艦長江口鱗六中佐はおyくその任務を果たしたが、ロジェストウェンスキーにおける駆逐艦ベトーウィのバラーノフほどこへ行ったのか、行方をくらましてしまっているのである。
バラーノフ中佐は艦隊幹部の中ではもっとも評判の悪い男だったが、ロ提督にだけは物売りの商人のような態度でとり入っていた。ロ提督も、
「すべての艦長はバラーノフに見習え」
と言ったりして彼が激賞する唯一人の艦長であったが、しかしバラーノフは実は機械の軍艦というものには素人で、艦長級ではめずらしく海軍兵学校も出ていなかった。
砲術も、魚雷も知らず、信じられないことだが艦長の主要任務である操縦も下手で、彼は自分の艦を繋留するのにつねに二十分も三十分もかかると言われていた。
ロジェストウェンスキーがこのような人物を寵愛したのは、ひょっとするつ海戦中旗艦がやられた場合には自分を収容してくれる男として期待していたのかもしれない。むろんその期待は見当外れなものではなかった。侍女のように旗艦にくっついて来るベドーウィには看護婦としての義務も当然背負わされていた。
|