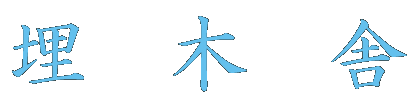加藤友三郎は、三笠の艦橋でたえずからだの位置を移していた。相変らず神経性の胃痛が間歇的
に彼をおそい、からだを動かすことによって痛みをなだめようとした。加藤は双眼鏡をのぞきっぱなしだったが、この時、レンズに拡大されて映っている敵旗艦スワロフの艦首がわずかに北へ動くのを見て狼狽した。
彼は後年もまるで冷血動物のように表情を変えないと言われたが、この時ばかりはその小さな、ちょうど萱かや
で切ったような両眼に色が走った。このことを彼は予感していたのである。予感していたことが、つい彼の先入主になった。敵艦隊が北走するのではないか、ということである。ところがその予感どおりにスワロフが北へ回頭しはじめたのである。加藤ほどの男が、この進行中の事実を冷静に観察するよりも、自分の予感の方に判断を短絡たんらく
させてしまった。
加藤は、切り裂くように真之を振り返った。
まずいことに真之は、双眼鏡を持っていなかった。
「肉眼で見る方が確かなところが分かる」
というこの天才的な男の一種神秘性を持った肉眼信仰が、この場合ばかりは役に立たなかった。スワロフの艦首の微細な変化など、肉眼でとらえられるはずがなかった。
加藤が真之の同意を得るべく振り返った時、真之はその両眼をするどく光らせてはいたものの、しかしあご・・
だけはしきりに動いていた。例の空豆の煎ったのをポケットから取り出しては、噛み砕いているのである。
(このばかが。 ──)
と、加藤はあとあとまでこの時のことを思っては腹が立った。真之はたしかに天才的な設計者であったであろう。しかし天才というのはその半面暗いいびつさを持っているものかも知れず、現場での運営指揮ということとは別なものであるかのようだった。
加藤は、東郷の横顔を覗き込んだ。
東郷はそのプリズムの双眼鏡によって、より大きな像としてのスワロフをとらえていた。東郷もまた、加藤と同じことを思った。敵はわが艦隊の列後にまわって北走すべく回頭したのではあるまいか。
これを扼やく
する必要があった。
「こちらも、左八点の一斉回頭をしましょうか」
と、加藤は砲声の中でどなった。
東郷は双眼鏡をのぞきつつうなずいた。
「左八点、一斉回頭。──」
加藤は、甲高い声をはりあげた。
三笠のマストに、旗旒信号が点々と揚がった。
その信号の意味は、各艦が各個に、そして同時に左へ九十度針路を変えよ、ということであった。後続する各艦がおんじ信号をつぎつぎに掲げた。 |