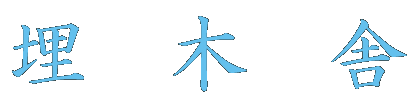それでもなおロシア側はかろうじて陣形を保つつ進んだ。主力艦のほとんどが火炎を背負っており、黒煙は艦隊をおおった。ある艦は列外へよろめき出、ある艦は浮かぶ廃墟同然になりながらも艦体だけが航走していた。だがなお射撃可能な砲は火光をたばしらせて砲火を歇
めようとはしなかった。
「記録のため」
という目的で旗艦スワロフ艦内のあちこちを駆け回っていたセミョノーフ中佐は、もう一度上甲板に出て日本艦隊を見ておこうと思った時期がある。
上甲板へおどり出た彼は、まず火と戦わねばならなかった。死体を避けねばならず、こわれきった構造物と構造物との間をすり抜けねばならなかった。彼は艦首へ出ようとした。
(日本艦隊も相当やられているはずだ)
と、彼の古参仕官としての堅牢な想像力がそのように彼を予想させた。
彼は艦首へ近づいた。十二インチ砲と六インチ砲との間の右舷に出ると、前方の海が展望できた。日本艦隊はいた。
「ところが、敵艦隊は、最初見た姿とまったく同じ姿でわれわれの前途にいたのである。火災もなく、傾斜をおこしている艦もなかった。一艦といえども艦橋を破壊されいる艦はなかった。彼らにとってあたかもこれは戦闘ではなく、射撃演習のようであった」
さらにセミョーノフは言う。
「わが艦隊は殷々いんいん
として砲声をとどろかせること三十分におよんでいる。この間かん
、大量の砲弾を発射したはずであったが、あのぼう大な砲弾は一体どこへ行ったのであろう」
セミョーノフはその原因を砲弾の威力に求めようとした。彼によればロシア製の砲弾は粗悪で不発弾が多かったのではないかという。たしかに日本側の観測でもロシア砲弾には不発のものもあった。しかしセミョノーフが呪うほどあったわけではに。
セミョノーフはさらに日本が発明した新砲弾の威力を過大なほどに評価した。
「日本の砲弾は普通の綿火薬でなく下瀬火薬を用いている。大ざっぱに言えば、炸裂せる日本砲弾の破壊力はロシア砲弾の十二個ぶんの威力を持っていた」
とセミョノーフは、日本の持つ物理的な力にすべての原因を帰せしめようとしたが、その動機の一つは彼がロジェストウェンスキーの記録者として、その提督の戦術が拙劣であったということを覆いたいというところから出ていた。
これに対し、東郷は巧妙すぎた。
両艦隊は、運動している。双方航走しつつ戦う以上、東郷にすればよほど運動を巧妙にしなければ敵をとり逃がすおそれがあったが、彼は双方の形態の変化によって運動を変えつつも、つねに敵の前面を押さえ込んで行くという彼の主題をかたくまもりつづけた。この運動方法を、秋山真之は古水軍から言葉をとって、
「乙字戦法」
と名づけていた。艦隊そのものが乙字運動をくりかえすのである。このため、ロシア側のある幕僚は悲鳴をあげるように、
「三笠はいつもわれわれの前面にいた」
と、魔術師の魔法を見たように語っている。
|