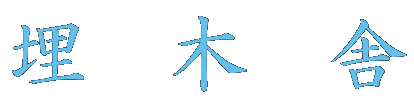旗艦スワロフの前部艦橋にいるロジェストウェンスキーは、東郷が彼を発見すると同時に彼も東郷の三笠の艦影を濛気のむこうに発見した。
「閣下、ご覧なさい。東郷は八月十日とおなじ陣形でやって来ています」
と、ロジェストウェンスキーに向かって叫んだのは、記録係の幕僚で、人の三倍も脂肪を抱え込んでいるウラジミール・セミョーノフ中佐であった。
セミョーノフ中佐は多少文筆の才能はあったが、彼は不幸なことに艦体作戦やその他の艦体勤務に不可欠の人物であるとは思われていなかった。彼は作戦会議から疎外されていただけでなく、いかなる勤務にもつけてもらっていなかった。彼はこの不名誉を憤懣
のかたちでつねに持ち、彼の仲間全員を呪のろ
わしく思っていただけでなく、それを終生、忘れなかったという驚嘆すべき執拗しつよう
さをもっていた。
しかしながらこの孤独な作戦作家の救いは、ただ一人の人間に対してのみ、そのあらゆる欠点をむしろ長所であるとして見てやる情愛を持っていたことであった。ただ一人の人間とは、司令長官ロジェストウェンスキーのことである。
ロシアの海軍省が彼に期待していた仕事は、この大艦隊が演じつつある世界史的な壮挙を、その名文によって後世に残すことであった。
しかし結果としては、記録者としての彼の才能は乏しかったといわざるを得ない。彼の文章は、造船技師ポリトゥスキーがその新妻に宛てて送りつづけた手紙の文章にくらべ、はるかに粗雑で、しかも記録性の乏しいものであった。
「ロジェストウェンスキー航海」
とと呼ばれる長期の大航海の記録については、セミョーノフはまるっきり怠ってしまっていたし、またロシア人が軍艦という近代技術の粋を集めた物体に乗って海に浮かんだ場合の無数の課題については何等ふれるところがなかった。
セミョーノフは、軍人としても記録者としても分析能力を欠いていたが、ただ一種の精神を牢乎ろうこ
として持っていた。
「この艦隊は必ず勝つ」
という信念である。その信念は皇帝への忠誠心と愛国心から出ていたが、しかしひょっとすると厳密な意味での愛国心ではなく、自己愛が単に拡大されたものとしてのそれだったのかも知れない。彼は冷静な観察者というよりも、熱っぽい叙事詩的文藻ぶんそう
の持ち主で、英雄詩を書くにはあるいはふさわしい人であるかも知れなかった。事実、彼はこの日本海においてロジェストウェンスキーをたたえる英雄詩を書くつもりであり、今から起こる海戦は彼のとって、起こる以前から主題が決まっていた。つまり偉大なる統率者であるロジェストウェンスキーが、東郷とその艦隊を海底へたたき沈めてしまうことである。
そういう雄大な
「詩」 をセミョーノフ中佐が書く予定・・
にしているということは大英雄の予定者であるロジェストウェンスキー自身はむろん知っており、そういう詩人を軍隊が伴って行くというのはロシアの習慣でもあり、習慣であればこそロジェストウェンスキーはべつに気羞きはず
かしさのようなものは感じていなかった。
この大艦隊のどの軍艦にも世界を征服すべき義務を象徴する聖アンドレーエフの軍艦旗が翻っていたが、その軍艦旗にもっともふさわしい人物がこの詩人中佐であり、彼は、彼の詩を成立さsるにはともかくも彼の提督に勝ってもらわねばならないのである。 |