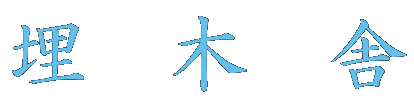ロシア側に、目を移す。
第二戦艦船隊の最後尾を航走している装甲巡洋艦ナヒーモフの士官であったザチョールツイの手記の文章を借りると、
「日本の艦隊が、わが左舷の方角より出現したのは、一九〇五年五月二十七日午後一時三十分
(註・実際は三十九分) であった。そのときバルチック艦隊は海峡のもっとも狭い所にいた」
── 海峡のもっとも狭い所にいあた。
というのがいかにも自然に存在したように書かれているが、東郷とその幕僚が敵とこの場所で落ち合うべく計算し、行動していたのである。
「兵たちはずっと前に昼食をすませていた。少し落ち着いた連中は、食後の一休みをしていた」
と、言う。
たしかにロシア人たちの神経は、巨大な運命を前にして意外なほどに余裕を持っていた。
たとえば第一戦艦船隊の戦艦アリョールにいたっては、ロシア海軍の習慣である昼食後の午睡さえとっている者がいたのである。その習慣がこの日もまもられた。午睡の終了は、午後一時二十分であった。号令で終了が告げられた。午睡のあとは、ロシア人の日常生活に欠くことのできないお茶を飲む許可がある。ロシアの軍艦には、ロシアのどの家庭にもある銅製の湯沸かし器が積まれていた。午睡終了の後は、
「茶を飲め。──」
という号令がかかる。兵員たちはそれぞれ湯呑を手にして、巨大な湯沸かし器のそばへ行くべく駈けた。人間が、その精神の秩序と安定をまもるためにはいかなる場合でも習慣というものから切り離されてしまってはいけないという鉄則でもそこにあるかのようで、号令も、号令につられて走って行く兵員も、そして熱い液体を食道に流し込む生理的作業も、普段とまったく変わりがなかった。
ただし、この時刻には日本艦隊は出現しておらず、兵員たちが茶を唇につけてあと少なくとも十分以内に現れるのである。
「日本艦隊は単縱陣を組み、非常な速力でもってわが第二「戦艦船隊後方の運送船の方向に向かって進航しつつあった」
要するに東郷艦隊は南下してきた。バルチック艦隊は北上しつつある。さらに東郷艦隊はザチョールツイが
「わが第二戦艦船隊の」 といっているように、バルチック艦隊の脆弱部
とみられる左翼 (第二、第三戦艦船隊) に向かってやって来たのである。
戦艦アリョールの前部上甲板には、士官や兵員が集まって、日本艦隊を見ようとしていた。
「あれは三笠じゃないか」
と、叫んだ士官の声が印象的であった。
まだ日本のすべての勢力を見ることが出来ず、先頭の艦影とそれにつづく十隻ばかりが見える程度であった。その先頭に三笠が波を蹴立てているというのが、なにかまぼろしを見ているような不思議さを全員に与えた。
三笠は旅順の封鎖作戦中に、機雷に触れて沈んだものと信じられていたのである。
「そんな馬鹿な」
と否定する士官もいたが、日本の艦型を諳記あんき
しているたれもが、それが三笠であると認めざるを得なかった。そのとき、天を覆っていた雲がわずかに切れ、強い太陽が海面を照らした。たしかに三笠であった。濃灰色の三笠は、おりから降りそそいできた光線の束に照らされ、青く輝いているように見えた。 |