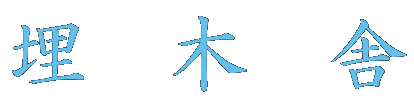当時の水雷艇というのは、およそひどい乗物であった。
汽罐
をたいて煙突一本で走りまわっているハシケのようなもので、魚雷を何本か抱いている。刺し違えの覚悟で敵の大艦の舷側にぶつかるほどに接近し、魚雷を発射して逃げるのだが、その成功にはよほどの勇気と幸運を必要とした。
「平素は軍港付近の津々浦々や、島々の間の狭い瀬戸を縫って走りまわり、ときどきその辺りの岩に舵かじ
をひっかけて曲げたりしますと、艇を石崖に寄せて浜辺の村鍛冶を呼び、叩き直してもらってさらに走るというようなものでした」
と正木生虎氏は語っている。生虎氏の亡父は正木義太中将で、日露戦争の旅順閉塞のとき大尉で参加して負傷した。正木義太は明治三十三、四年ごろ生虎に語ったのが右の内容である。
この当時、日本の海軍では水雷艇乗りのことを、
「乞食商売」
といっていた。服装が汚く、食事が粗末で、厠かわや
もなく、居住性という点では惨澹さんたん
たるものであった。そういう彼らをささえてうるのは、短刀一本で敵艦を抱き刺しにする海の刺客という誇りだけであった。
日本側は水雷艇の数が多かった。
この五月二十七日までにとくに対馬の尾崎湾に待機していた水雷艇たちは、長い月日を哨戒勤務についやしてきたために艇体の塗料が剥げ、煙突と艇尾の旭日旗がなければ朽ちた丸太が浮かんでいるようであった。
対馬の尾崎湾に待機しているこれらの水雷艇に出港用意が命ぜられたのが、二十七日の払暁である。
「総員起し。出港用意」
と、どの艇でも号令が発せられた。午前五時四十分、いっせいに錨をあげた。揚錨機キャプスタン
ががらがらと鳴り、汽罐が燃えはじめた。
外洋に出ると風がひどく、艇を呑み込むような大波が間断なく押し寄せ、挺身は前後左右に揺れた。艇上のコンパス台に立っている士官は柱にしがみつきながら指揮をとっているのだが、もし放せばたちまち海面にほうり出されるはずであった。しぶきがたえず全身を洗ってゆくのでふつう合羽とゴム長をはいているのだが、それらは戦闘動作をさまたげるため、たいていの士官は江戸時代の盗賊のように手拭でほっかぶりをし、ズボンをたくしあげて足には足袋をはき、首筋から海水が入らぬように手拭をぐるぐる巻きにしていた。
この第三艦隊司令部では、この風浪を押して水雷艇を連れて行くかどうかについてだいぶ議論が阿多。むしろ主力が先発し、波の静まるのを待って彼らを後発させればいいのではないかという意見もあったが、司令長官の片岡七朗は、
「気の毒だが、連れて行こう」
と、断を下した。
旗艦の厳島から見ると、水雷艇群が波間をかいくぐったりスクリューを天にあげたりしながら懸命について来るのが見える。
「あまり気の毒で、なるべく見ないようにしていた」
と、厳島乗組みの参謀百武三郎少佐はのちに語っている。この第三艦隊の第五、第六戦隊は老朽艦ばかりでとてもバルチック艦隊には対抗できない。ただ水雷艇を随伴していると敵が甘くみないためで、彼らが何割途中で風浪のために沈没しようとも連れて行かざるを得なかったのである。
|