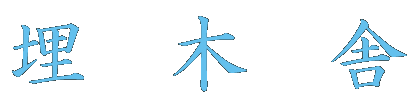実之助は、これぞまさしく、宇佐八幡宮の神託なりと勇み立った。彼はその老僧の名と、山国谿に向かう道を聞くと、もはや八
つ刻どき を過ぎていたにこかかわらず、必死を力で双脚そうきゃく
にこめて、敵かたき の所在ありか
へと急いだ。その日の初更近く、樋田村に着いた実之助は、直ちに洞窟へ立ち向かおうかと思ったが、焦あせ
ってはならぬと思い返して、その夜は樋田駅の宿に、焦慮の一夜を明かすと、翌日は早く起き出でて、軽装して樋田の刳貫へと向かった。
刳貫の入口に着いたとき、彼はそこに石の破片かけら
を、運び出している石工にたずねた。
「この洞窟の中に、了海といわるるご出家が、おわすそうじゃが、それに相違ないか」
「おわさないでなんとしよう。了海さまは、この洞ほら
の主も同様な方じゃ、ハハハ」 と、石工は心なげに笑った。
実之助は、本懐を達すること、はや眼前にありと、よろこび勇んだ。が、彼は周章あわ
てては、ならぬと思った。
「して、出入の口はここ一箇所か」 と聞いた。敵に、逃げられてはならぬと思ったからである。
「それは知れたことじゃ。向こうへ口を開けるために、了海さまは塗炭の苦しみをなさっているのじゃ」
と、石工が答えた。
実之助は、多年の怨敵おんてき
が、嚢中のうちゅう の鼠ねずみ
のごとく、目前に置かれてあるのを喜んだ。たとい、その下に使わるる石工が、幾人いようとも、斬き
り殺すになんの雑作ぞうさ もあるべきと、勇み立った。
「其方そち
に少し頼みがある。了海どにに、御意得たいため、はるばると尋ねてまいった者じゃと、伝えてくれ」 と言った。
石工が、洞窟の中へ入ったあとで、実之助は一刀の目くぎを湿した。
彼は、心の内で、生来初めてめぐりあう敵の容貌ようぼう
を想像した。洞門の開鑿かいさく
を、統領していると」いえば、五十は過ぎているとはいえ、筋骨たくましき男であろう。ことに、若年のころには、兵法に疎うと
からざりしというのであるから、ゆめ油断はならぬと思っていた。
が、しばらくして実之助の前面へと、洞門から出て来た一人の乞食僧こじきそう
があった。それは、出て来るというよりも、蟇がま
のごとくはい出て来たというほうが、適当であった。それは人間というよりも、むしろ人間の残骸ざんがい
というべきであった。肉ことごとく落ちて骨あらわれ、脚あし
の関節以下はところどころ爛ただ
れて、長く正視するにたえなかった。敗れた法衣ころも
に依って、僧形とは知れるものの、頭髪は永きのびて皺しわ
だらけの額をおおうていた。老僧は、灰色をなした眼まなこ
をしばたきながら、実之助を見上げて、
「老眼衰えはてまして、いずれの方ともわきまえかねまする」 と、言った。
実之助の、極度まで、張りつめてきた心は、この老僧を一目見た刹那タジタジとなってしまっていた。彼は、心の底から憎悪を感じうるような悪僧を、欲していた。しかるに彼の前には、人間とも死骸ともつかぬ、半死の老僧がうずくまっているのである。実之助は、失望しはじめた自分の心を励まして、
「そのもとが、了海といわるるか」
と、息ごんで聞いた。
「いかにも、さようでござります。して其許そのもと
は」 と、老僧はいぶかしげに実之助を見上げた。
「了海とやら、いかに僧形に身をやつすとも、よも忘れはいたすまい。汝なんじ
、市九郎と呼ばれし若年の砌みぎり
、主人中川三郎兵衛を打って立ち退いた覚えがあろう。某それがし
は、三郎兵衛の一子実之助と、申すものじゃ。もはや、のがれぬ所と、覚悟せよ」
と、実之助の言葉は、あくまでも落ち着いていたが、そこに一歩も、許すまじき厳正さがあった。
が、市九郎は実之助の言葉を聞いて、少しも驚かなかった。
「いかさま、中川さまのご子息、実之助さまか。いやお父上を、打って立ち退いた者、この了海に相違ございませぬ」
と、彼は自分を敵とねらう者に逢ったというよりも、旧主の遺児わすれご
に逢った親しさをもって答えたが、実之助は、市九郎の声音こわね
に欺かれてはならぬと思った。
「主しゅ
を打って立ち退いた非道の汝を打つために、十年に近い年月を艱難のうちに過ごしたわ。ここで会うからは、もはやのがれぬ所と、尋常に勝負せよ」 と、言った。 |