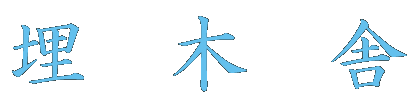一年経ち、二年経った。一念の動くところ、彼の痩せた腕は、鉄のごとく屈しなかった。ちょうど、十八年目の終わりであった。彼は、いつの間にか、岩壁の二分の一をうがってうた。
里人は、この恐ろしき奇跡を見るとを見ると、もはや市九郎の仕事を、少しも疑わなかった。彼らは、前二回の懈怠
を、心から恥じ、七郷の人々合力のまことを尽くしてこぞって市九郎をたすけはじめた。
その年、中津藩の郡奉行こおりぶぎょう
が、巡視して、市九郎に対して、奇特の言葉を下した。近郷近在から、三十人に近い石工が集められた。工事は、枯葉を焼く火のように進んだ。
人々は、衰残の姿いたいたしい市九郎に、
「まはや、そなたは石工どもの統領たばね
を、なさりませ。みずから槌を振うには及びませぬ」 と、すすめたが、市九郎は頑として応じなかった。彼は、たおるれば槌を握ったままと、思っているらしかった。彼は、三十の石工が、かたわらに働くのも知らぬように、寝食を忘れ、懸命の力を尽くすこと、少しも前と変わらなかった。
が、人々が市九郎に、休息をすすめたのも、無理ではなかった。二十年にも近い間、日の光も射さぬ岩壁の奥深く、すわりつづけたためであろう。彼の両足は、長い端坐に傷いた
み、いつの間にか屈伸の自在を欠いていた。彼は、わずかの歩行にも杖にすがらねばならなかった。
そのうえ、長い間、闇に坐ざ
して、日光を見なかったためでもあろう、また不断に、彼の身辺に飛び散る砕けた石の破片かけら
が、その眼を傷つけたためでもあろう、彼の両眼は、朦朧もうろう
として光を失い、物のあいろもわきまえかねるようになっていた。
さすがに、不退転の市九郎も、身に迫る老衰を痛む心はあった。身命に対する執着はなかったけれど中道にして倒れることを、なによりも無念と思ったからであった。
「もう二年のしんぼうじゃ」
と、彼は心のうちに叫んで、身の老衰を忘れようと、懸命に槌を振うのであった。
おかしがたき大自然の威厳を示して、市九郎の前に、立ちふさがっていた岩壁は、いつの間にか衰残の乞食僧一人の腕に貫かれて、その中腹をうがつ洞窟は、命ある者のごとく、一路その核心を貫かんとしているのであった
|