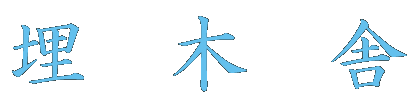戦艦三笠は鎮海湾の底に錨をおろし、白っぽい海面にえぐったようない濃い暗緑色の影をおとしていた。
この春は桜も桃も一時に咲いた。春がすぎて、陽ざしが日に日に強くなり、すでに海に照り映える太陽は初夏のものであった。
三笠の吃水線
がいつもよりも沈んでいるのは、英炭を満載して上甲板まで積み上げているためであった。三笠の隣には戦艦敷島がいる。さらにその付近に朝日もいたし、春日もいた。みな舷が低くなるほどに石炭を腹いっぱい積んでいたし、鎮海湾から加德水道にかけて点々と浮かんでいる大小の艦はみな同じ状態であった。
「敵が太平洋をまわる公算大」
という秋山真之ら艦隊幕僚の不安が、この石炭満載の景況を生み出したのである。敵がその不幸な
(東郷艦隊にとって) コースをとれば大急ぎで日本海を北上して青森県の日本海沖で待ち伏せするための燃料であった。もし敵が対馬コースをとってやって来れば不要になる燃料である。
「その時は海へ捨てればよい」
と、真之は考えていた。
真之の心気はこの時期乱れつづけ、敵のコースを予測するについての不動の判断というものがなかった。彼のこの時の神経と頭脳の極度の疲労がその後の短い余生をずっと支配しつづけるのだが、この時期の懊悩おうのう
ぶりはその行動に常軌を失わせたほどであった。
たとえば彼は靴をはいたまま眠った。
彼の上司である加藤友三郎参謀長が、
「そんなことをしていては体がもたない」
と、見かねて忠告したが、真之はその加藤に顔をじっと見つめているだけで、加藤の言葉が耳に入らないようでった。その加藤も、神経性の胃痛がはげしく断続して夜中しばしば目が醒め、またある参謀の如きは尿が出なくなるという奇妙な生理現象をおこした。
「いっそ能登半島の沖で待ってはどうですか」
と言い出す若い参謀もいた。
なるほど能登半島なら敵が北へまわろうが南から来ようが、ちょうど真ン中になって両端いずれに駈けて行こうとも便利である。
が、それには致命的欠陥があった。海戦の時間が短くなるということである。敵が対馬から来る場合、ウラジオストックまでの間、七段の構えで合戦
(戦闘・海軍用語) をくりかえし、敵を全滅させるという目的の達成が不可能になる。能登半島から出発すればせいぜい一回か二回の合戦しか出来ないのである。
「かならず敵は対馬から来る」
という信念を堅持したのは東京の大本営と、第二艦隊の幕僚、または第四駆逐隊司令の鈴木貫太郎たいわば作戦中枢から遠い場所もしくは岡目八目というその岡目の位置にうた連中で、そういう位置にいるために客観的判断も可能であり、物事を巨視的に見ることも出来、さらには小さな現象に心をおびえさせる度合いがより少なく済むのである。東郷のそばにいる幕僚たちはそうはいかなかった。決定は東郷がするにせよ、彼ら幕僚の判断によって国家の存亡が決まってしまうという心理的重圧感が、彼らを羅針盤の針のようにこまかくふるえさせつづけていたのである。 |