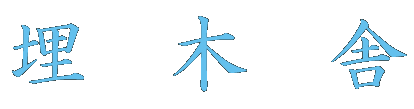乃木の日記の七日の項、つづく。
「・・・・・志賀アリ、詩談」
と、簡潔に書かれている。志賀アリ、というのは、児玉の部屋をあけると、志賀がいた、ということである。
志賀重昂
のことである。
ここで、 「志賀」 について説明しなければならない。
明治陸軍は、外国陸軍の模倣から出発した。外国陸軍にあっては (海軍もそうだが)
大戦を遂行する場合、高名な文学者を連れて行くことが多い。ひとつにはその理由で、志賀重昂を、勅任官待遇の観戦員として乃木軍司令部に従軍させた。勅任官の説明はむずかしいが、例でいえば各省次官、府県知事といった官吏であり、勅任官相当の待遇を受けるクグループには大学、専門学校、高等学校の教授がある。
文学者といっても、明治政府の感覚では、外国の場合のように、小説家などを勅任官待遇にして観戦員にはしない。当時の分類でいう硬文学の徒から選ばれた。それも無冠の硬文学者は選ばれない。志賀重昂はジャーナリストであったが、一時官途について農商務省山林局長や外務省勅人参事官をしたこともある。この経歴のおもしろさが買われて、観戦員に選ばれた。が、文章家としても、識見の人としても、当時、日本における屈指の人物であったことには間違いない。
彼は文久三
(一八六三) 年、三河岡崎に生まれ、北海道大学の前身である札幌農学校を出た。とくに興味があったのは、地理学であった。
明治十九年、海軍兵学校の卒業航海に随行し、練習艦
「筑波」 で南洋諸島をまわり、南洋諸島における列強の植民地経営を観察し、経世的立場からの地理学という、彼の学問の独創的な基礎をつくった。この時の著書が 「南洋時事」
で、要するに 「国家は生産力を増強せざるべからず」 という論旨によって、当時浮薄な・・・
政争に明け暮れていた政界と言論界に衝撃を与えた。
この立場は晩年、地理学者として英国王立地理学協会名誉会員になるにいたるまで終始かわっておらず、彼もまた明治のこの新興国家の象徴的人物であったであろう。ジャーナリストとしての志賀重昂の活躍舞台は、彼がつくった雑誌
「日本人」 と、陸羯南や正岡子規のいた新聞 「日本」 、 「東京朝日新聞」 などであった。
さらに明治陸軍が彼を乃木軍司令部に従軍させた理由のいま一つは、英文がうまいことであり、ロシア軍に対して降伏勧告文を書いたり、あるいはステッセルが降伏してきた場合の通訳をする事であり、またさらには必要以上に戦時国際法の優等生たろうとした日本陸軍としては、そのルールを知っている志賀を乃木につけることによって、その点の誤りをなからしめようとした。
志賀はこの時、四十二歳である。ロンドンで作ったという古ぼけたフロックコートを着ていた。
児玉が、乃木との詩会に志賀を呼んだのは、志賀を評者にして興を添えるためであった。彼は漢詩人としても、この当時多少の評価はうけていた。
部屋の天井から長いひもが垂れて、その先にランプがぶらさがっている。児玉は、そのランプの下で、小さな手帳を繰っている。
「詩稿やね」
と、乃木は微笑し、児玉の手帳をのぞきたそうなしぐさをした。
「あ、見ちゃいかん」
と、児玉は変にはずかしそうに、ランプの下から手帳を遠ざけた。志賀が声をあげて笑い、児玉の背後にすわっている随員の田中国重少佐までがくすくし笑った。
「田中、なにがおかしい」
児玉は、その癖で、唇をへの字にまげたとき、遠い砲声が、つづけさまにとどろいた。
「乃木よ」
と、児玉は言った。
「わしのはまだ推敲すいこう
ができちょらんのじゃ。それよりおぬしから披露ひろう
せい」
「わしのもまだ粗稿じゃ」
と言いながら、乃木はポケットから手帳をとりだした。
田中国重が、硯すずり
と紙を持って来た。
乃木はその紙へ、みごとな筆蹟で自作の詩を書いた。
有死無生何足悲
千年誰見表忠碑
皇軍十万誰英傑
驚世功名是此時
この詩は、この日乃木が高崎山から柳樹房へ戻るまでの間、馬上で即吟したものである。
「これはええ」
と、児玉は心から感心した。
「ぬしの山川草木さんせんそうもく
は悲傷の気持が満ちちょるが、この詩はいかにも三軍の将らしく英気溌剌はつらつ
たるものしゃ」
児玉は、訓よ
みくだした。
死あって生なし何なん
ぞ悲しむに足らん
千年誰か見ん表忠碑
皇軍十万誰か英傑
世を驚かすの功名これ此の時
意味はこうであろう。
「この戦場にあっては死のみあり、生はない。が、それは少しも悲しむに足りない。どうせ人生は短いのである。無形の表忠碑こそ先年の風霜ふうそう
に耐えるものではないか。皇軍十万、ことごとくが英傑であり、世を驚かす功名こそこれこのときである。・・・・」
「しかし」
と、児玉はくびをひねった。
「千年誰か見ん表忠碑というのは、なにやら物悲しすぎるようだ。千年朽ちず
(千年不朽) とすればどうか」
と、臆面もなくいうと、乃木は素直に、
「ああ、そうかもしれん」
と言って、すぐ二字を消し、千年不朽表忠碑とし、
「石樵せきしょう
」
と、署名を入れた。石樵とは乃木の号で、べつに石林子とも号した。 |