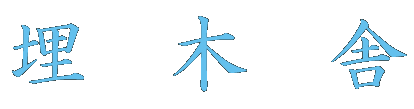十二月十五日になった。
陣地移動を完了した攻城砲は早暁から砲撃を開始した。
同時に、二〇三高地の砲塁は咆哮し、そのうしろ
(東方) にある椅子山の砲台からも、巨弾が二〇三高地の頂上越えに降ってきた。それらが日本軍歩兵壕に次々に落下し、土砂や銃器、人間ときには古い死体を天へ噴き上げた。新陣地についた日本軍の攻城砲の巨弾も、それに対して今日からは沈黙していなかった。報復のために椅子山のベトンに向かって殺到した。
遠くの敵塁からの砲弾は、轟っと遠雷のような音をひきながら飛んで来る。落下するまで数秒を数える事が出来た。これに対し、日本軍の重砲は、射撃距離が短くなったため、
「くわっ」
と、短く咆哮したかと思うと、すぐ敵陣での爆発音がおこった。発射音と爆発音とが、殆ど同時であった。このことが、山腹で突撃姿勢をとっている歩兵の士気をいちじるしく高めた。
この時、児玉は二〇三高地の近くの丘に登りつつあった。椅子右から送られて来る砲弾が、その前後に落下した。児玉は、歩兵の一等卒のごとく山頂に向かって駈けた。そのうしろから、ぞろぞろと参謀懸章の群れがついてくる。軍司令部の参謀もいれば、指弾参謀もいた。第一と第七の師団長もいた。それらの副官もいる。これだけの多数の乃木軍の作戦頭脳が、一時に弾雨をくぐったのは、初めてであった。
児玉のそばに、随行の田中国重少佐が、灰褐色の山土を踏みながら、児玉をかばうようにして行く。そのあとに、砲弾の破片が無数に散らばっていた。小男の児玉を抱くようにして進んでいるのは、少将福島安正であった。このシベリア単騎横断を遂げた男は、おれは空気のようなものだ、という言葉を、いつか吐いた。意味はよく分からないが、自分自身が空気のようになってしまえばシベリアでも横断出来るし、弾の中でも平気で歩くことが出来る。そういうことかも知れない。
山頂に達した児玉はそこで伏せ、稜線に双眼鏡を出して二〇三高地を頂上を近々と展望した。死んでいる者、生きて動いている者がよく見えた。山頂の一角をなおも死守している百人足らずの兵の姿が、児玉には感動的であった。彼らは高等司令部から捨てられたようなかたちで、しかもそれを恨まずに死闘をくりかえしている。
「あれを見て、心動かさぬ奴は人間ではない」
と、児玉は横の福島に言った。参謀なら、心を動かして同時に頭を動かすべきであろう。処置についてのプランが沸くはずであった。頭の良否ではない。心の良否だ、と児玉は思った。
そう思ったために、彼の有名な怒声の場面が、そのつぎに炸裂するのである。
なぜなら、ぞろぞろあがって来た師団長や参謀たちは、なにか義務的にこの上まで登らされたように、ぼんやりしている。
(たれも責任を感じてはいない!)
と、児玉は思った。責任を感じているならこの場でもすぐ処置があるべきであった。ところがみな見学者のような無責任な顔をしている。 |