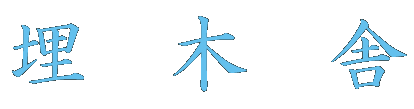(なんと無謀なことを言う人だ)
と、砲兵中佐佐藤鋼次郎は思った。児玉という人は攻城用の重砲を、そのあたりで馬に曳かせている野砲や山砲と間違えているのではないか、と思った。
大砲の化け物と言っていい二十八サンチ榴弾砲はもとより、最後方の火石嶺に置かれている陸戦重砲でも、それを据えつけるについては、一個のビルをつくるほどの基礎工事が必要であった。
であるのに児玉は、オモチャの大砲でも移動させるような口調で、
「すみやかに重砲隊を移動し」
などと言っている。
みな、ぼう然となった面持ちで、沈黙した。
児玉にすれば、この作戦しかないと思っている。要塞を粉砕するに足るあらゆる大口径砲を、二〇三高地の近くに集めてしまって間断なく巨弾を送ることであった。子供でも考えられるほどに、単純な理屈である。
この単純な理屈を、なぜ乃木軍司令部がとっていなかったかということが、むしろ不思議であった。
これについて、児玉は、
(乃木は、専門家に呑まれちょったんじゃ)
と、解釈している。
大本営は、第三軍司令部を編成するに当って、砲兵の権威たちを乃木につけた。
参謀長伊地知幸介少将にしても、砲兵科の出身である。また攻城砲の運用を組織的にやるため、それをまとめて一人の司令官のもとに置いた。第三軍攻城砲兵司令官豊島陽蔵少将が、それである。その豊島の下には、高級部員として、右の砲兵中佐佐藤鋼次郎がいる。ほかに若手の砲兵の権威が多い。要するに銃砲という、陸戦最大の機械を扱う上での最新知識の持ち主が、乃木軍司令部に揃っていると言っていい。
乃木は、安心してその上の載っていたということが言えるであろう。乃木自身、ほとんど近代兵学の研究はしていない。まして砲についての研究などしたことがなかった。専門家を尊重するしか、仕方がなかった。
ところが児玉に言わせれば、
(専門家の言うことを聞いて戦術の基礎を立てれば、とんでもないことになりがちだ)
ということであった。専門家といっても、この当時の日本の専門家は、外国知識の翻訳者にすぎず、追随者の悲しさで、意外な着想を思いつくというところまで、知識と精神のゆとりを持っていない。児玉は過去に何度も経験したが、専門家に聞くと、十中八、九、
「それは出来ません」
という答えを受けた。彼らの思考範囲が、いかに狭いかを、児玉は痛感していた。
児玉はかつて参謀本部で、
「諸君は昨日の専門家であるかもしれん。しかし明日の専門家ではない」
と、怒鳴ったことがある。専門知識というのは、ゆらい保守的なものであった。児玉は、そのことをよく知っていた。
(戦争という至上の要求が、重砲陣地のすみやかな転換と集中を命じているのだ。状況というものは、つねに専門家の思うつぼにははまってくれぬ。重砲陣地の転換と集中が出来ねば、日露戦争そのものが負けるのだ)
と、児玉は思っている。その課題への緊張が、この男の気魄になっていた。 |